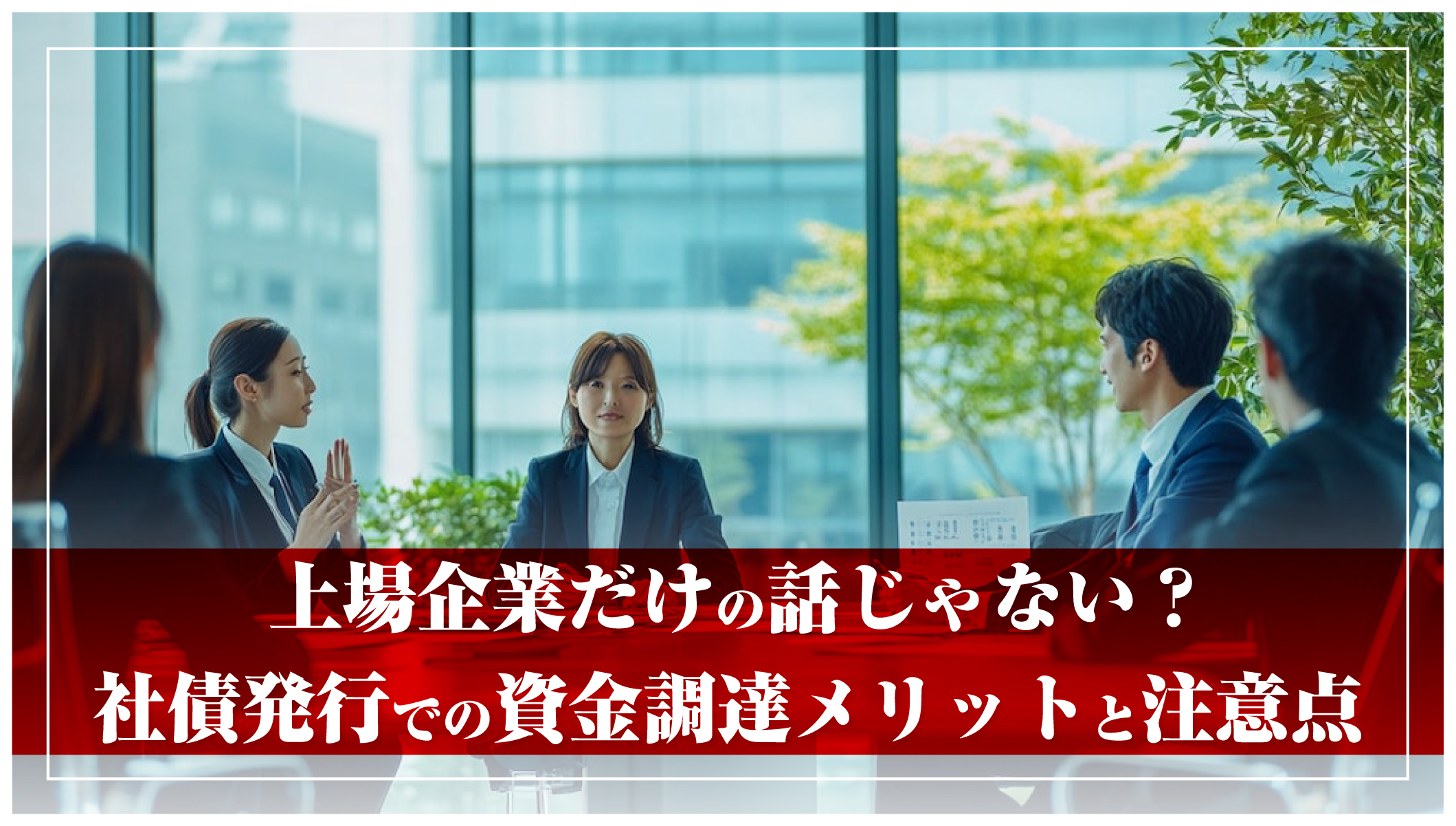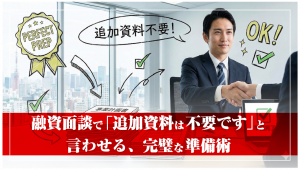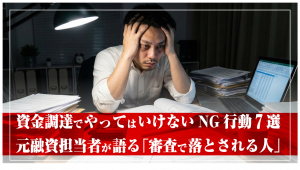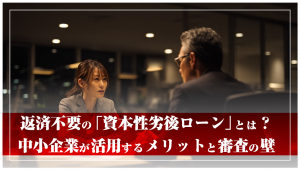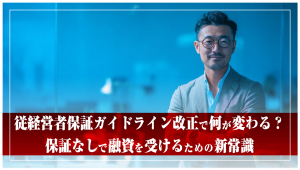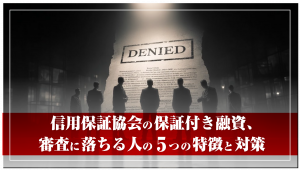「銀行からこれ以上借りるのは難しいと言われた…」
「担保はもう出し尽くしてしまった…」
「経営の自由度を確保しながら資金を調達する方法はないだろうか…」
経営者の皆さん、このような悩みを抱えていませんか?
 佐藤 真由美
佐藤 真由美資金調達は企業経営における永遠の課題です。
特に非上場企業にとって、銀行借入以外の選択肢を持つことは経営の自由度を高める重要な戦略となります。
実は「社債発行」という資金調達手段。これは上場企業だけのものではありません。
中小企業や非上場企業でも活用できる、もうひとつの有力な選択肢なのです。
銀行で融資審査を10年間担当し、その後経営コンサルタントとして中小企業の資金調達を支援してきた経験から、「社債発行」という選択肢の可能性と注意点をお伝えします。
【この記事の結論】社債発行の3つの重要ポイント
- 社債発行とは?
企業が投資家から直接お金を借りる「直接金融」の一種です。特に非上場企業は、縁故者など50名未満を対象とする「少人数私募債」を活用できます。 - 主なメリットは?
原則として担保・保証人が不要で、返済期間や金利を柔軟に設計できます。また、多くは「満期一括返済」のため、月々の返済負担を抑えながら長期安定資金を確保しやすいのが特徴です。 - 注意すべき点は?
満期時に元本を一括で返済する必要があるため、計画的な償還資金の準備が不可欠です。また、銀行融資と違い、業績が悪化しても返済条件の変更は原則として困難です。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
社債発行の基本と非上場企業にとっての可能性
社債とは何か?基本的な仕組みを理解する
社債とは、簡単に言えば「企業が発行する借用証書」です。
企業が資金を調達する方法として、銀行などの金融機関から融資を受ける「間接金融」に対し、社債は投資家から直接資金を調達する「直接金融」に分類されます。
銀行融資と社債発行の根本的な違いは下記の通りです。
| 項目 | 銀行融資 | 社債発行 |
|---|---|---|
| 資金の出し手 | 金融機関 | 投資家(個人・法人) |
| 金利設定 | 銀行の審査で決定 | 発行企業が自ら設定 |
| 返済方法 | 通常は分割返済 | 多くは満期一括返済 |
| 担保・保証 | 多くの場合必要 | 原則として不要 |
| 資金使途 | 制限あり | 比較的自由 |
社債は株式とも異なります。
株式は「出資証券」であり、会社の所有権(株主権)を表すものですが、社債は「債券」であり、あくまで「お金を貸した」という債権を表します。
💡 ワンポイントアドバイス
社債は「借入」の一種ですから、株式発行と違って経営権の分散を心配する必要はありません。出資者を増やすことなく、必要な資金を調達できる点が大きなメリットです。



社債を発行すると、企業は「利息」を投資家に定期的に支払い、満期には「元本」を返済する義務を負います。つまり、銀行借入と同様に「負債」として扱われます。
非上場企業でも発行できる「私募債」の種類
「社債と言えば東京証券取引所に上場している大企業が発行するものでは?」と思われがちですが、実はそうではありません。
上場企業が不特定多数の投資家向けに発行する社債は「公募債」と呼ばれますが、非上場企業でも「私募債」という形で社債発行が可能です。
私募債には以下のような種類があります。
| 種類 | 概要 | 引受先 | 発行条件 |
|---|---|---|---|
| 少人数私募債 | 縁故者など少数の投資家向け | 役員・従業員・取引先など | 勧誘先が50名未満 |
| 銀行引受私募債 | 銀行が引き受ける私募債 | 銀行(信金等) | 銀行の審査基準を満たす必要あり |
| 適格機関投資家私募債 | 機関投資家向け | 証券会社・銀行など | 機関投資家のみが対象 |
特に「少人数私募債」は、中小企業や非上場企業にとって現実的な選択肢です。
経営者の親族や取引先など、企業との関係が深い人物を対象に発行できるため、比較的発行のハードルが低いのが特徴です。
🔍 専門家の見解
私が銀行員時代、多くの中小企業が「社債なんて自分たちには無縁」と思い込んでいました。しかし実際には、年商数億円規模の企業でも少人数私募債を上手に活用しているケースがあります。特に、事業拡大期で銀行融資だけでは資金が足りない企業にとって、有効な選択肢となっています。
社債発行の法的要件と基本条件
社債を発行するためには、いくつかの法的要件を満たす必要があります。
会社法上、株式会社であれば社債発行が可能です。
2006年の会社法施行以降は、合同会社なども社債発行が可能となりましたが、実務上はほとんどが株式会社による発行です。
少人数私募債を発行する場合、特に重要なのは金融商品取引法上の要件です。
- 社債の勧誘先が50名未満であること
- 社債券面の最低単位(例:1口100万円)で分割した口数が50未満であること
- 譲渡制限が付されていること(自由に転売できない)
例えば、1口100万円の社債を発行する場合、4,900万円までなら少人数私募債として発行可能という計算になります(49口まで)。
少人数私募債であれば、金融庁や財務局への届出が不要で、社債管理者(通常は信託銀行等)の設置も不要です。
これにより、発行手続きが比較的簡素化され、発行コストも抑えられます。
⚠️ 注意事項
少人数私募債の発行条件を守らないと、金融商品取引法違反となる可能性があります。特に「50名未満」という条件は厳格に守る必要があります。同一の募集で50名以上に勧誘すると、有価証券届出書の提出義務が生じます。
非上場企業が社債発行を検討すべき状況
銀行借入だけでは限界がある場合
銀行融資は多くの企業にとって資金調達の主軸ですが、次のような限界も存在します。
- 与信限度額の制約: 一般的に、銀行は企業の資本金や純資産の一定倍率までしか融資しないケースが多い
- 担保・保証人の問題: 不動産担保や経営者の個人保証を求められるが、それらを十分に提供できない場合がある
- 資金使途の制限: 「運転資金」「設備資金」など使途が限定され、特に新規事業などリスクの高い用途への融資は厳しい
私がコンサルタントとして支援した製造業A社の例では、銀行からの借入残高が3億円に達し、金融機関からは「これ以上の融資は難しい」と言われていました。
しかし、新規の生産ラインを導入するためには、さらに5,000万円の資金が必要だったのです。
そこでA社は、会長の親族や古くからの取引先など10名から5,000万円の少人数私募債を発行。
これにより新規設備投資を実現し、生産効率の向上につなげることができました。
長期安定資金を確保したい場合
企業の成長には、短期的な資金繰りだけでなく、長期的な視点での投資が欠かせません。
特に設備投資や研究開発、新規事業立ち上げなどは、すぐに収益化できるとは限らないため、長期安定資金の確保が重要です。



社債発行のメリットは、償還期間を自社で設定できる点にあります。
例えば5年満期や7年満期の社債を発行することで、その期間中は元本返済の心配をせずに事業に集中できます。
銀行融資では通常、毎月の返済が必要ですが、社債は多くの場合、利息のみの支払いで済み、元本は満期時に一括返済するため、月々のキャッシュフロー負担が軽減されます。
📝 ポイントまとめ
長期安定資金の確保においては、社債の「満期一括償還」という特性が大きなメリットとなります。ただし、満期時に一度に多額の資金が必要になるため、計画的な資金準備が不可欠です。
資金調達手段の多様化を図りたい場合
「資金調達の卵はひとつのカゴに盛るな」—これは財務戦略の鉄則です。
銀行融資一本に頼った資金調達は、経済環境の変化や金融機関の貸出姿勢の変化に弱く、リスクが高いと言えます。
リーマンショック後や新型コロナウイルス感染症の拡大時には、多くの企業が資金調達に苦労しました。
特に、業績に波がある業種では、業績悪化時に銀行が融資姿勢を厳しくするという「貸し渋り」リスクも考慮する必要があります。
資金調達手段を多様化することで、こうしたリスクに備えることができます。
社債発行は、銀行融資と並行して活用できる有力な選択肢のひとつです。
例えば、サービス業のB社では、資金調達の柱として「銀行融資6割、社債発行3割、リース活用1割」という比率を目安にしています。
これにより、どれか一つの調達手段が使えなくなっても、経営に大きな支障が出ないような体制を構築しています。
社債発行のメリット:なぜ非上場企業にとって魅力的なのか
担保・保証人が不要で調達できる
社債発行の大きなメリットのひとつが、原則として担保や保証人が不要という点です。
銀行融資では、特に中小企業の場合、不動産担保や経営者の個人保証を求められることが一般的ですが、社債はそうした制約から自由です。
これは特に、以下のような企業にとって大きなメリットとなります。
- 担保となる資産が乏しい企業
- 経営者の個人保証負担を軽減したい企業
- 創業間もなく担保資産を築けていない企業
実際の例として、ITサービス企業C社の場合、知的財産が主な資産であり、不動産などの物的担保が少なかったため、銀行からの融資額には限りがありました。しかし、同社は役員や取引先などから少人数私募債を発行することで、無担保で2,000万円の資金調達に成功しています。
担保・保証人が原則不要とはいえ、発行企業の信用力が低い場合には、銀行保証付私募債など第三者の信用補完を活用する方法もあります。その場合、保証料などのコストが発生しますが、調達可能性が高まるというメリットがあります。
返済条件の自由度が高い
社債発行のもうひとつの大きなメリットは、償還期間や利率、利払いのタイミングなどを自社で設定できる点です。
銀行融資では銀行側の審査によって決まる条件も、社債では自社の事業計画や資金繰り計画に合わせて設計できます。
例えば、以下のような設計が可能です。
- 償還期間: 3年、5年、7年など自社の事業サイクルに合わせて設定
- 利率: 市場金利や自社の信用力を考慮して設定(通常は年1%〜5%程度)
- 利払いのタイミング: 年1回、半年ごと、四半期ごとなど
- 償還方法: 満期一括償還が一般的だが、分割償還も可能
私がアドバイスした小売業D社の例では、出店計画に合わせて5年満期、年利2.0%、利払いは年2回、満期一括償還という条件の社債を3,000万円発行しました。
銀行融資では毎月の返済が必要でしたが、社債では利息の支払いだけで済むため、出店初期の資金繰りの負担が大幅に軽減されました。
📊 データポイント
日本銀行の資料によると、中小企業が発行する私募債の平均利率は、2023年時点で年1.5%〜2.5%程度となっています。これは同時期の銀行の長期貸出金利(約1.0%〜1.5%)よりもやや高めの水準です。
企業の信用力向上につながる
社債を発行することは、企業の社会的信用やステータスの向上にもつながります。
「社債を発行できる企業」というだけで、ある程度の信用力や経営基盤があると評価されるのです。
特に銀行保証付私募債の場合、銀行の厳格な審査を通過した証明にもなります。
これにより、取引先や金融機関からの評価が向上し、より有利な条件での取引や融資獲得にもつながる可能性があります。
実際、機械部品製造のE社では、銀行保証付私募債を発行した後、取引先からの引き合いが増加したといいます。
「新聞に社債発行の記事が掲載されたことで、当社の知名度や信用力が高まった」と社長は話していました。
🧠 考えてみよう
あなたの会社が社債を発行したら、取引先や地域社会にどのような印象を与えるでしょうか?現時点で社債発行が可能かどうか、財務状況や信用力を見直してみることも価値があります。
縁故者からの資金調達が可能
少人数私募債の最大の特徴は、経営者の親族や役員、取引先など「縁故者」から資金を調達できる点です。
これにより、銀行融資よりも柔軟な条件設定が可能になり、互いにメリットのある関係構築が期待できます。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 経営者の親族が所有する遊休資金の活用
- 取引先との関係強化(資金の出し手としての協力)
- 役員や従業員の会社への帰属意識向上
飲食店チェーンF社の例では、オーナーの親族や古くからの顧客、取引先など計15名から合計3,500万円の少人数私募債を発行。
年利3.0%という条件は、投資家にとっては銀行預金より高利回りになり、会社にとっても銀行借入より機動的な資金調達が可能になりました。
縁故者からの資金調達であっても、投資家保護の観点からの配慮は必要です。社債の性質や利率、償還条件、リスクなどについて十分に説明し、書面での契約を交わすことが重要です。「親しき仲にも礼儀あり」の精神で、ビジネスライクな関係を維持しましょう。
社債発行の注意点:事前に理解しておくべきリスク
一括償還の負担を計画的に準備する必要性
社債発行の最大の注意点は、満期時の一括償還に備えた計画的な資金準備の必要性です。
銀行融資のように毎月少しずつ返済するのではなく、満期時に一度に全額を返済する必要があるため、その準備を怠ると大きな資金繰り危機に陥るリスクがあります。
例えば、5年満期で5,000万円の社債を発行した場合、5年後には5,000万円を一度に用意する必要があります。
この償還資金を計画的に積み立てておくか、あるいは償還時に借り換え(リファイナンス)するなどの計画が不可欠です。
私の経験では、成功している企業は以下のような対策を講じています。
- 計画的な積立: 毎月の利益から一定額を「社債償還準備金」として積み立てる
- リファイナンス戦略: 満期前に新たな社債発行や銀行融資を確保する交渉を開始する
- 複数回に分けた発行: 全額を一度に発行せず、満期をずらして分散発行する
📝 ポイントまとめ
社債の満期一括償還は、企業にとって大きな資金負担となります。5,000万円の社債を5年満期で発行した場合、単純計算で毎月約83万円の積立が必要になります。こうした返済計画を事前に立てておくことが重要です。
発行コストと手続きの負担
社債発行には、発行方法によって異なるものの、様々なコストや手続きの負担が発生します。
これらを事前に理解し、発行規模との兼ね合いで採算が取れるかを検討することが重要です。
少人数私募債を自社で直接発行する場合の主なコストは以下の通りです。
- 印紙税:発行額の0.1%(5,000万円なら5万円)
- 社債原簿作成費用:数万円程度
- 契約書作成費用:数万円程度
- 社債券発行費用(発行する場合):数万円〜数十万円
一方、銀行引受の私募債の場合は、以下のような費用が発生します。
- 事務手数料:発行額の1〜2%程度(5,000万円なら50〜100万円)
- 引受手数料:発行額の0.5〜1%程度
- 保証料(保証付きの場合):年0.1〜0.5%程度×年数
- 登記費用、印紙税など



「社債発行はコストがかかるから割に合わない」という考えは、必ずしも正しくありません。
確かに銀行引受私募債などは初期コストが高いですが、少人数私募債を縁故者に直接発行する場合は、比較的低コストで発行可能です。
発行方法と規模に応じた費用対効果を検討することが重要です。
社債権者との関係維持の重要性
社債発行では、社債権者(投資家)との関係維持も重要な課題です。
特に縁故者が投資家となる少人数私募債の場合、親族や取引先などとのビジネス関係に加え、債権者・債務者としての関係が加わるため、より慎重な対応が必要になります。
経営状況が悪化した場合や、当初の事業計画通りに進まない場合には、投資家の不安や不満が生じる可能性もあります。
こうした事態を未然に防ぐためには、定期的な情報開示や丁寧なコミュニケーションが欠かせません。
具体的には、以下のような取り組みが有効です。
- 四半期ごとや半期ごとの業績報告会の開催
- 決算書類の提供と分かりやすい解説
- 事業計画の進捗状況の定期的な報告
- 経営環境の変化があった場合の迅速な情報共有
💯 成功事例
製造業G社では、少人数私募債の投資家向けに年2回の「債権者説明会」を開催し、業績報告だけでなく、工場見学や新製品紹介なども行っています。これにより投資家との信頼関係が深まり、満期を迎えた社債の再投資率(ロールオーバー率)が90%以上となっています。
償還条件の変更が困難
銀行借入と社債発行の大きな違いの一つが、条件変更の難易度です。
銀行借入の場合、業績悪化時などには返済条件の変更(リスケジュール)交渉が可能ですが、社債の場合は原則として社債要項で定めた条件を変更することが難しいのです。
社債の償還条件(償還期日、利率など)を変更するには、社債権者集会の特別決議(社債権者の3分の2以上の同意)が必要となり、手続きは非常に複雑です。
特に社債権者が多数の場合、全員の合意を得ることは容易ではありません。
このリスクを踏まえ、社債発行時には無理のない償還計画を立てることが重要です。
また、満期前に条件変更が必要になりそうな場合は、早めに社債権者と個別に相談することも検討すべきでしょう。
社債の償還条件変更が困難という特性は、投資家保護の観点からは重要な要素です。しかし発行企業にとっては大きなリスク要因となります。そのため、「確実に返済できる金額」を見極めた上での発行が不可欠です。楽観的な事業計画に基づいた過大な発行額は危険です。
社債発行の実務:具体的な手順と必要書類
発行前の準備と社内決議
社債発行を検討する際は、まず以下のような準備が必要です。
- 事業計画の策定: 資金使途を明確にし、返済計画を含めた具体的な事業計画を立てる
- 定款の確認: 社債発行に関する規定があるか確認(ない場合は定款変更が必要)
- 資金使途の明確化: どの事業にいくら使うのかを明確にする
- 引受先候補の検討: 誰に引き受けてもらうか、候補者リストを作成する
これらの準備ができたら、取締役会決議を行います。取締役会で決議すべき主な事項は以下の通りです。
- 社債の種類(少人数私募債、銀行引受私募債など)
- 発行総額
- 各社債の金額(券面額)
- 利率
- 償還期限
- 利払日
- 募集方法
- 社債管理者の設置の有無
- 担保の有無
📝 ポイントまとめ
定款に社債発行の規定がない場合は、株主総会での定款変更決議が必要です。多くの中小企業では定款に「会社は、取締役会の決議によって、社債を発行することができる」といった規定を設けています。もし規定がない場合は、事前に顧問弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
社債要項の設計ポイント
社債要項は、社債発行の条件を定めた重要な書類です。
以下のポイントを考慮して設計することが重要です。
発行総額の設定
発行総額は、資金需要と返済能力のバランスを考慮して決定します。
少人数私募債の場合、50口未満という制限も考慮する必要があります。
例えば、年商3億円、営業利益2,000万円の企業であれば、営業利益の1〜2倍程度(2,000万円〜4,000万円)が一つの目安となります。
利率の設定
利率は、市場金利、自社の信用力、償還期間などを考慮して決定します。
一般的には、同等の条件での銀行借入金利よりも0.5〜1.0%程度高めに設定することが多いです。
現在の低金利環境では、年1.0%〜3.0%程度が一般的ですが、発行企業の信用力や投資家層によって異なります。
償還期間の設定
償還期間は、資金使途や返済計画に応じて設定します。
設備投資資金であれば5〜7年、運転資金であれば3〜5年といった具合です。
🎯 実践ステップ
社債要項設計の実践例:
- 発行総額:3,000万円
- 券面額:1口100万円(30口発行)
- 利率:年2.0%
- 償還期間:5年(満期一括償還)
- 利払日:毎年3月31日、9月30日
この場合、年間の利息支払額は60万円(3,000万円×2.0%)、半年ごとに30万円の支払いとなります。5年間の総利息支払額は300万円、5年後に元本3,000万円を一括返済する計画となります。
引受先の選定と勧誘方法
社債の引受先(投資家)の選定は、社債発行成功の鍵を握る重要なステップです。
特に少人数私募債の場合、縁故者への勧誘が中心となります。
引受先候補の例:
- 経営者の親族
- 役員・幹部社員
- 取引先(仕入先、販売先)
- 会社の顧問(税理士、弁護士など)
- 地元の支援者
勧誘に際しては、金融商品取引法上の規制に触れないよう、以下の点に注意する必要があります。
- 勧誘対象者を50名未満に厳格に制限する
- 社債の性質、リスク、償還条件などを明確に説明する
- 投資判断に必要な情報(財務状況、事業計画など)を提供する
- 書面による契約を交わす
社債の勧誘は「金融商品の販売」に該当するため、虚偽の説明や重要事項の不告知などがあった場合、金融商品販売法上の損害賠償責任が生じる可能性があります。投資家保護の観点からも、誠実な情報提供と説明を心がけましょう。
発行後の管理と償還計画
社債発行後は、以下のような管理業務が発生します。
定期的な業務:
- 利息の計算と支払い(年1〜2回が一般的)
- 社債原簿の管理
- 投資家への情報提供(決算報告など)
償還に向けた準備:
- 償還資金の計画的な積立
- 償還前の資金確保(借換えや新規調達の検討)
- 償還手続きの準備
例えば、5年満期の3,000万円の社債を発行した場合、毎月50万円ずつ積み立てれば、理論上は5年で3,000万円の償還資金が確保できます。
実務上は、積立と併せて満期前に新たな資金調達(借換え)の計画も立てておくことが望ましいでしょう。
💡 ワンポイントアドバイス
社債償還のための積立は、通常の預金口座とは別に「社債償還準備金」として管理することをお勧めします。これにより、他の運転資金などと混同せず、確実に償還資金を確保できます。
また、満期の1年前くらいから、償還資金の確保または借換えの準備を始めることが重要です。景気変動や金融情勢の変化に備え、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
成功事例に学ぶ:非上場企業の社債発行
製造業A社の設備投資資金調達事例
企業プロフィール:
- 業種:精密部品製造
- 規模:従業員50名、年商8億円
- 課題:生産ライン増設のための設備投資資金5,000万円が必要
調達方法:
A社は設備投資資金として、銀行融資3,000万円と社債発行2,000万円を組み合わせて調達することにしました。銀行からは「全額の融資は難しい」と言われていたため、社債発行で不足分を補完する戦略です。
社債の発行条件:
- 発行形態:少人数私募債
- 発行総額:2,000万円
- 券面額:1口100万円(20口発行)
- 引受先:社長の親族5名、取引先企業3社、役員2名
- 利率:年2.5%
- 償還期間:7年(満期一括償還)
- 利払日:毎年3月31日
成功のポイント:
- 銀行融資と社債発行を組み合わせたバランスの良い資金調達
- 設備投資の効果(生産性向上、コスト削減)を具体的な数字で示し、投資家を説得
- 投資家向けに四半期ごとの工場見学と報告会を実施し、信頼関係を構築
A社は社債で調達した資金で生産ラインを増設し、生産効率が30%向上。これにより年間の営業利益が約1,500万円増加し、7年後の社債償還も十分に賄える見通しとなりました。
サービス業B社の事業拡大資金調達事例
企業プロフィール:
- 業種:介護サービス
- 規模:従業員30名、年商2億円
- 課題:新規事業(デイサービス施設)開設資金3,000万円が必要
調達方法:
B社は新規事業であるデイサービス施設の開設資金として社債発行を選択しました。銀行には「新規事業は実績がなく融資が難しい」と言われていたためです。
社債の発行条件:
- 発行形態:少人数私募債
- 発行総額:3,000万円
- 券面額:1口50万円(60口発行)
- 引受先:経営者の知人・友人25名、既存の顧客家族8名
- 利率:年3.0%
- 償還期間:5年(満期一括償還)
- 利払日:毎年6月30日、12月31日
成功のポイント:
- 事業計画を詳細に策定し、投資家に具体的な収益見通しを提示
- 社会貢献性の高い事業(介護)であることをアピールし、投資の社会的意義を強調
- 投資家向けに施設見学会や介護セミナーを開催し、事業への理解と共感を促進
B社はデイサービス施設を計画通り開設し、2年目から黒字化に成功。社債投資家の中から利用者やその紹介も増え、事業と資金調達の好循環が生まれています。
社債発行を成功させるための共通ポイント
これらの成功事例から、社債発行を成功させるための共通ポイントとして以下が挙げられます。
1.綿密な事業計画の策定
- 資金使途の明確化
- 具体的な収益見通しと返済計画
- 最悪のケースも想定したリスク対策
2.適切な発行条件の設計
- 自社の返済能力に見合った発行総額
- 投資家にとって魅力的でありながら自社にとっても無理のない利率
- 事業の回収期間に合わせた償還期間
3.投資家との信頼関係構築
- 定期的な情報開示と報告会の実施
- 事業への理解と共感を促す取り組み
- 投資家の声を経営に反映する姿勢



ある地方の老舗和菓子メーカーでは、創業100周年を記念した「記念社債」として、長年の顧客や地域の支援者向けに少人数私募債を発行しました。
この社債は単なる資金調達手段ではなく、「会社と支援者をつなぐ絆」として位置づけられ、投資家には通常の利息に加えて自社製品の贈答や優待制度も設けました。
これにより資金調達だけでなく、顧客ロイヤルティの向上や地域での評判向上にもつながった好例です。
よくある質問(FAQ)
Q: 非上場の中小企業でも社債発行は可能ですか?
A: はい、可能です。特に「少人数私募債」は中小企業でも発行しやすい社債です。社債権者が50名未満、社債総額を最低券面額で除した数が50未満などの条件を満たせば、比較的簡易な手続きで発行できます。ただし、会社法上の要件として、株式会社であることが前提条件となります。
年商数億円程度の中小企業でも、実際に社債発行で資金調達している例は多数あります。私のコンサルティング経験でも、年商2億円程度の企業が3,000万円の社債を発行し、事業拡大に成功した事例があります。
Q: 社債発行と銀行借入、どちらが有利ですか?
A: 一概にどちらが有利とは言えません。社債発行は月々の返済負担がなく、担保・保証人が不要で、返済条件の自由度が高いというメリットがあります。一方、銀行借入は条件変更が可能で、継続的な関係構築による追加融資の可能性があるというメリットがあります。
理想的には、両者を適切に組み合わせることです。例えば、基本的な運転資金は銀行借入で、長期的な設備投資資金は社債で調達するといった使い分けです。
私が支援した企業の多くは、「銀行借入7割、社債2割、その他1割」程度の資金調達バランスを目安にしています。これにより、資金調達手段の多様化とリスク分散を図っています。
Q: 社債発行にかかる費用はどのくらいですか?
A: 発行方法によって大きく異なります。少人数私募債を自社で直接発行する場合は、印紙税や登記費用など最低限の費用で済みますが、銀行引受の私募債の場合は、事務手数料(発行額の1〜2%程度)、引受手数料、保証料などが発生し、コストが高くなります。
具体的には、自社で直接発行する少人数私募債の場合、3,000万円の発行で10〜20万円程度のコストで済むケースが多いです。一方、銀行引受私募債の場合は、同額で100〜200万円程度のコストが発生することもあります。
発行総額との兼ね合いで採算が取れるかを検討する必要がありますが、少人数私募債であれば比較的低コストで発行可能です。
Q: 社債の金利はどのように決めればよいですか?
A: 社債の金利は、市場金利、自社の信用力、償還期間、投資家層などを考慮して決定します。一般的には、同等の条件での銀行借入金利よりもやや高めに設定することが多いです。
現在の市場環境では、以下のような金利設定が目安となります。
- 大企業の公募債:年0.5%〜1.5%程度
- 中堅企業の銀行保証付私募債:年1.0%〜2.0%程度
- 中小企業の少人数私募債:年2.0%〜3.5%程度
ただし、縁故者向けの少人数私募債の場合は、投資家との関係性も考慮して決定することが多いです。投資家にとって魅力的でありながら、自社の返済能力に見合った水準を設定することが重要です。
Q: 社債発行後に業績が悪化した場合、返済条件の変更はできますか?
A: 原則として、社債要項で定めた償還条件(償還期日、利率など)の変更は困難です。銀行借入のように、業績悪化時に返済条件の変更交渉をすることは基本的にできません。
法的には、社債権者集会の特別決議(社債権者の3分の2以上の同意)によって条件変更が可能ですが、手続きは複雑です。
ただし、少人数私募債で縁故者が引受人の場合は、個別に交渉して条件変更に合意してもらえる可能性もあります。しかし、そのような事態にならないよう、無理のない償還計画を立てることが重要です。
Q: 社債発行に必要な社内手続きは何ですか?
A: 社債発行には、取締役会決議が必要です。また、定款に社債発行に関する規定がない場合は、定款変更のための株主総会決議も必要になります。
取締役会では、以下の事項を決議します。
- 社債の種類(少人数私募債、銀行引受私募債など)
- 発行総額
- 各社債の金額(券面額)
- 利率
- 償還期限
- 利払日
- 募集方法
- 社債管理者の設置の有無
- 担保の有無
また、社債原簿の作成・管理も法的に必要な手続きとなります。社債原簿には、社債権者の氏名・住所、各社債の記番号、取得日などを記録します。
Q: 社債発行のための最低限の企業規模や業歴はありますか?
A: 法律上、最低限の企業規模や業歴についての規定はありません。ただし、実質的には投資家から信頼を得られる程度の事業基盤や財務内容が必要です。
銀行保証付私募債の場合は、銀行の審査基準があり、例えば「純資産額1億円以上」「3期連続黒字」「自己資本比率20%以上」などの条件を満たす必要があることが一般的です。
一方、少人数私募債を縁故者中心に発行する場合は、比較的小規模な企業でも可能です。私の経験では、年商数千万円の企業でも、事業計画が明確で投資家との信頼関係があれば、少額(数百万円程度)の社債発行に成功した例があります。
Q: 社債発行後の情報開示義務はありますか?
A: 少人数私募債の場合、法律上の情報開示義務は限定的です。ただし、投資家との信頼関係維持のためには、定期的な業績報告や事業計画の進捗状況の説明など、自主的な情報提供が重要です。
具体的には、以下のような情報提供が望ましいでしょう。
- 決算報告(年次または半期)
- 事業計画の進捗状況
- 重要な経営判断や事業環境の変化
- 社債の償還計画の進捗状況
特に縁故者が投資家の場合でも、投資家保護の観点から適切な情報提供を心がけるべきです。「知り合いだから」という理由で情報提供を怠ると、後々信頼関係が損なわれる原因になりかねません。
まとめ
社債発行は、上場企業だけでなく非上場の中小企業にとっても有効な資金調達手段となり得ます。
特に「少人数私募債」は、銀行融資を補完する「もう一つの選択肢」として価値があります。
社債発行の主なメリットは以下の通りです。
- 担保・保証人が不要で調達できる
- 返済条件の自由度が高い
- 月々の返済負担がなく、キャッシュフロー管理がしやすい
- 企業の信用力向上につながる
- 縁故者からの資金調達が可能
一方で、以下のような注意点もあります。
- 満期一括償還の負担に備えた計画が必要
- 銀行融資より金利が高めになりがち
- 業績悪化時に償還条件の変更が困難
- 投資家との関係維持に継続的な努力が必要
社債発行を成功させるためには、綿密な事業計画の策定、適切な発行条件の設計、投資家との信頼関係構築が重要です。
また、銀行融資との適切な組み合わせを考え、資金調達手段の多様化を図ることが望ましいでしょう。
資金調達の選択肢を増やすことは、企業の成長戦略を支える重要な経営基盤となります。
社債発行という選択肢を持つことで、企業の資金調達の幅が広がり、経営の自由度が高まることを期待します。
🎯 実践ステップ
社債発行を検討する際の第一歩として、以下の3点を確認してみましょう。
- 定款に社債発行の規定があるか確認する
- 具体的な資金需要と使途を明確にする
- 潜在的な投資家(縁故者)のリストアップを行う
これらの準備ができたら、顧問税理士や弁護士に相談し、具体的な発行計画を立てていきましょう。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消