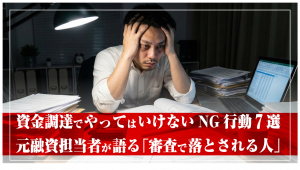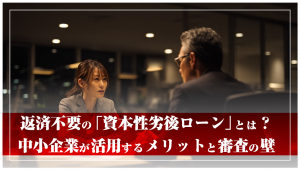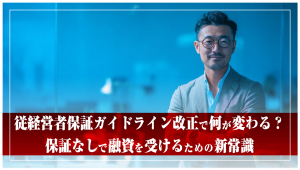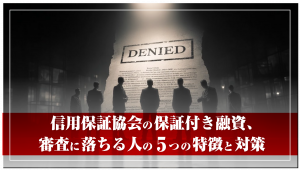──キャッシュは、企業の「血液」です。
資金の流れが滞った瞬間に、いかにビジネスモデルが優れていようとも、組織は機能しなくなります。
これは私が銀行員として10年間、中小企業の資金繰り支援に関わる中で、痛いほど実感してきた事実です。
創業間もない企業やスタートアップにとって、資金調達は成長の推進力である一方で、最初の大きな壁でもあります。
「売上が伸びているのに、資金が足りない」
「投資家にアプローチしたが、実績不足で断られた」
「融資を申し込んだが、書類の作り込みが甘く否決された」
そんな声を、これまで何度となく聞いてきました。
しかし、今回ご紹介するスタートアップ企業は、創業からわずか3年で5,000万円の資金調達に成功しています。
しかもその手段は、いわゆる「VC(ベンチャーキャピタル)からの大型出資」ではありません。
政策金融公庫の融資制度を活用し、補助金の獲得にも成功。さらには、地元信用金庫からの資金支援まで引き出したのです。
 佐藤 真由美
佐藤 真由美この一連の調達プロセスには、今まさに資金繰りに悩む中小企業やスタートアップ経営者の方にとって、大きな学びとヒントが詰まっています。
🔍 本記事で得られること
- どのタイミングで、なぜ資金調達が必要になったのか
- 調達額5,000万円の具体的な内訳
- 各種制度や融資をどう活用したのか
- 実際に提出したキャッシュフロー計画書や調達戦略資料の内容
- 「信頼を勝ち取る資金調達」のための視点・行動
記事を読み進めていただくと、「資金調達はお金集めではなく、信頼の証明プロセスである」という考え方に、きっと納得いただけるはずです。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
資金調達成功の背景と概要
創業から3年間の成長ステップ
あなたが創業3年目のスタートアップの経営者だったとしたら、どんな状況を想像されるでしょうか?
売上は立ち上がり始めたものの、広告費も人材採用も拡大期に入っていて、手元資金は決して潤沢とはいえない。
そんなフェーズにおいて、「資金調達」が事業の未来を大きく左右する鍵になります。
本記事のモデル事例となったのは、2021年に東京都内で創業されたIT系BtoB SaaSスタートアップ。
初年度は開発に集中し、売上はゼロ。
2年目に一部クライアントからの収益が立ち上がり、年間売上は約2,800万円。
3年目を迎えた2024年、導入企業が30社を超え、年間売上が6,200万円に達する見込みとなったタイミングで、資金調達に踏み切りました。
資金使途は、主に以下の3点です。
- 営業・カスタマーサクセス人員の増員(年収換算 約2,400万円)
- プロダクト改良のための開発投資(1,200万円)
- 認知拡大のための広告出稿費(1,000万円)
このように、事業の拡大フェーズで必要になるのは、「売上に直結する投資」です。
資金がなければ人も雇えず、施策のスピード感も失われてしまいます。
だからこそ、「今が勝負」と、調達を決断したわけです。
5,000万円の資金調達の内訳
調達にあたり、モデル企業が選んだ手段は、単一のVC出資ではありません。
むしろ、リスク分散と信用構築を両立する“複合調達戦略”を採用していました。
以下がその内訳です。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 資金調達内訳(合計:5,000万円) ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓
┃ 政策金融公庫 創業融資制度 ┃ 2,000万円 ┃
┃ 地方信用金庫 融資 ┃ 1,500万円 ┃
┃ 中小企業省力化投資補助金 ┃ 800万円 ┃
┃ 自己資金 ┃ 700万円 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┛特に注目すべきは、公的資金を最大限活用している点です。
政策金融公庫からは、無担保・無保証人で2,000万円の借入に成功。
さらに、自治体補助金では省人化・DX化のための投資に対し800万円の補助を得ています。
また、自己資金をきちんと組み入れている点も、金融機関からの信頼を得るためには重要なポイントでした。
「この人は、自分のお金もリスクに晒している」
というメッセージが、説得力を高める要因になったのです。
成功を導いた資金調達手法の全体像
スタートアップにとって、資金調達は「運任せ」のものではありません。
重要なのは、「信用の積み上げ」と「制度の正しい活用」です。
ここからは、モデル企業が実際に活用した主な資金調達手法を、3つの柱に分けてご紹介します。
融資:政策金融公庫の創業融資制度をどう活用したか
モデル企業がまず着手したのは、日本政策金融公庫の「新規開業資金」でした。
この制度は、創業から7年以内の企業を対象とした融資制度で、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)までの借入が可能です。
彼らが実行したポイントは、次の通りです。
【1】創業計画書の徹底的な作り込み
- フォーマットは公庫公式サイトの記入例を活用
→ 無駄なアピールは避け、シンプルに「数値で語る」構成に。 - 売上予測の根拠として、導入見込み企業リストを添付
→ 顧客ヒアリングの内容をExcelで一覧にまとめ、信頼性を補強。
【2】面談対策としての“想定問答集”づくり
- 審査で問われやすい質問項目(資金使途、返済原資、失敗時対応)を15項目抽出し、経営陣全員で模擬面談を実施
- 言葉のズレが信用を失うため、提出資料と一言一句合わせるトレーニングを重ねた
【3】自己資金比率の明示
- 調達総額の約14%(700万円)を「代表者自己資金」として明記し、リスク共有の姿勢を提示
これらの準備の結果、公庫からは2,000万円の無担保融資が実行されました。
据置期間2年・返済期間7年という、スタートアップには理想的な条件での調達です。


補助金:使えた補助金と、通過する申請書の書き方
続いてモデル企業が着手したのが、中小企業省力化投資補助金の申請でした。
この制度は、2025年現在で非常に注目されている補助金の一つです。
【対象と補助率】
- 自動化設備や省人化ツールの導入が対象
- 補助率は 2/3、上限1,500万円
【申請成功のポイント】
- 計画書は「設備導入による利益増加」のストーリーで構成
→ ただの設備購入計画ではなく、「導入後の売上推移」と「人件費削減インパクト」を具体数値で示す - ROI(費用対効果)シートを別添資料として作成
→ たとえば、「50万円の設備で年80万円の業務削減効果 → ROI160%」という定量的説明が決め手に
申請書は、行政書士やコンサルタントに“丸投げ”するのではなく、内部で書いた草案に専門家の添削を受けるというスタイルで仕上げました。
このバランス感が、「事業主自身の理解」と「制度適用の整合性」を両立させた要因といえます。
結果、補助金として800万円が交付決定。
申請から交付決定までは約2か月、交付実行まではさらに2か月の時間がかかりましたが、確実に資金計画に組み込める結果となりました。
次章では、「地元金融機関との信頼構築」によって追加の1,500万円をどう獲得したかをご紹介します。
補助金や公的融資とはまた異なる、「人間関係」が資金を動かす実例です。
民間からの資金:地元金融機関との関係構築
資金調達というと、「書類勝負」「数値勝負」の印象が強いかもしれません。
しかし、民間金融機関との関係構築において最も重視されるのは“人と人の信頼関係”です。
モデル企業が追加で調達した1,500万円の融資は、まさにこの“信用の積み上げ”が実を結んだ結果でした。
【選んだ金融機関:地域密着型の信用金庫】
都内に拠点を構える西武信用金庫の「TOKYO Startup Nexus」は、創業間もない企業に対して、事業性を重視した融資支援を行っています。
モデル企業は、創業1年目からこの信金に口座を開設し、毎月、次のような情報共有を欠かさず続けていました。
- 売上・KPIレポート(2ページ以内に簡潔に)
- トピック(新規受注、展示会出展、採用実績など)
- 今後3か月の資金繰り予定表
これをメール1通+オンライン面談(月1回)というペースで1年半以上継続。
それにより、「この企業は小さいながらも誠実だ」「数字と現場がつながっている」という印象を担当者に与えることができました。
【融資実行のきっかけ】
3年目に入り、政策金融公庫からの2,000万円の実行が決まった直後。
同社は信金に対して以下のように“情報提供と提案”の形で資金需要を提示しました。
「今回、広告費と人員増のために残り1,500万円を調達したく、公庫とは別建てでご相談したいと思っています。
実行スケジュール、利率、保証料など、率直にご相談できませんか?」



このように、「お願い」ではなく、「計画に基づいた提案」という姿勢が、結果的に融資決定を早めることになりました。
審査もスムーズに進み、提出書類も公庫向けに作成したキャッシュフロー表を基礎に再構成するのみで対応。
最終的に、金利1.5%、返済期間5年という条件での融資実行に至りました。
信金担当者のひとこと(実際のやりとりより)
「この企業さんは、売上が伸びていく過程を“数字と行動”で見せてくれていたので、私自身、上司を説得しやすかったんです。
書類よりも、毎月の積み重ねが決め手でした。」
融資担当者にここまで言わせる関係性は、1日や1週間では築けません。
調達成功の陰には、“情報共有と継続的な信頼形成”という地味な努力の積み重ねがあることを、改めて認識しておく必要があります。
実務で使った資料・準備したこと
資金調達は、単なる“お願い”ではありません。
むしろ、「計画を信じてもらう」ための資料づくり=説得の準備プロセスだと私は考えています。
モデル企業が実際に活用した資料は、以下の2点が柱となっていました。
キャッシュフロー計画書の作成方法
【なぜキャッシュフロー表が必要なのか】
資金調達を希望する際、金融機関や補助金審査員が最も注目するのが、「資金繰りの見通し」です。
売上は伸びているか?
利益は出ているか?
そして、何より“返済可能性が見えるか”。
この点を可視化するため、モデル企業は3年間の月次キャッシュフロー計画書をExcelで作成しました。


【構成のポイント】
- 収入欄
- 顧客別売上の計画(3カテゴリに分解)
- 補助金入金予定時期
- 支出欄
- 人件費(採用スケジュールと連動)
- 外注費・広告費・借入返済額
- キャッシュ残高推移
- 各月末残高を折れ線グラフで表示
- 月末キャッシュがマイナスにならないよう計画を調整
【見せ方の工夫】
- 視覚的に伝わるグラフ併用
→ キャッシュ残高・売上・利益の推移を別々のグラフに - 「楽観」「現実」「悲観」3パターンを提示
→ 調達後の売上成長が予想より下振れした場合の影響を見せ、リスク耐性をアピール
このExcel表は、政策金融公庫と信用金庫、どちらの融資審査にも活用されました。
特に信金の担当者からは、「ここまで作り込まれていると、社内稟議が通しやすい」という声も得られたそうです。
調達戦略シートの中身公開
「なぜ今、いくら必要なのか」を伝えるために用意されたのが、「資金調達戦略シート」です。
A4で1〜2枚にまとめ、関係者への説明資料として使用されました。
【構成要素】
1. 資金調達の目的と背景
- 3年目の成長加速期における施策一覧
- 人材採用/広告投資/開発強化の内訳
2. 資金使途の明確化
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 資金使途別:必要金額 ┃
┣━━━━━━━━━┳━━━━┫
┃ 採用人件費 ┃ 2,400万円 ┃
┃ 広告宣伝費 ┃ 1,000万円 ┃
┃ 開発投資費 ┃ 1,200万円 ┃
┃ 合計 ┃ 4,600万円 ┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━┛3. 期待される効果(ROI)
- 例えば、広告100万円投下 → 平均CV数120件、LTVベースで3.2倍の回収が見込める試算
- 各施策ごとに「投資→効果→売上貢献」の数式を明示
4. スケジュールと資金回収見込み
- 採用から収益化までのタイムラグを記載
- キャッシュアウト→キャッシュインの時間軸を月単位で図解
これらの資料を通じて、資金提供者が求める以下の3点がクリアに伝わるようになりました。
- この資金は「なんとなく必要」ではない
- 投資先が明確で、回収可能性がある
- 経営者が数字に強く、言葉と計画が一致している
次章では、このような調達の成功を裏付けた「マインドセット」と「行動姿勢」について、より深く掘り下げていきます。
資金提供者が「出したくなる人」とはどういう存在なのかを、私の銀行経験も踏まえてご紹介します。
調達を成功させるためのマインドと行動
資金調達の成否は、制度や書類だけで決まるものではありません。
実際、私が金融機関の審査担当として現場にいた頃、「制度的にはOKでも、この人には出したくない」と感じたケースもあれば、「まだ実績は浅いけれど、この人なら貸せる」と感じた企業もありました。
その違いを分けるのは、やはり「経営者のマインド」と「行動」です。
「借りる視点」から「信用を創る視点」へ
モデル企業の経営者は、終始一貫してこう語っていました。
「融資は“お金を借りる”ことではなく、信用を証明していくプロセスだと考えています」
これは、まさに私が伝え続けてきた信念と同じです。
【信頼される経営者の3つの特徴】
1. 数字に強く、自分の言葉で説明できる
- Excelで作った計画書の中身を、きちんと口頭で語れる
- 数字の根拠を問われたときに、「税理士が作ったので…」では通用しない
2. 「透明性」を武器にする
- 売上が伸びていない月も隠さず報告
- 成功だけでなく、失敗の分析まで率直に共有
3. 「一緒に成長したい」という態度を示す
- 金融機関を“資金提供者”としてだけでなく、“伴走者”として巻き込む姿勢



実際にモデル企業は、補助金採択後も進捗レポートを自主的に提出し、信金の担当者と月次ミーティングを継続しています。
このような一貫した行動の積み重ねが、「融資枠の追加」や「紹介先の拡大」にもつながっていくのです。
専門家のサポートを得る重要性
さらに見逃せないのが、外部専門家との連携です。
モデル企業が最も助けられたと語るのは、以下の2つの専門職の存在でした。
【1】税理士との連携
- 財務データの正確性確保
- 節税と資金繰りを両立する計画作成支援
- 銀行用資料と税務申告書類の整合性を担保
特に重要だったのは、「税理士が数字を作り、経営者が理解して語れる」状態を維持すること。
アウトソースではなく“共創”のスタンスが、金融機関にも伝わったのです。
【2】中小企業診断士による補助金書類のブラッシュアップ
- 補助金特有の「審査員目線」を踏まえた文書表現のアドバイス
- 採択事例に沿った「言い回し」や「ストーリーテンプレート」の提供
ここでも丸投げはせず、あくまで「原稿作成:経営者/添削:診断士」という形で、経営者の想いと制度の言語を橋渡しする関係が構築されていました。
資金調達の成功は、個人戦ではなくチーム戦です。
そしてその中心に立つのが、“自分のビジネスを自分の言葉で語れる経営者”であること。
それを実現するには、「学ぶこと」「頼ること」「継続すること」の3つが不可欠です。
よくある質問(FAQ)
資金調達に関して、セミナーや個別相談でも特に多く寄せられる質問をピックアップし、実務経験と制度のリアルを踏まえて回答いたします。
「自分にも当てはまりそう」と感じたら、ぜひそのまま実行のヒントにしてみてください。
Q:創業3年未満でも高額な融資を受けられるのですか?
A:可能です。特に政策金融公庫では「実績」よりも「将来性」が重視されます。
政策金融公庫は、創業支援を目的とした公的機関です。
創業3年未満であっても、事業計画に合理性があり、資金使途・収益見通し・返済プランが明確であれば、1,000万円〜2,000万円規模の融資は珍しくありません。
特に以下の要素がポイントとなります。
- 自己資金比率:自己資金が1〜3割程度あると信頼度が増します
- 売上見込の根拠:契約書や発注書などの「証拠資料」が強力な武器になります
- 代表者の経歴:同業種での経験や実績があると、説得力が増します
実際に、モデル企業は創業3年以内で2,000万円の無担保融資を得ています。
Q:補助金と融資、どちらを先に検討すべき?
A:並行して進めるのが理想ですが、スピード感重視なら融資から始めましょう。
補助金は、「申請 → 採択 → 実行 → 後払い」が基本構造です。
一方で融資は、「審査 → 実行」でスムーズに着金しやすいため、キャッシュフローに余裕がない場合は融資を先行させるべきです。
補助金を使いたい場合でも、次のような進め方が現実的です。
- STEP1:融資を申請して必要資金を確保
- STEP2:補助金申請と同時に、対象となる支出を明確に分けておく
- STEP3:採択後は、補助金で「後払い回収」する前提で資金繰りを構築
Q:創業初期に信頼を得るには何が必要?
A:「継続的な可視化」と「誠実な報告」が最大の信頼構築手段です。
たとえば、以下のような取り組みは強い信頼形成に繋がります。
- 毎月1回、金融機関に売上・KPIの進捗レポートを共有
- 数値だけでなく、「今後3か月の取り組み」も添える
- 良い報告だけでなく、ネガティブな情報も隠さず共有
この「透明性の積み重ね」が、「この会社は信頼できる」という判断につながります。
Q:自分で申請書を書くのが不安です。外注すべき?
A:完全な丸投げは避けてください。ベストは「自分で書いて、専門家に添削してもらう」スタイルです。
金融機関や補助金の審査員は、書類だけでなく「経営者の理解度」も見ています。
申請書の内容を面談で説明できなければ、「本当に理解していないのでは?」と疑われる可能性があります。
おすすめは以下の流れです。
- ドラフトは自分の言葉で書く
- 専門家(税理士や診断士)にチェック・添削を依頼
- 添削後の内容を、再度“自分の言葉”で話せるよう練習
Q:5,000万円は何に使ったのか?
A:全額を「売上に直結する投資」に振り切っています。
モデル企業では、以下の使途で資金を配分しました。
- 営業・CS(カスタマーサクセス)人件費:2,400万円
- プロダクト開発強化:1,200万円
- 広告出稿・展示会出展など:1,000万円
- 予備運転資金(キャッシュバッファ):400万円
このように、調達額の9割以上が「将来の売上に直接つながる施策」に投資されていることが、金融機関や審査官にとって最も安心できるポイントとなりました。
まとめ
資金調達は、単なる「お金集め」ではありません。
むしろそれは、事業の信頼性や成長可能性を可視化し、第三者に“投資する理由”を提示するプロセスです。
創業3年目にして5,000万円を調達した今回の事例は、「華やかなプレゼン」や「知名度のある投資家」に頼ったものではありません。
一歩一歩、丁寧に信用を積み上げたこと。
制度の本質を理解し、自分たちの言葉で説明し切ったこと。
そして、「応援したくなる企業」として誠実な行動を継続してきたこと。
そのすべてが、調達成功という結果を生みました。
✅ 今日からできるアクションリスト
- キャッシュフロー計画書を月単位で可視化してみる
- 地元金融機関との“月1回の情報共有”を始める
- 補助金制度の公募スケジュールを確認する(中小企業庁の公式サイト等)
- 自分の事業計画を“他人に伝える言葉”で話せるか練習してみる
- 税理士や診断士と“添削型の連携”をスタートする
「まだ創業3年目だから」ではなく、
「創業3年目だからこそ、次の一手が重要だ」
そんな視点で、この記事をきっかけに資金調達への一歩を踏み出していただけたら、これ以上の喜びはありません。
資金繰りの課題は、企業の血流の問題。
滞ればすべてが止まりますが、流れれば、次のチャレンジに向かう余力が生まれます。
あなたのビジネスが、次のステージへと進むことを、心から応援しています。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消