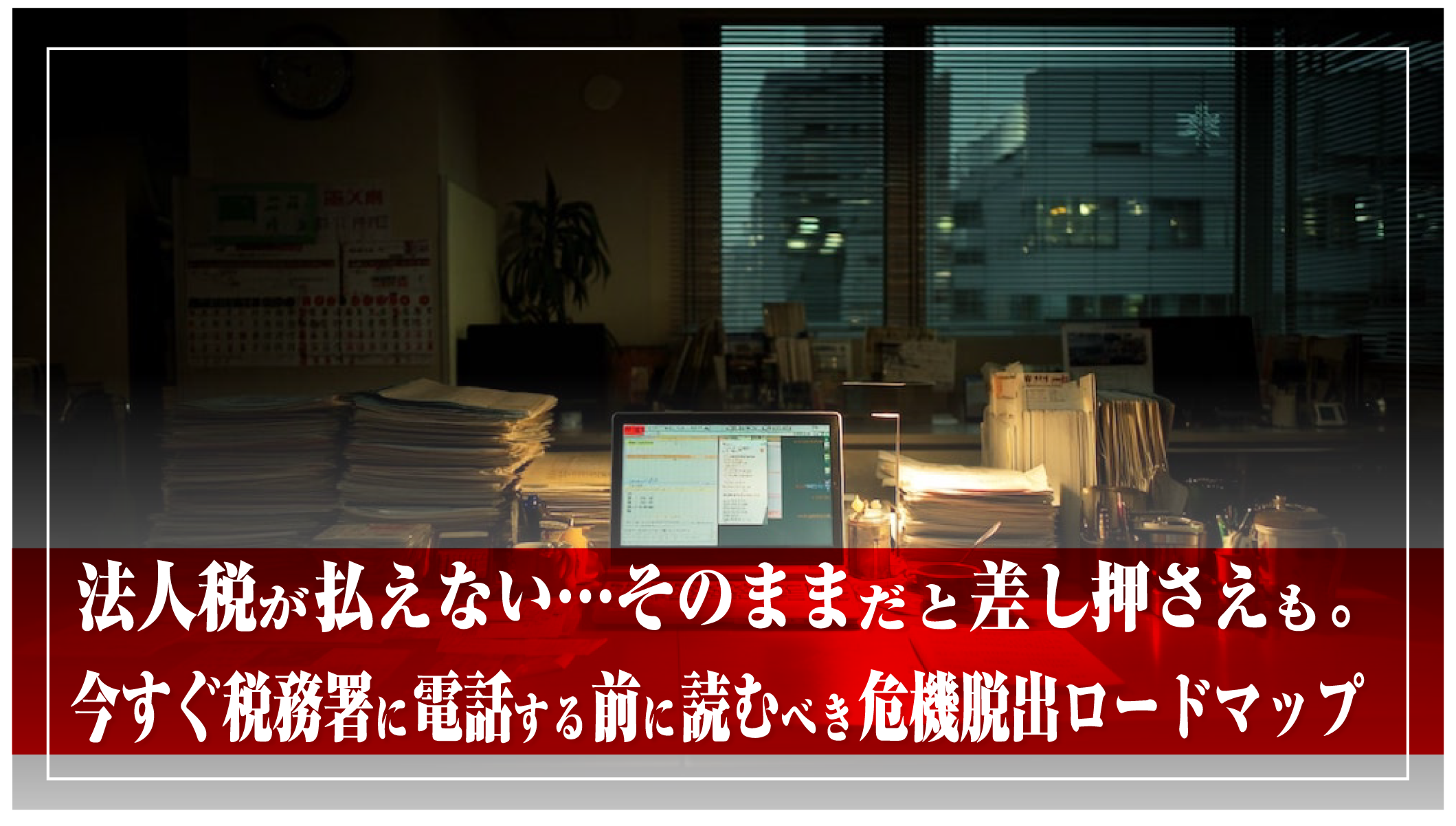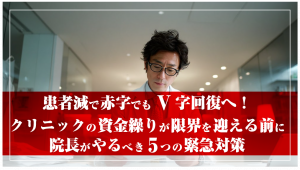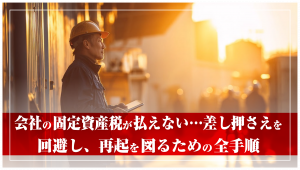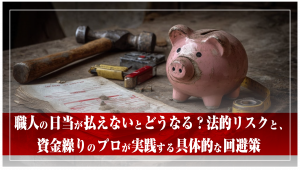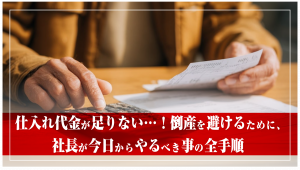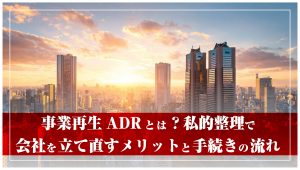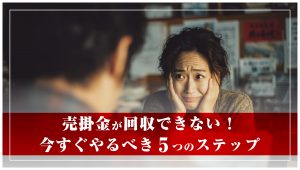「今月の法人税、どうしても払えそうにない…」
もしあなたが今、通帳の残高を前に絶望的なため息をついているなら、この記事はあなたのためのものです。
税金の滞納は、延滞税や差し押さえのリスクだけでなく、大切に築き上げてきた社会的信用を一瞬で失いかねない、まさに経営の危機。その恐怖と焦りは痛いほどわかります。
しかし、慌てて税務署に電話をするのはお待ちください。
 佐藤 真由美
佐藤 真由美はじめまして。元銀行員で、数々の中小企業の資金繰りを見てきた佐藤真由美と申します。その経験から断言します。正しい知識と準備さえあれば、差し押さえは100%回避できます。
この記事は、単なる制度解説ではありません。あなたが今夜から安心して眠れるようになり、再び事業の成長に集中できる未来を取り戻すための、具体的で血の通った「危機脱出ロードマップ」です。
【この記事の結論】法人税が払えない時に、まずやるべき3つのこと
- 放置は絶対NG!すぐに税務署へ相談の準備を
法人税の滞納は、「延滞税」や財産の「差し押さえ」に直結します。手遅れになる前に、資金繰り表などを用意し、税務署へ分割納付の相談をする準備を始めましょう。 - 公的な救済制度「換価の猶予」を検討する
事業の継続が困難な場合、1年以内の分割納付が認められる「換価の猶予」という制度があります。申請には「納期限から6ヶ月以内」という期限があるため、早めの行動が重要です。 - 緊急の資金調達法を確保しておく
納税資金がどうしても足りない場合、売掛金を即日現金化できる「ファクタリング」や、経営セーフティ共済の「一時貸付金制度」などが選択肢になります。
本文では、税務署への相談方法から資金調達の具体的な手順まで、この危機を乗り越えるためのロードマップを詳しく解説します。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
【ステップ1】まずは冷静に。法人税が払えない場合に起こる「不都合な真実」
延滞税の発生と計算方法
納税は、国民の義務です。
そのため、納付期限を1日でも過ぎれば、その瞬間から「延滞税」というペナルティが発生します。
これはまるで、静かに出血し続ける傷口のようなもの。
気づかないうちに、あなたの会社の「血液」であるキャッシュが、着実に失われていくのです。
具体的には、2段階の利率が適用されます。(※2025年の見込み税率)
- 納期限の翌日から2ヶ月間:年2.4%
- それ以降:年8.7%
例えば、納税額が100万円で、滞納が1年間続いたとしましょう。
最初の2ヶ月で約4,000円、その後の10ヶ月で約72,500円、合計で約76,500円もの延滞税がかかります。
これは、本来払う必要のなかったコストです。
時間が経てば経つほど、この出血はひどくなります。
督促状の送付から差し押さえまでの流れ
「そのうち払えばいい」という考えは、絶対に持たないでください。
税務署の対応は、あなたが思うよりずっと迅速かつシステマチックです。
納期限から50日以内に、まず書面で「督促状」が届きます。この紙の冷たい質感は、現実の厳しさを突きつけてくるでしょう。
督促状を無視していると、税務署から電話がかかってきたり、担当者が直接会社に訪問してきたりします。鳴り響く電話の音に、心臓が跳ねる日々が始まります。
それでも納税されない場合、税務署はあなたの会社の資産を徹底的に調査します。預金残高、売掛金、不動産、自動車…すべてが対象です。これは、差し押さえの「準備」に他なりません。
法律上、督促状を発行してから10日を経過すれば、いつでも差し押さえが可能になります。ある日突然、銀行口座が凍結され、取引先への売掛金が差し押さえられる。事業の継続が、事実上不可能になる瞬間です。
【元銀行員が解説】最も恐ろしいのは「社会的信用の失墜」
差し押さえという直接的なダメージ以上に、経営者として本当に恐れるべきもの。
それは「社会的信用の失墜」です。
銀行の融資審査室の、あの冷たい空気感を私は今でも覚えています。
社長が熱意を込めて語る事業計画書、何枚にもわたる試算表。
しかし、最後に提出された「納税証明書」に「未納」の二文字があった瞬間、その場の空気が凍りつくのです。
なぜなら、銀行にとって税金の滞納は、単なる資金繰りの悪化以上の意味を持つからです。
- 「経営管理能力が欠如している」という烙印
- 「差し押さえリスクがあり、融資を回収できないかもしれない」という懸念
どんなに素晴らしい事業計画も、この一枚の紙の前では色褪せてしまいます。
新規融資はもちろん、既存の融資の借り換え(リファイナンス)すら絶望的になる。
それは、会社の未来へ続くはずだった扉が、目の前で固く閉ざされることを意味します。
【ステップ2】税務署に電話する前に!今すぐあなたが準備すべき3つのこと
1. なぜ払えないのか?資金繰り状況の正確な把握
税務署の担当者が知りたいのは、あなたの涙ではなく「数字」です。
なぜ払えないのか、そして、いつなら払えるのか。
それを説明するための、客観的な証拠を用意しましょう。
- 試算表:最新の経営成績と財務状況を示します。
- 資金繰り表:会社の血液であるキャッシュが、いつ、いくら入り、いつ、いくら出ていくのか。これこそが「会社の心電図」です。
これらを作成し、「売上が急減した」「大きな支払いと重なった」といった窮状を、具体的な数字で語れるようにしてください。
そして何より重要なのが、「いつまでに」「いくらなら分割で払えるのか」という現実的な納税計画の根拠を示すことです。
2. 「納税に対する誠実な意思」を示すための資料準備
税務署との交渉で、最も重要な武器は「誠実さ」です。
「払う意思はある。しかし、今はどうしても払えない。だから、事業を立て直すまで待ってほしい」
このメッセージを、資料を通じて伝えるのです。
- 今後の売上見込み:希望的観測ではなく、受注状況などに基づいた現実的な数字を。
- 経費削減計画:役員報酬のカット、不要な経費の見直しなど、身を切る努力を示します。
- 経営改善計画書:今回の事態をどう乗り越え、今後どのように納税していくかの具体的な道筋を示します。
これらは、単なる書類ではありません。
あなたの経営者としての覚悟を示す「未来への約束手形」なのです。
3. どの制度が使える?「納税の猶予」と「換価の猶予」の事前知識
国も、事業者を追い詰めることだけが目的ではありません。
再起の意思がある事業者には、公的な救済制度が用意されています。
交渉の前に、自分がどの扉を開けられる可能性があるのか、地図を読んでおきましょう。
- 納税の猶予:災害や病気、事業の休廃業など、特別な事情がある場合に適用される可能性があります。
- 換価の猶予:国税を一時に納付すると事業継続が困難になる場合に、申請できる可能性があります。多くの経営者が対象となるのはこちらです。
これらの制度を事前に知っておくだけで、交渉の主導権を握りやすくなります。
【ステップ3】公的な救済制度を使いこなす!「納税の猶予」と「換価の猶予」徹底活用術
準備が整ったら、いよいよ具体的な解決策である「猶予制度」の活用を検討します。
これは、国が認めた公式な「時間稼ぎ」の手段。
この時間を使って、私たちは事業の立て直しを図るのです。
2つの猶予制度、あなたの場合はどっち?違いを比較解説
どちらの制度があなたの会社の処方箋となるのか。
下の表で、自社の状況と照らし合わせてみてください。
| 項目 | 納税の猶予 | 換価の猶予 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 災害、病気、事業の休廃業などで納税が困難な方 | 国税を一時に納付すると事業継続が困難になる方 |
| 申請期限 | 事情が発生してから概ね2ヶ月以内など | 納期限から6ヶ月以内 |
| 主な効果 | ・1年以内の納税猶予 ・期間中の延滞税が軽減または免除 ・差し押さえの猶予 | ・1年以内の納税猶予 ・期間中の延滞税が一部免除 ・差し押さえの猶予 |
| 担保の要否 | 猶予額や期間により必要 | 原則として必要(100万円以下などは不要な場合も) |
【佐藤のコンサル事例】
- A社(飲食店)のケース:急な売上減少で資金繰りが悪化。「このままでは納税できない」と判断し、納期限から2ヶ月後に相談。「換価の猶予」を申請し、1年間の分割納付が認められました。
- B社(製造業)のケース:社長が病気で長期入院。事業が一時ストップし、納税が困難に。こちらは「納税の猶予」の対象となり、延滞税の大部分が免除されました。
【記載例あり】申請書作成のポイントと必要書類
申請には、主に以下の書類が必要です。
- 猶予申請書
- 財産収支状況書(資産、負債、収支の状況を記載)
- 担保提供に関する書類(必要な場合)
- 災害などの事実を証する書類(納税の猶予の場合)



最も重要なのは、「猶予が認められなければ、事業の継続が困難になる」ことを、具体的な言葉で訴えることです。
例えば、「財産収支状況書」の「今後の収支の見込み」欄には、ただ数字を書くだけでなく、
「納税により運転資金〇〇円がショートし、仕入れが不可能となり事業継続が困難」
といったように、この一文があなたの未来を左右するという気概で、窮状を具体的に書き記してください。
猶予が認められた後の注意点と分割納付計画
忘れてはならないのは、猶予は「免除」ではないということです。
これはあくまで一時的な止血帯に過ぎません。
猶予が認められたら、承認された分割納付計画に基づき、1円たりとも遅れることなく納税を履行しなければなりません。
もし計画通りに納付できなければ、猶予が取り消され、即座に差し押さえに移行する可能性もあります。
この猶予期間こそ、後述する根本的な資金繰り改善に取り組むための、最後のチャンスなのです。
【ステップ4】それでも資金が足りない…元銀行員が教える緊急資金調達法
緊急時の選択肢①:ファクタリング
これは、あなたの会社が持つ「売掛債権(未回収の請求書)」を、ファクタリング会社に買い取ってもらうことで、早期に現金化する方法です。
- メリット:自社の信用力ではなく、売掛先の信用力が重視されるため、税金滞納中でも利用しやすい。最短即日で現金化できる場合もある。
- デメリット:手数料が高い(売掛金の数%〜20%程度)。悪質な業者も存在するため、業者選びは慎重に行う必要があります。
これは、未来の利益を前借りしているのと同じです。
あくまで一時的な橋渡し(ブリッジファイナンス)として考えましょう。
緊急時の選択肢②:ノンバンクのビジネスローン
銀行以外の金融機関(消費者金融や信販会社など)が提供する事業資金融資です。
- メリット:銀行に比べて審査がスピーディーで、基準も柔軟な傾向がある。
- デメリット:金利が非常に高い。安易に借り入れると、返済が新たな資金繰り悪化の原因となり、負のスパイラルに陥る危険があります。
利用するとしても、納税に必要な最低限の金額を、ごく短期で返済する計画が立てられる場合に限定すべきです。
【経営者必見】経営セーフティ共済(倒産防止共済)は使えるか?
もし、あなたが経営セーフティ共済に加入しているなら、希望の光が見えるかもしれません。
この共済には、取引先が倒産していなくても、解約手当金の95%を上限に、無担保・無保証人で借入れができる「一時貸付金制度」があります。
あなたがコツコツと未来のために積み立ててきた「お守り」が、今この瞬間、会社を救う「最強の武器」になるかもしれないのです。
今すぐ、加入状況を確認してみてください。
【ステップ5】二度と繰り返さないために。根本的な資金繰り改善ロードマップ
ここまで、緊急的な止血の方法についてお話してきました。
しかし、最も重要なのは、二度とこのような事態を繰り返さないことです。
この危機を、あなたの会社の財務体質を根本から見直す「手術」の機会と捉えましょう。
なぜ資金繰りが悪化したのか?根本原因を分析する
なぜ、あなたの会社の血液は足りなくなったのでしょうか?
傷口はどこにあるのか、冷静に分析する必要があります。
- 売上の問題?:売上そのものが減少しているのか?
- 回収の問題?:売掛金の回収が遅れていないか?(回収サイトが長すぎないか)
- 支払の問題?:買掛金の支払いが早すぎないか?(支払サイトが短すぎないか)
- 在庫の問題?:売れない在庫(キャッシュを生まない資産)を抱えすぎていないか?
- 経費の問題?:固定費が高すぎないか?不要な支出はないか?
この原因分析なくして、真の再建はありえません。
「キャッシュは企業の血液」キャッシュフロー経営への転換
私が銀行員時代から一貫して言い続けている持論があります。
それは、「キャッシュは企業の血液」だということです。
損益計算書(PL)上の利益は、あくまで「健康診断の結果」です。
黒字でも、血液であるキャッシュが回らなくなれば、会社は倒産します(黒字倒産)。
本当に見るべきは、キャッシュフロー計算書(CF)、あるいは日々の資金繰り表という「心電図」なのです。
常に会社の血流を意識し、現金の出入りを最優先に考える「キャッシュフロー経営」へ。
今こそ、経営の舵を大きく切る時です。
明日からできる資金繰り改善アクションプラン
難しい理論は必要ありません。
明日から、いえ、今日から始められる具体的な行動リストです。
- 【回収を早める】
- 請求書は商品納品後、即日発行する。
- 入金が遅れている取引先には、すぐに連絡する。
- 回収サイトの短い取引を増やす交渉をする。
- 【支払いを遅らせる】
- 仕入れ先と交渉し、支払サイトを1日でも長くしてもらう。
- クレジットカードや手形を有効活用する。
- 【在庫を減らす】
- 不要な在庫は、セールなどを行ってでも現金化する。
- 適正在庫の基準を設け、過剰な仕入れをしない。
- 【経費を削る】
- 聖域なく、すべての固定費(家賃、人件費、リース料など)を見直す。
- まずは社長であるあなたの役員報酬から見直す姿勢を示す。
一つひとつは小さなことかもしれません。
しかし、この地道な努力の積み重ねが、会社の血管を強くしなやかにしていくのです。
よくある質問(FAQ)
Q: 税務署への相談は、税理士に代理してもらうべきですか?
A: 必須ではありませんが、税務署との交渉に不安がある場合や、ご自身の状況を客観的に説明するのが難しい場合は、税理士に同席または代理を依頼することをおすすめします。専門家がいることで、よりスムーズかつ有利に交渉を進められる可能性があります。まずは現状を正直に話せる信頼できる税理士に相談してみましょう。
Q: 「納税の猶予」が認められないのはどんなケースですか?
A: 例えば、納税に対する誠実な意思が見られない(連絡を無視し続けるなど)、申請書類に虚偽がある、明らかに納税できる資産があるにもかかわらず隠している、といったケースでは認められにくいです。また、申請期限を過ぎてしまっている場合も原則として認められません。
Q: 消費税や源泉所得税も払えないのですが、法人税と同じように考えて良いですか?
A: いいえ、危険度が全く異なります。消費税や源泉所得税は、顧客や従業員から「預かっているお金」です。これを滞納することは、自社の利益から払う法人税の滞納よりも悪質と見なされ、差し押さえに至るスピードが早い傾向があります。 複数の税金を滞納している場合は、消費税と源泉所得税を最優先で納付するようにしてください。
参考: 消費税が払えない中小企業必見!滞納前にやるべき5つの緊急対策
Q: 差し押さえの対象になる資産には何がありますか?
A: 預貯金、売掛金、自動車、不動産、有価証券など、会社名義の換金可能なあらゆる資産が対象となります。 特に預貯金や売掛金は差し押さえられやすく、実行されると事業の継続が極めて困難になります。
Q: 税務署に相談に行くのが怖いのですが、どうすれば良いですか?
A: そのお気持ちは、痛いほどよく分かります。しかし、税務署は滞納者を追い詰めることだけが目的ではありません。彼らの最終目的は「税金を徴収すること」であり、会社が倒産してしまっては元も子もないのです。
誠実な態度で「払う意思はあるが、現状では難しい」ということを具体的な数字で示せば、分割納付などの相談に真摯に応じてくれるケースがほとんどです。一人で抱え込まず、勇気を出して相談することが解決への第一歩です。
まとめ
法人税が払えないという事態は、経営者にとって、まさに悪夢のような状況です。
眠れない夜が続き、一人ですべてを背負い込んでいるかもしれません。
しかし、本日お伝えしたロードマップの通り、パニックにならず、一つひとつ冷静に対処すれば、必ずこの危機は乗り越えられます。
重要なのは、次の3つのステップです。
- 現状を正確に把握し、準備を整えること。
- 誠実な意思を持って、税務署に相談すること。
- 二度と繰り返さないための資金繰り改善を、断行すること。
元銀行員として、そして経営アドバイザーとして断言します。
キャッシュフローを制するものが、経営を制します。
この危機を、単なる「終わり」と捉えないでください。
これは、あなたの会社の財務体質を根本から見直し、より強く、しなやかな企業へと生まれ変わるための「始まり」なのです。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消