「今月末の支払いに、現金が足りない…」
「取引先からの入金は2ヶ月も先。銀行融資も間に合わない…」
「このままでは、社員の給料が払えないかもしれない…」
はじめまして。
元金融コンサルタントの山田 麻里です。
かつてコンサルタントとして、多くの素晴らしい経営者の方々が、このような資金繰りの崖っぷちに立たされている現実を目の当たりにしてきました。
 山田 麻里
山田 麻里情熱も、技術も、そしてお客様からの信頼もある。
それなのに、ほんの少しの資金のズレが、事業の存続を脅かしてしまう。
その悔しさ、そして焦り。痛いほどよく分かります。
そんな時の救世主となり得るのが「ファクタリング」です。
しかし、その契約書には、専門用語や見慣れない条項が並び、
「どこを見ればいいのか分からない」
「もし不利な契約を結んでしまったら…」
と、新たな不安が生まれてしまうのも事実です。
この記事は、そんなあなたのための「羅針盤」です。
私がコンサルタント時代に培った知識と経験のすべてを注ぎ込み、ファクタリング契約で絶対に失敗しないための「10のチェックポイント」を、誰にでも分かるように徹底解説します。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
そもそもファクタリング契約とは?押さえておくべき3つの基本
この章を読めば、あなたは契約書に書かれていることの「本質」を理解できるようになります。
ファクタリングは「融資」ではなく「債権の売買契約」です
まず、最も大切なことをお伝えします。
ファクタリングは、銀行からの借金(融資)とは全くの別物です。
これは、あなたの会社が持っている「将来、取引先からお金を受け取る権利(売掛債権)」を、ファクタリング会社に売却(譲渡)する取引です。
いわば、まだ手元にない未来の現金を、少し手数料を払って「前倒し」で手に入れるイメージですね。
私がコンサルした企業でも、「借金が増えるのは避けたい」と考える経営者の方が多くいらっしゃいました。
ファクタリングは「売買」なので、貸借対照表(B/S)上も負債にはなりません。
つまり、信用情報に影響を与えることなく、資金を調達できる。これが最大のメリットの一つです。
【図解:融資とファクタリングの違い】
| 項目 | 銀行融資 | ファクタリング |
|---|---|---|
| 取引の種類 | 金銭消費貸借契約(借金) | 債権譲渡契約(売買) |
| 審査の対象 | あなたの会社の信用力 | 取引先(売掛先)の信用力 |
| 信用情報 | 影響あり | 影響なし |
| 担保・保証人 | 原則必要 | 原則不要 |
【一行要約】ファクタリングは借金ではなく、未来の入金予定を売る「権利の売買」です。
「2社間」と「3社間」で契約内容はこう変わります
ファクタリングには、主に2つのタイプがあり、どちらを選ぶかで契約内容、特に「登場人物」が大きく変わります。
2社間ファクタリング
あなたとファクタリング会社の2社だけで完結する契約です。
取引先(売掛先)に通知する必要がないため、資金繰りの状況を知られずに、スピーディーに資金化できるのが最大のメリットです。
3社間ファクタリング
あなた、ファクタリング会社、そして取引先(売掛先)の3社が関わる契約です。
取引先に債権を譲渡したことを通知し、承諾を得る必要があります。
手間はかかりますが、ファクタリング会社にとって未回収リスクが低いため、手数料が安くなる傾向にあります。
【図解:2社間と3社間の流れ】
▼2社間ファクタリング
- あなた ⇔ ファクタリング会社(契約・入金)
- 取引先 → あなた(通常の入金)
- あなた → ファクタリング会社(返済)
▼3社間ファクタリング
- あなた ⇔ ファクタリング会社(契約・入金)
- あなた → 取引先(債権譲渡の通知・承諾)
- 取引先 → ファクタリング会社(直接支払い)
どちらが良いかは、あなたの状況次第です。
「取引先に知られず、とにかく早く!」なら2社間。
「少し時間はかかっても、手数料を抑えたい」なら3社間、という判断になります。
【一行要約】取引先に秘密なら「2社間」、手数料を安くしたいなら「3社間」です。


「基本契約」と「個別契約」- 2種類の契約書が存在する理由
いざ契約となると、2種類の契約書が出てきて戸惑うかもしれません。
でも、役割はシンプルです。
- ファクタリング取引基本契約書:
今後、継続的にファクタリングを利用するための「基本的なルールブック」です。初回に一度だけ結びます。 - 債権譲渡契約書(個別契約書):
「どの会社の、いくらの売掛債権を、いつ売るか」という、「個別の取引内容」を定めたものです。取引の都度、交わします。



これは、例えば賃貸マンションを借りる時の「賃貸借契約書(基本ルール)」と、毎月の「家賃の支払い(個別取引)」の関係に似ていますね。
継続して利用する可能性がある場合は、この2段構えになるのが一般的です。
【一行要約】「基本契約」は全体のルール、「個別契約」は今回の取引内容を決めるものです。


【最重要】元コンサルが伝授!契約書で絶対に見るべき10のチェックポイント
ここからが本番です。
契約書を前に、虫眼鏡を持って宝探しをするような気持ちで、以下の10項目を一つずつ確認していきましょう。あなたの会社を守るための、最も重要なパートです。
① 譲渡対象の債権は正確か? – 金額・支払期日・取引先
当たり前のように聞こえますが、ここが全ての土台です。
あなたが売却しようとしている売掛債権の情報が、一字一句間違いないか確認してください。
- 取引先(債務者)の名称・住所
- 債権の金額(請求額)
- 支払期日
「A社への請求書だと思っていたら、よく似た名前のB社への請求書になっていた…」
こんな単純なミスが、後々「契約違反だ」と大きなトラブルに発展しかねません。必ず、お手元の請求書と契約書を並べて、指差し確認してください。
【一行要約】売るつもりの請求書と契約書の内容が、完全に一致しているか確認しましょう。
② 手数料と諸費用 – 見積もりと相違ないか、内訳は明確か
「手数料は8%です」
この言葉だけを信じてはいけません。重要なのは「最終的に、あなたの手元にいくら残るのか」です。
契約書では、手数料の内訳を厳しくチェックしてください。
- ファクタリング手数料: ○%
- 債権譲渡登記費用: ○円(司法書士報酬含む)
- 印紙代、事務手数料など: ○円
もし、口頭での説明になかった費用が追記されていたら、それは危険なサインかもしれません。
「これは何のための費用ですか?」と、その場で必ず質問し、納得できなければ署名してはいけません。
【シミュレーション:300万円の売掛金を現金化する場合】
- 良い例(手数料10%):
買取額 270万円。その他費用なし。- 悪い例(手数料5%+不明瞭な費用):
手数料15万円は安いが、調査料10万円、事務手数料5万円などが追加され、結局買取額は270万円。もしくはそれ以下に。
【一行要約】「総額でいくら引かれるのか」を確認し、不明な費用項目は絶対に放置しないこと。
③ 償還請求権(リコース)の有無 – 「ノンリコース」の記載は絶対!
ここが、この記事で最も重要なポイントです。
契約書の中に「償還請求権なし」または「ノンリコース」という文言があるか、血眼になって探してください。
これは、「万が一、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなっても、ファクタリング会社はあなたに返金を請求しません」という、あなたを救うための生命線です。
もし、この記載がない、あるいは逆に「償還請求権あり(ウィズリコース)」と書かれていたら、その契約はファクタリングではありません。実質的な「借金」と同じです。
取引先が倒産した場合、あなたがその穴埋めをしなければならず、資金調達どころか、さらなる負債を抱えることになります。
【一行要約】「償還請求権なし(ノンリコース)」の記載がなければ、絶対にサインしてはいけません。
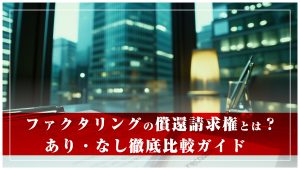
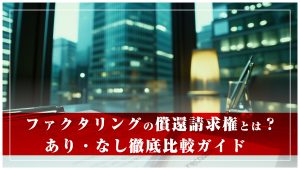
④ 債権譲渡登記 – 「留保」か「必須」か、費用負担は誰か
特に2社間ファクタリングで問題になるのが、この「債権譲渡登記」です。
これは、ファクタリング会社が「この債権は、私たちが正式に買い取りましたよ」と法務局で公示する手続きのこと。主に、あなたが同じ債権を別の会社にも売ってしまう「二重譲渡」を防ぐために行われます。
契約書で確認すべきは、
- 登記は必須か、それとも留保(通常は行わない)か
- 登記する場合、費用(数万円~)はどちらが負担するのか
登記をすると、第三者(例えば取引銀行)がその事実を知る可能性があります。それが融資に影響を与えるケースもゼロではありません。
「登記は不要と聞いていたのに…」とならないよう、契約書での扱いをしっかり確認しましょう。
【一行要約】登記の有無と費用負担を確認し、自社の状況に合うか判断しましょう。
⑤ 債権譲渡の通知 – 誰が、いつ、どのように通知するのか
これは3社間ファクタリングの場合のチェックポイントです。
取引先に債権譲渡を知らせる「通知」について、契約書でどう定められているかを確認します。
- 誰が通知するのか?(あなたか、ファクタリング会社か)
- いつ通知するのか?(契約後すぐか、など)
- どんな方法で通知するのか?(内容証明郵便など)
私がコンサルした企業では、ファクタリング会社が一方的に高圧的な通知を送ってしまい、長年の取引先との関係が悪化してしまったケースがありました。
取引先との関係を損なわないためにも、通知の進め方は事前にしっかりすり合わせておくことが重要です。
【一行要y約】取引先との関係を守るため、通知の「主体・時期・方法」を必ず確認しましょう。
⑥ 担保・保証人 – 原則不要!要求されたら危険信号
思い出してください。ファクタリングは「債権の売買」です。
したがって、不動産などの担保や、代表者個人の連帯保証人は、原則として一切不要です。
もし契約書に「担保」や「保証人」の欄があり、署名を求められたら、それは極めて危険なサインです。
その業者は、ファクタリングを装ったヤミ金融(違法な貸金業者)である可能性が非常に高いです。金融庁も、このような手口に強く注意を呼びかけています。
迷わず、その契約は中止し、別の会社を探してください。
【一行要約】担保・保証人を要求されたら、それはヤミ金融の可能性大。即座に取引をやめましょう。
⑦ 報告義務 – どんな時に、何を報告する必要があるか
契約書には、あなたの「報告義務」が定められていることがあります。
例えば、「取引先の経営状態に重大な変化(倒産の兆候など)を知った場合は、速やかに報告する」といった内容です。
この義務を怠ると、万が一の際に「義務違反」として損害賠償を請求される可能性があります。
どんな場合に、何を報告する必要があるのか。自分に不利な内容になっていないか、事前に把握しておきましょう。
【一行要約】どんな時に報告が必要かを確認し、予期せぬペナルティを避けましょう。
⑧ 損害賠償・違約金 – 不利で高額なペナルティになっていないか
あなたが契約内容に違反した場合の、ペナルティに関する条項です。
もちろんルールを守ることは大前提ですが、その内容が一方的にあなたに不利で、法外な金額になっていないかを確認する必要があります。
- どんな行為が「違反」と見なされるのか
- 違約金の金額は、実際の損害に対して妥当か
例えば、「入金された資金の送金が1日でも遅れたら、遅延損害金として年率50%を請求する」といった、あまりに高額なペナルティは要注意です。
【一行要約】ペナルティの内容が、一方的で高額すぎないかチェックしましょう。
⑨ 契約解除の条件 – 一方的に解除されないか、中途解約は可能か
どんな場合に、この契約が解除されるのかを定めた条項です。
特に注意したいのは、「ファクタリング会社の判断で、いつでも一方的に契約を解除できる」といった趣旨の条項がないか、という点です。
これでは、あなたにとって非常に不安定な契約になってしまいます。
また、あなたから中途解約したい場合の手続きや、その際の費用の扱いについても、明記されているか確認しておくと、より安心です。
【一行要約】ファクタリング会社に有利すぎる解除条項がないか、確認しましょう。
⑩ 契約期間と自動更新 – 知らない間に更新料が発生しないか
基本契約書には、「契約期間1年」といった有効期間が定められていることがあります。
その場合、必ずセットで確認したいのが「自動更新」の条項です。
- 契約は自動で更新されるのか?
- 更新を望まない場合、いつまでに、どうやって伝えればいいのか?
- 更新時に、更新料などの費用は発生しないか?
「もう利用しないと思っていたのに、解約手続きを忘れていて、自動更新で更新料を請求された…」という相談は、意外と多いのです。
契約の出口まで、しっかり確認しておきましょう。
【一行要約】契約の終わり方を確認し、「知らない間の自動更新」を防ぎましょう。
【実践編】問い合わせから入金まで|契約手続き5つのステップと注意点
知識を武器に変え、実際に行動に移すためのステップです。
この流れに沿って進めれば、慌てず、安全に資金調達を完了できます。
ステップ1:複数社へ相談・相見積もり
これが成功の鍵です。
悪質業者を避け、あなたの会社にとって最も良い条件を見つけるために、必ず2~3社に相談し、見積もり(相見積もり)を取りましょう。
「急いでいるから」と1社に決めてしまうのが、最も危険な道です。
ステップ2:必要書類の準備・提出
一般的に以下の書類が必要になります。スムーズな審査のために、早めに準備しておきましょう。
- 必須 → 身分証明書、売掛金の請求書、事業用の通帳コピー(直近3ヶ月分など)
- 追加で求められる場合 → 決算書、商業登記簿謄本、印鑑証明書など
ステップ3:審査
ファクタリング会社が、主にあなたの会社ではなく「取引先(売掛先)の支払い能力」を審査します。
そのため、あなたの会社が赤字決算や税金滞納の状態でも、利用できる可能性は十分にあります。
ステップ4:契約内容の最終確認と締結
審査に通ると、契約書が提示されます。ここで、この記事の「10のチェックポイント」を使って、最終確認を行ってください。
全ての項目に納得できたら、署名・捺印します。電子契約の場合は、タイムスタンプ付きの契約書PDFを必ず保存しておきましょう。
ステップ5:債権譲渡と入金確認
契約締結後、ファクタリング会社からあなたの口座に、手数料を差し引いた代金が振り込まれます。契約書に記載された期日通りに入金されるか、必ず確認してください。
よくある質問(FAQ)
最後に、多くの方が抱く疑問に、Q&A形式でお答えします。
Q: 契約書の雛形(テンプレート)はどこかで入手できますか?
A: 弁護士事務所のサイト等で公開されている例もありますが、各社で内容は異なります。重要なのは、雛形を覚えることより、提示された契約書のポイントを本記事のチェックリストで確認することです。この記事が、あなただけの最強のテンプレートになります。
Q: 「償還請求権なし」なら、売掛先が倒産しても本当に返済義務はないのですか?
A: はい、その通りです。ノンリコース契約であれば、売掛先が倒産しても利用者が返済義務を負うことはありません。そのためのファクタリングです。契約書に「償還請求権なし」または「ノンリコース」と明記されていることを、重ねて必ず確認してください。
Q: 手数料以外に、後から請求される費用はありますか?
A: 優良な会社であれば、契約前に提示した見積もり以外の費用を後から請求することはありません。しかし、悪質な業者は「調査料」「事務手数料」などを別途請求するケースがあります。契約書に記載のない費用は支払う義務はありません。
Q: 契約書にサインした後でも、キャンセル(クーリングオフ)はできますか?
A: ファクタリングは事業者間の契約であり、消費者を守るクーリングオフ制度の適用は基本的にありません。そのため、署名・捺印はすべての内容に納得してから行う必要があります。安易な契約は絶対に避けてください。
まとめ:あなたの未来を照らす、賢い一歩を
この記事では、ファクタリング契約で失敗しないための10のチェックポイントと、契約手続きの具体的な流れを解説しました。
もう一度、最も重要な3つのポイントを繰り返します。
- 「償還請求権なし(ノンリコース)」の記載は絶対か?
- 手数料の内訳は明確で、不当な追加費用はないか?
- 担保や保証人を要求されていないか?
契約書は、あなたの会社を守るための最後の砦です。
そして、正しい知識は、その砦をより強固にするための武器となります。



内容をしっかり理解し、少しでも疑問があれば遠慮なく質問する。その姿勢が、あなたをリスクから遠ざけ、安全な資金調達へと導きます。
資金繰りに悩むのは、あなただけではありません。
この記事を片手に、まずは信頼できるファクタリング会社を2~3社探し、相談してみることから始めてみませんか?
その一歩が、あなたの会社の苦しい今を乗り越え、明るい未来を切り拓く、賢明な一歩となることを心から願っています。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化



