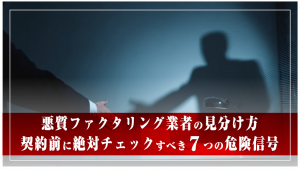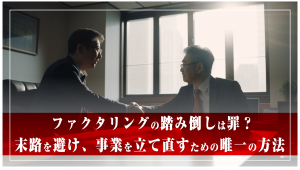「手数料が高すぎて結局赤字になるのでは?」「取引先に知られたら関係が悪化しそう…」――ファクタリングを検討するとき、こんな不安が頭をよぎりませんか。
 山田 麻里
山田 麻里実は私の元にも、契約後に“想定外の落とし穴”に悩む中小企業経営者からの相談が毎週のように届きます。
本記事では ファクタリングのデメリット5選と具体的な回避策を、資金繰り支援歴10年超の中小企業専門ファイナンシャルアドバイザーである筆者が徹底解説します。
【この記事の結論】ファクタリングの5つの致命的なデメリット
ファクタリングは迅速な資金調達に有効ですが、契約前に知るべき5つの重要なデメリットがあります。対策を怠ると、かえって資金繰りを悪化させる危険性があるため注意が必要です。
- 手数料が高い
銀行融資の金利(年数%)に比べ、手数料は数%〜20%程度と高額。特に「2社間ファクタリング」は割高で、利益を圧迫する可能性があります。 - 取引先に知られるリスク
「3社間ファクタリング」では取引先への通知が必須。資金繰りの悪化を懸念され、今後の取引に影響が出る恐れがあります。 - 悪質な業者の存在
法整備が追いついていないため、「ヤミ金」のような悪質業者が存在するのも事実です。法外な手数料や不透明な契約を迫られる危険があります。 - 根本的な資金繰りは改善しない
あくまで「売掛金の前借り」であるため、根本的な経営改善には繋がりません。常用すると手数料負担でかえって資金繰りが悪化し、「自転車操業」に陥るリスクがあります。 - 銀行融資で不利になる可能性
ファクタリングの利用自体は信用情報に記録されませんが、頻繁な利用は「資金繰りが厳しい」と判断され、銀行融資の審査でマイナス評価となるケースがあります。
本文では、これらのデメリットを回避するための具体的な対策や、手数料を安くする交渉術を詳しく解説します。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
今さら聞けない『ファクタリング』とは?仕組みとメリットを簡単解説
ファクタリングの仕組みを図解|売掛金が即日現金になる流れ
ファクタリングは、企業が保有する「売掛金(売掛債権)」をファクタリング会社に買い取ってもらい、支払い期日前に現金化する資金調達手段です。
銀行融資とは異なり、企業の財務状況よりも「売掛先(取引先)の信用力」が重視されるため、赤字決算や創業間もない企業でも利用しやすいといわれています。
では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
短期的な資金繰りが改善しやすい
銀行融資は審査に時間がかかるケースが多いですが、ファクタリングであれば必要書類さえ揃えば数日、場合によっては即日で資金化できる可能性があります。
信用情報への影響が少ない
売掛金の売却にあたるため、借入金のように負債を計上する必要がありません。
「借金ゼロで資金を確保する手段」として注目されやすいのも特徴です。
取引先の倒産リスク回避
ノンリコース(償還請求権なし)の契約であれば、仮に取引先が倒産して売掛金が回収不能になった場合でも、利用企業に返済義務が生じないことがあります。
ただし、契約形態によっては償還請求権ありの場合もあるため、事前の契約確認が欠かせません。


2社間と3社間ファクタリングの違いは?手数料と通知リスクで選ぶ最適な方法
ファクタリングは「2社間」と「3社間」で契約形式が異なり、それぞれメリット・デメリットがあります。
以下に簡単な表を用意しましたので、比較の参考にしてみてください。
| 形式 | 契約当事者 | 通知の有無 | 一般的な手数料 | 資金化スピード | 取引先へのイメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2社間方式 | 利用企業・ファクタリング会社 | 取引先への通知なし | 高め(数%~20%程度) | 迅速(最短即日) | 知られにくい |
| 3社間方式 | 利用企業・ファクタリング会社・取引先 | 取引先への通知(承諾)必須 | 低め(数%~10%程度) | 多少時間がかかる | ファクタリング利用が伝わる |
一般的には、取引先に知られずに利用できる2社間ファクタリングの方が手数料は高く、3社間ファクタリングは手数料が安い代わりに取引先への通知が必要です。
取引先との関係性やコスト意識によって、どちらを選ぶかを検討するとよいでしょう。
ファクタリングはどんな時に使う?中小企業が活用すべき3つのケース
私がコンサルタントとして中小企業の資金繰りに関わってきた経験から言えるのは、多くのケースで「銀行融資が間に合わない」「審査が通らない」あるいは「取引先からの入金サイトが長い」といった理由が挙げられるという点です。
特に、下記のような背景をお持ちの企業では、ファクタリングのニーズが高まる傾向があります。
① 銀行融資の審査が厳しい状況にある
┗ 設立間もないベンチャーや、赤字が続いている中小企業
② 取引先の支払いサイトが長い
┗ 建設業や製造業など、60日・90日後に入金がずれ込む業態
③ 一時的なキャッシュ不足を解消したい
┗ 仕入れや人件費、税金の支払いが迫っているが、融資審査では間に合わない場合
こうした課題を抱える企業が、比較的柔軟に利用できる資金調達方法としてファクタリングに注目しているのです。
ただし、次章以降で解説するように、ファクタリングにはメリットの裏にデメリットも存在します。
利用を検討する際は、長所だけでなく短所やリスクを十分に把握したうえで、最適な契約形態を選ぶことが大切だと言えるでしょう。
契約前に知らないと大損!ファクタリングの致命的なデメリット5選
デメリット1:手数料はなぜ高い?銀行金利との比較と相場を解説
ファクタリング最大のデメリットは、なんといっても「手数料の高さ」です。
銀行融資の金利が年数%であるのに比べると、ファクタリングの手数料は売掛金額の数%~20%程度と割高になります。
特に2社間ファクタリングでは、取引先に通知しない分だけファクタリング会社がリスクを負うため、手数料がさらに上乗せされる傾向があります。
一度だけの利用であればまだしも、これを常態化すると利益率を大きく圧迫する可能性が高いです。
- 利用頻度が高いほど手数料の合計負担が増えやすい
- 取引先の信用力が低いと、さらに高額な手数料を提示されることがある
- 売掛金を先に使い込んでしまうことで、将来的なキャッシュフローにも影響する
たとえば、100万円の売掛金を手数料15%でファクタリングした場合は、15万円のコストがかかります。
仮に利益率が10%の取引であれば、ファクタリングをした時点で赤字になる計算です。
短期のつなぎ資金が必要な場面ではやむを得ないかもしれませんが、常用すると「先に入るはずだったお金が常に減っていく状態」に陥りやすくなります。
デメリット2:取引先にバレる?資金繰り悪化を疑われる通知リスクと回避策
ファクタリングには「2社間方式」と「3社間方式」がありますが、3社間方式の場合は取引先への通知と承諾が必須です。
取引先に「うちの資金繰りが厳しいのでは?」という印象を与えたくない場合、通知リスクは大きなデメリットと言えるでしょう。
2社間方式を選べば通知を回避できる一方で、手数料が高くなる懸念もあります。
- 3社間では取引先に知られるため、取引継続が不安視されるリスクがある
- 2社間を選ぶとコストが高くなりやすい
- 債権譲渡登記を求められると、登記情報から取引先に知られる可能性もゼロではない
- 「キャッシュフロー改善策の一環」としてポジティブに説明する
- 自社の財務的健全性や成長戦略をきちんと伝え、相手の不安を払拭
- 取引先が協力的であれば、3社間でも低い手数料で資金化できるチャンスがある
取引先が大手企業の場合、その企業の承諾が必要になるなど、実務的にも時間がかかるケースがあります。
取引先への通知リスクは心理的負担が大きいと感じる経営者も少なくありません。
デメリット3:危険な『ヤミ金』業者の見分け方|契約を避けるべき3つの特徴
ファクタリング業界はまだ法整備の途上ということもあり、残念ながら悪質な業者が紛れ込んでいるのも事実です。
手数料を高額に設定しておきながら、「審査なし即日OK」「誰でも利用可能」などと謳い、結果的に高利貸しと変わらない契約を結ばせるケースもあります。
- 契約書の条項が不透明なまま契約を急かされる
- 手数料以外にも、違約金や追加費用などの名目で予想外のコストを請求される
- ノンリコース契約のはずが、実質的には企業側が返済義務を負うような契約形態になっている
もし悪質業者と知らずに契約してしまうと、法外なコストを支払うだけでなく、トラブルが長期化するリスクも考えられます。
また、契約形態によってはファクタリングが単なる「闇金」と見なされるおそれもあるため、十分に注意しなければなりません。
- 公式サイト・会社概要が明確に公開されているかをチェック
- 複数社からの見積もりや評判を比較検討する
- 契約書の内容や料金体系を細かく確認する
上記のようなステップを踏むことで、悪質業者との契約リスクを大幅に減らすことができます。
デメリット4:なぜ『自転車操業』に陥るのか?根本的な資金繰りが改善しない仕組み
ファクタリングは、あくまで「売掛金を先取りする」仕組みです。
したがって、一時的にキャッシュが潤ったように見えても、本来入金されるタイミングで実際のキャッシュインが減ってしまうデメリットがあります。
- その場しのぎとしては有効でも、根本的な資金繰り改善にはつながらない
- 高頻度で繰り返すと、常に次の売掛金を前倒しで使い続ける「依存状態」になる
- 利益率が低いビジネスで頻繁に使えば、手数料の累積で収益がさらに圧迫される
長期的に安定した経営を考えるならば、ファクタリング以外の方法を組み合わせることが大切だと言えます。
銀行融資、補助金・助成金、投資家からの出資(エクイティファイナンス)など、ほかの選択肢も積極的に検討してみましょう。
デメリット5:信用情報に傷がつく?銀行融資で不利になるケースとは
ファクタリング自体は「負債」として扱われないため、通常は信用情報に大きな影響を与えません。
しかし、契約形態や今後の取引状況によっては、金融機関が「キャッシュフローが安定していないのでは」と判断する可能性もあります。
特に、短期間に何度もファクタリングを利用している企業の場合、銀行融資の審査でマイナス要因とみなされるリスクがあるでしょう。
- ファクタリング利用履歴そのものは信用情報機関に登録されない
- ただし、「資金繰りが厳しいから頻繁に売掛金を前倒ししているのでは」と推測される可能性あり
- 今後の銀行融資やビジネスローンの審査で不利になるケースも考えられる
以下の項目を自社で確認しましょう。
- 直近6ヶ月でファクタリングを何度利用したか
- 他の資金調達方法との併用プランはあるか
- 利用したファクタリング会社の評判や実績は問題ないか
頻繁にファクタリングを使わざるを得ないほど資金繰りが追いつかない場合は、根本的なビジネスモデルやキャッシュフローサイクルを見直すべきサインかもしれません。
ファクタリングで失敗しないための賢い自衛策と交渉術
手数料を安くする3つの交渉術|相見積もりと与信力の活用法
ファクタリングの最大の難点である「手数料コスト」を下げるには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
私自身、中小企業向けコンサルの現場で「どこに相談すればいいのかわからない」という経営者の方に対して、以下のステップをおすすめしてきました。
1. 複数のファクタリング会社から見積もりを取る
- 手数料率はもちろん、審査スピードや追加費用(契約書作成費用・登記費用など)も比較する
- とくに2社間ファクタリングは手数料が高めになりがちなので要注意
2. 取引先の信用力を強みにする
- 売掛先が大企業や公的機関であれば、与信リスクが低い分手数料の引き下げ交渉がしやすい
- 手数料だけでなく「サービス内容」や「資金化までの日数」なども併せて評価する
3. 3社間ファクタリングも検討する
- 取引先が協力的ならば、手数料を大幅に下げられる可能性がある
- 通知リスクがあっても、月々のキャッシュフローへの負担が軽減されるメリットは大きい
優良ファクタリング会社の選び方|公式サイトで見るべき6つのチェック項目
悪質業者を回避し、安心してファクタリングを利用するためには「業者選び」と「契約書の内容チェック」が肝心です。
私はコンサルタント時代に、契約書を隅々まで読まないまま締結してしまい、高額な違約金を請求された中小企業を何社も見てきました。
そうならないためにも、以下を徹底しましょう。
✔️ 業者選びのポイント
- 会社概要や所在地、代表者の情報を公式サイトできちんと公開しているか
- 創業実績や取引件数など、具体的な数字が明示されているか
- SNSや口コミサイトで悪評が目立たないか(あまり鵜呑みにしすぎないことも大事)
✔️ 契約書確認のポイント
- 手数料の計算方法や支払いスケジュールが明瞭か
- 追加費用や違約金が発生する条件がはっきり書かれているか
- ノンリコース(償還請求権なし)契約であるか、実質借入のような形態になっていないか
経営コンサルタントや税理士、弁護士に相談すると、契約書のチェックや費用相場の把握がスムーズです。
自社だけで判断が難しい場合は、時間とコストをかけてでも専門家に目を通してもらうことをおすすめします。
ファクタリング以外の資金調達方法|銀行融資・補助金との賢い使い分け
ファクタリングは便利な一方、長期的には「売掛金の先取り」にしかならず、根本的な財務改善には結びつきにくいという難点があります。
そこで、銀行融資や補助金・助成金、ビジネスローンなど、他の資金調達方法と組み合わせながらリスクを分散することが理想的です。
銀行融資やビジネスローン
- 年利数%程度で借りられる可能性があり、手数料より割安になるケースが多い
- 審査は厳しいものの、長期資金として使いやすい
- 信用情報を積み上げることで、次の融資が受けやすくなるメリットも
補助金・助成金の活用
- 設備投資や新規事業に対する公的支援制度を活用すれば、経営の安定と成長を同時に目指せる
- 申請手続きが複雑な場合があるため、専門家のサポートを受けると良い
エクイティファイナンス(増資)
- 投資家から出資を受ける形なので、返済義務は発生しない
- 一方で、株式を渡すことにより経営権の一部が移るデメリットも
- 中長期的に事業を大きくしたいベンチャー向けの資金調達
ファクタリングと銀行融資、どっちを選ぶべき?|メリット・デメリット比較表
ファクタリング以外の主要な資金調達手段と、そのメリット・デメリットをまとめてみました。
| 資金調達手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ファクタリング | – 審査が比較的通りやすい – 即日~数日で資金化しやすい | – 手数料が高め – 取引先通知リスクがある |
| 銀行融資 | – 金利が低め(年利1~3%程度) – 長期資金の確保が可能 | – 審査が厳しい – 審査完了までに時間を要する |
| ビジネスローン | – 銀行よりは審査が柔軟 – 比較的迅速に借入できる | – 金利が高め(年利10%前後のケースも) – 信用情報に影響 |
| 補助金・助成金 | – 返済義務なし – 中小企業支援策など種類が豊富 | – 申請や事務手続きが複雑 – 受給まで時間がかかる |
| エクイティファイナンス(増資) | – 返済不要 – 成長が見込めれば大きな資金調達も可能 | – 経営権の一部を投資家に譲渡 – ビジネスプランの説得が必要 |
よくある質問(FAQ)
まとめ
ファクタリングは売掛金を早期現金化し、資金繰りを一時的にでも安定させる有効な手段と言えます。
銀行融資やビジネスローンでは対応できない「急ぎの支払いが迫っている」「融資審査に通りにくい」という状況に強みを発揮するからです。
しかし同時に、手数料コストの高さや取引先への通知リスクなど、押さえておきたいデメリットも存在します。
過度に依存すると、かえってキャッシュフローを悪化させてしまう恐れさえあるでしょう。
- 短期・スポットでの資金調達に使い、長期利用は避ける
- 複数のファクタリング会社を比較し、悪質業者を回避する
- 銀行融資や補助金など、他の資金調達手段との併用も検討する
- 取引先に通知が必要な場合は、誠意をもって説明・根回しをする
私自身、金融コンサルとして中小企業の資金繰りをサポートしてきた経験から感じるのは、ファクタリングはあくまでも「売掛金の前借り」であるということです。
したがって、本質的な経営課題を解決するためには、収益モデルの再構築やコスト管理、取引先との交渉力強化といった根本的な経営改善が必要になります。
ファクタリングをきっかけにして「見直すべき点」が浮き彫りになるケースも少なくありません。
ぜひ今回の記事を参考に、ファクタリングと他の選択肢を併用しながら、自社のキャッシュフロー最適化と長期的な成長を目指してみてください。
ファクタリングは決して「悪い手段」ではなく、使い方を誤ると痛手を被りやすい手段です。
ここでお伝えしたデメリットや対策を踏まえ、正しく利用すれば、突然の資金ショートリスクを避けながら安定した経営を実現できます。
中小企業にとっては頼もしい選択肢の一つですので、ぜひ冷静な比較検討を行い、適切な方法でファクタリングを活用してみてください。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化