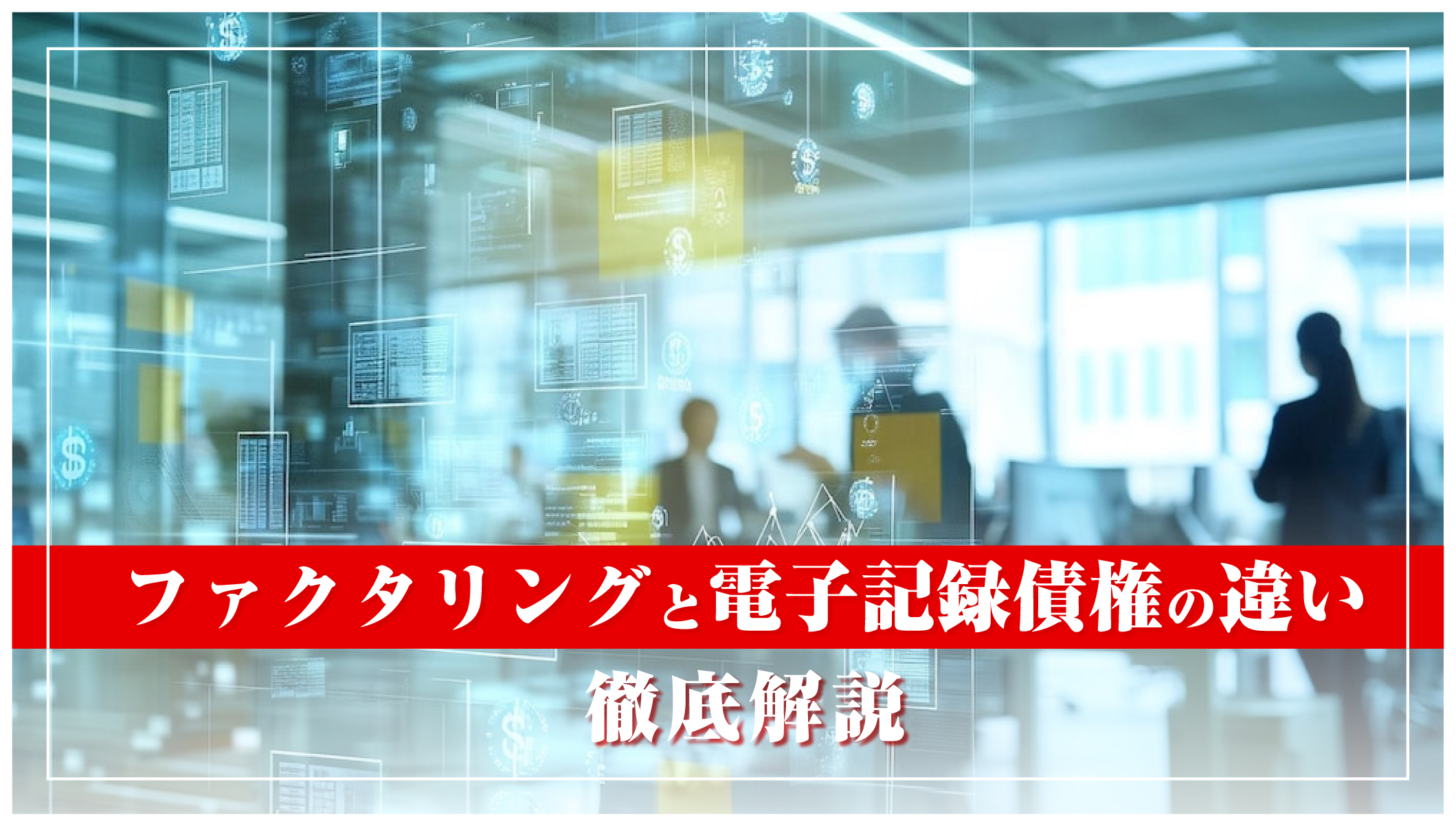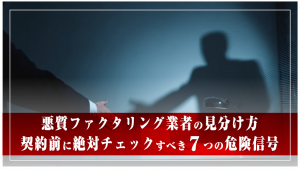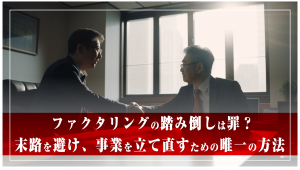「ファクタリングとでんさい、聞いたことはあるけど、結局うちの会社にはどっちが合っているんだろう…」
資金繰りを考える中で、そんな風に手が止まっていませんか?
ご安心ください。元金融コンサルタントとして数多くの中小企業を支援してきた経験から断言します。
 山田 麻里
山田 麻里ファクタリングとでんさいは、会社の状況によって「正解」が明確に分かれます。
本記事では、ファクタリングとでんさいの根本的な違いから、あなたの会社が「今すぐ選ぶべきはどちらか」を判断できる具体的なポイントまで徹底解説します。
【この記事の結論】ファクタリングと「でんさい」の主な違い
- 目的と仕組みの違い
- ファクタリング: 売掛債権を「譲渡」して早期に資金化するサービス。
- でんさい: 手形や売掛債権を「電子記録」で管理する決済の仕組み。資金化には「でんさい割引」を利用。
- 資金調達のスピード
- ファクタリング: 最短即日も可能で、緊急性の高い資金調達に向いている。
- でんさい: 導入に数週間かかる場合があり、即時の資金化には不向き。
- 取引先への通知
- ファクタリング: 「2社間契約」なら取引先に知られずに利用可能。
- でんさい: 仕組み上、取引先(売掛先)の協力や登録が必須となる。
- 貸し倒れリスクの所在
- ファクタリング: リスクをファクタリング会社に移転できる(償還請求権なしの場合)。
- でんさい: リスクは自社が負う。売掛先が倒産すると回収不能になる。
本文では、これらの違いや具体的な使い分け、それぞれのメリット・デメリットをさらに詳しく解説します。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
ファクタリングとは?
ファクタリングの基本仕組み
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、支払い期日を待たずに現金化できる仕組みです。
中小企業や個人事業主が資金繰りを早期に改善する手段として、近年ますます注目を集めています。
ポイントを簡潔にまとめると、以下のようになります。
- 売掛先が支払うはずの代金を、ファクタリング会社が立て替えてくれる
- 売掛金が期日を迎える前に資金調達が可能
- 基本的に担保や保証人は不要(売掛金自体が担保の役割を果たす)
- 売掛先の信用力が重要視されるため、自社が赤字でも利用できる可能性がある


2社間ファクタリングと3社間ファクタリング
ファクタリング契約には大きく分けて2種類の形態があります。
| ファクタリング方式 | 主な特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 2社間ファクタリング | – 利用企業とファクタリング会社だけで契約 – 売掛先への通知は不要 | – 取引先に知られず資金調達できる – 審査や契約手続きがスピーディー | – ファクタリング会社のリスクが高いため手数料率が高め – 利用を繰り返すと負担が大きくなる可能性 |
| 3社間ファクタリング | – 利用企業・ファクタリング会社・売掛先の3者契約 – 売掛先が譲渡を承諾 | – ファクタリング会社のリスクが下がるため手数料率が低め – 後々のトラブルが起こりにくい | – 売掛先にファクタリング利用を知られてしまう – 承諾を得るための手続きに時間がかかる |
2社間は「取引先に事情を知られたくない」「とにかく早く資金が必要」という場合に適していると言えるでしょう。
一方、3社間は「手数料を抑えたい」「相手との信頼関係は十分にあるため通知されても問題ない」ケースで検討されることが多いです。
ファクタリングのメリット・デメリット
ファクタリングはキャッシュフロー改善に大いに役立ちますが、注意すべき点もいくつかあります。
💡 メリット
- 入金サイクルを大幅に短縮できるため、急な仕入れや給与支払いにも対応しやすいです。
- 売掛先の倒産リスクを実質的に回避できる場合が多いです(ノンリコース型契約)。
- 担保や保証人が不要で、銀行融資が難しい企業でも利用できる可能性があります。
⚠️ デメリット
- 手数料がかかるため、売掛金を満額で回収できないデメリットがあります。
- 悪徳業者に当たると高額な費用を請求されるなどのリスクがあり、信頼できるファクタリング会社選びが重要です。
- 3社間ファクタリングでは、売掛先に資金繰りを知られてしまい、取引関係に影響が及ぶ可能性があります。
ファクタリングは確かに便利ですが、手数料負担がネックになりやすい面があります。
何度も繰り返し利用するような状態が続くと、せっかくの売掛金が目減りしてしまう可能性が高いです。
そのため、もしファクタリングを導入する際は、並行してキャッシュフロー改善策を進めることをおすすめします。
例えば、取引先との支払いサイトの見直しや在庫回転率の向上などです。
「緊急時のスポット利用」ぐらいのイメージを持っておくと良いでしょう。
でんさい(電子記録債権)とは?
でんさいの基本仕組み
「でんさい」とは、従来の紙の手形や売掛債権を電子上でやり取りできるようにした仕組みです。
正式には「電子記録債権」と呼ばれ、全国銀行協会が運営する「でんさいネット」というシステムを通じて記録・管理されます。
紙の手形と違って印紙代が不要であるほか、紛失・盗難などのリスクも大幅に低減できることから、近年注目度が増している決済手段です。
具体的には以下のような流れになります。
- 売掛先が「支払いデータ」をでんさいネットに登録し、電子記録債権を発行する
- 受取企業(債権者)は期日になれば自動で入金を受けられる
- 早期に資金化したい場合、金融機関で「でんさい割引(買取)」を利用できる
このようにでんさいは、「取引データをオンラインで管理し、必要に応じて資金を前倒しで得る」仕組みとイメージするとわかりやすいでしょう。
ただし利用を始めるには、自社も取引先もともにでんさいネットに登録している必要があります。
また、金融機関からの審査で信用力が問われるケースもあり、導入までに少し時間がかかる点がファクタリングとの大きな違いです。
でんさいのメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 費用面 | – 紙の手形に必要な印紙代が不要 – 割引手数料も比較的低率 | – 初期登録や月額利用料がかかるケースあり – 割引を利用する際は信用力次第で金利が変動 |
| 資金調達スピード | – 期日到来時の入金は自動 – システム利用後は手続きが簡易 | – 割引で前倒しするには金融機関の審査が必要 – 即日・翌日など超短期の資金調達には不向き |
| リスク管理 | – 紙の紛失・盗難のリスクがない – 取立などの手間が軽減 | – 支払側が倒産すると債権未回収のリスクが利用企業に残る – ノンリコース契約がなく償還義務が発生 |
| 導入のしやすさ | – 一度システムを整えれば取引を電子化しやすい | – 自社・取引先双方が登録しなければならない – 銀行によっては導入審査が厳しい場合がある |
| 取引先への通知 | – 取引そのものが電子管理で透明性が高い | – 債権譲渡の事実は支払側に通知される – 「非通知で資金化したい」というニーズに応えにくい |
💡 メリット
- 紙の手形と比べて事務コストやリスクが大幅に減らせる
- 金融機関での割引利用なら、手数料率が比較的低め
- 分割譲渡が可能なため、「必要な分だけ」資金化できる柔軟性がある
⚠️ デメリット
- 取引先もでんさいネットを導入していないと使えない
- 売掛先の倒産リスクは利用企業側が負い続ける(償還義務がある)
- 開始までに口座開設やシステム登録が必要で、即時導入は難しい
- すでに手形決済が多く、印紙代や紛失リスクを避けたい
- 主要な取引先がでんさいを使っている、または導入に前向き
- 資金調達を急がず、計画的に低コストで現金化したい
- 自社が金融機関から一定の信用を得られる財務体質である
上記の条件を満たすなら、でんさいは大きくコスト削減と事務効率化をもたらす可能性があります。
ただし「倒産リスクを一切背負いたくない」という場合は、別の方法(ファクタリングなど)との併用を検討するのも選択肢でしょう。
ファクタリングとでんさいの違い・使い分け
資金調達スピードとコスト
ファクタリングとでんさいを比較する際に、まず重要となるのが「資金化の速さ」と「手数料負担」です。
緊急度が高い場合は、どうしてもファクタリングに軍配が上がるシーンが多いでしょう。
一方、コスト面を重視するならばでんさいが適しているケースがあります。
ファクタリングの特徴
- 最短即日資金調達が可能(特に2社間ファクタリング)
- 取引先の承諾不要で早いが、手数料率が高め
- 継続的に利用すると手数料負担がかさんでしまう
でんさいの特徴
- 割引利用しない限り追加の手数料は低い(印紙代も不要)
- 割引する場合も金利が比較的低率に設定されることが多い
- ただしすぐに導入できないケースが多く、即日資金化には向かない
下記の表は、ファクタリングとでんさいを「スピード」と「コスト」の観点で比較した例です。
| 比較項目 | ファクタリング | でんさい(電子記録債権) |
|---|---|---|
| 資金調達スピード | – 2社間であれば最短即日~数日 – 3社間は売掛先の承諾が必要で1週間程度かかることも | – 運用開始までは口座開設やシステム登録で時間を要する – 割引利用の場合は金融機関の審査次第 |
| コスト負担 | – 2社間:売掛金額の8~18%程度が手数料の目安 – 3社間:2~9%程度とやや低め | – 発生記録手数料や月額利用料などは安価 – 割引手数料は年率1.5~5.5%程度が相場 |
| 向いているケース | – 「早く資金が欲しい」「取引先に知られたくない」 | – 「手形文化から脱却したい」「低コストで計画的な資金調達をしたい」 |
債権管理や信用リスクの違い
ファクタリングとでんさいは、債権を「誰が管理し、どこにリスクが残るのか」という点でも大きく異なります。
◉ファクタリングは貸し倒れリスクをファクタリング会社に移転できる
- ノンリコース型(償還請求権なし)の契約であれば、売掛先が倒産しても返済義務が生じないケースがほとんどです。
- 売掛先の信用リスクをファクタリング会社が背負う形になるため、利用企業としては安心感が高いです。
◉でんさいは利用企業が倒産リスクを引き続き背負う
- 期日まで待てば満額受け取れますが、もし売掛先が倒産してしまうと未回収になる可能性があります。
- 割引利用して早期現金化していた場合、支払不能時には金融機関から償還を求められるリスクがあります。
ファクタリングは「確実にお金を手に入れる」代わりに、手数料がやや高めになります。
一方のでんさいは低コストですが、倒産リスクを負う点には注意が必要です。
取引先の信用度が高ければ問題ないかもしれませんが、大口案件などは慎重な判断が求められます。
以上を踏まえると、「万が一の倒産リスクを避けたいならファクタリング」「自社と取引先双方が盤石でコストを抑えたいならでんさい」という大きな使い分け軸が見えてきます。
導入時の注意点と選び方
ファクタリング導入のポイント
ファクタリングを導入する際は、以下の点をしっかり確認しておく必要があります。
1.ファクタリング会社の信頼度を見極める
- 公式サイトで会社概要や実績、手数料の透明性を確認
- 経営者仲間の口コミや、金融関連の専門メディアによるランキングを参考にする
- 極端に高い手数料率を提示してくる業者は注意が必要
2.契約形態(2社間か3社間か)の選択
- 2社間ファクタリング:スピード重視・取引先に知られずに利用したい場合
- 3社間ファクタリング:手数料をなるべく抑えたい、売掛先との関係に問題がない場合
3.キャッシュフローや会計処理との連動
- 実際の入金タイミングに合わせて財務管理をする
- 短期的に資金繰りを改善できても、長期利用では手数料負担が増すリスクがある
- 継続利用の場合は、売掛先別にかかる手数料率や回収状況を定期的にチェック
たとえば「急に大型受注が入り、仕入れ資金が不足している」場面などでは、2社間ファクタリングを利用して即日~数日で資金調達した例があります。
私のコンサル時代にも、月末の給与支払いが迫るなかでファクタリングを利用して乗り切ったケースを何度か見ました。
ただし、こうした利用が毎月のように続くと手数料がかさむので、根本的なキャッシュフロー対策が必要になります。
でんさい導入のポイント
でんさいは、電子記録債権システムを使った決済・資金化の手段です。導入前に以下をチェックしましょう。
1.自社と主要取引先の登録状況を確認
- 取引先が未登録の場合、口座開設から協力してもらう必要がある
- 中小企業ではまだ導入率が低い業界もあるため、相手先との連携が不可欠
2.金融機関での審査に備える
- でんさい割引(期日前に現金化)を利用する場合は、銀行側が自社の信用度を審査する
- 銀行融資に近いプロセスがあるため、決算内容や取引実績を整理しておく
3.紙の手形からの移行メリットを試算する
- 印紙代や郵送費などの削減額を数値化し、導入コストと比較
- 一度導入すれば継続的に業務効率化できるので、中期的なメリットが大きい
ファクタリングとでんさいのハイブリッド活用
両者は「二者択一」ではありません。実務の現場では、次のような併用パターンを見かけることもあります。
- 主要な取引先はでんさいで決済し、安定したキャッシュフローを確保
- 新規や不定期の取引先に対してはファクタリングでリスクヘッジ
- 緊急時だけファクタリングを利用し、それ以外はでんさいや一般的な回収サイトで運用
こうすることで、普段のコストを抑えながら急な資金不足にも対応できる体制をつくることが可能です。
営業担当や経理担当が入り混じるケースでは、まず社内で「でんさいの導入意義」を共有することがポイントです。
一方、既存の取引で現場がすぐには切り替えられない場合、ファクタリングを併用することで即時の資金繰り不安を解消できます。
自社だけで決めるのではなく、取引先や金融機関と積極的にコミュニケーションをとりながらベストな組み合わせを探してください。
よくある質問(FAQ)
まとめ
ファクタリングとでんさいはいずれも、中小企業や個人事業主にとって資金繰り改善を図る上で有力な手段と言えます。
◉ファクタリング:
- スピード重視の資金調達が可能
- 倒産リスクを回避しやすいが、手数料がやや高め
- 銀行融資が受けられない場合や緊急時のキャッシュ確保に最適
◉でんさい(電子記録債権):
- 印紙税や紛失リスクなど、紙の手形特有の問題を解消できる
- 割引利用でも金利負担が比較的抑えられる
- ただし倒産リスクは自社が負い続ける点に注意
最終的にどちらを選ぶかは、自社の信用力、取引先の状況、資金繰りの緊急度などによって変わります。
私自身の実務経験から言えるのは、「どちらか一方に固執するのではなく、必要に応じて上手に使い分ける」ことが成功のカギです。
- 取引先が安定している場合はでんさいをベースにし、手形業務や印紙代を削減
- 新規取引先や支払いサイトが長いケースは、ファクタリングで早めに現金を確保
- 緊急時はファクタリングを利用し、それ以外は通常の現金回収やでんさいに任せる
自社のキャッシュフローを客観的に評価し、最適な手段を選ぶことが、経営の安定につながるでしょう。
ぜひ本記事を参考に、ファクタリングとでんさいの特徴を整理しながら、自社にぴったりの資金調達方法を検討してみてください。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化