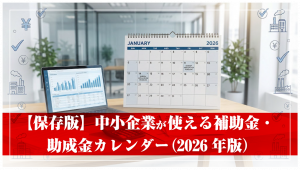多くの中小企業経営者が設備投資や販路開拓の資金調達に頭を悩ませています。
「銀行融資のハードルは高い」「自己資金だけでは足りない」そんな状況で検討したい選択肢の一つが「補助金」です。
しかし、実際に申請要領を開いてみると、専門用語の数々に圧倒され、「これは素人には無理かも」と尻込みしてしまう方も少なくありません。
私は銀行で10年間の融資審査業務を経験し、その後コンサルティング会社での5年間を含め、数多くの中小企業の資金調達をサポートしてきました。
その経験から言えるのは、補助金は決して「運」や「コネ」ではなく、「正しい理解」と「適切な準備」があれば十分に獲得可能だということです。
この記事では、補助金の基本から採択されるための審査ポイント、よくある失敗例まで、現場で培った知識を惜しみなくお伝えします。
銀行員時代から私が常に伝えてきた「キャッシュは企業の血液」という考えのもと、補助金という資金調達手段を最大限に活用するための道筋をご案内します。

🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
まずはここから!補助金のキホンと重要用語
補助金申請の第一関門は「専門用語の壁」です。
まずはこの壁を突破するため、基本的な知識と重要用語をしっかり押さえていきましょう。
補助金とは?目的と仕組みをサクッと理解
補助金とは、国や地方自治体が特定の政策目的を達成するために、民間企業などに対して交付する返済不要の資金援助です。重要なポイントは以下の3つです。
- 返済不要である(融資とは異なり、原則として返す必要はありません)
- 審査がある(条件を満たすだけでなく、計画の質や効果が問われます)
- 公益性が求められる(税金が財源であるため、社会的意義が重視されます)
例えば、国が中小企業のデジタル化を進めたい場合には「IT導入補助金」といった形で、システム導入費用の一部を補助することで、企業のデジタル投資を促進します。
つまり、企業にとっては資金調達手段ですが、国にとっては政策実現の手段なのです。
💡 ワンポイントアドバイス
補助金は「もらえるお金」ではなく「政策目的達成のための手段」と理解すると、審査での評価ポイントが見えてきます。自社の取り組みが国や自治体の政策とどう合致するかを意識しましょう。
「助成金」「給付金」との決定的な違いとは?
補助金と混同されやすい制度に「助成金」と「給付金」があります。
それぞれの違いを理解しておくことで、自社に合った支援策を選べるようになります。
| 区分 | 審査の特徴 | 主な所管 | 代表例 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 補助金 | 競争的審査 (事業計画の質が問われる) | 経済産業省 中小企業庁など | ものづくり補助金 持続化補助金 | 採択率は30~60%程度 申請手続きが比較的複雑 |
| 助成金 | 要件審査 (条件を満たせば原則支給) | 厚生労働省 労働局など | キャリアアップ助成金 両立支援助成金 | 要件を満たせば高確率で受給可 雇用関連が多い |
| 給付金 | 資格確認 (該当すれば給付) | 災害時:内閣府 その他:各省庁 | 持続化給付金 事業復興支援金 | 緊急支援や災害対応が多い 手続きは比較的簡素 |
 佐藤 真由美
佐藤 真由美最も重要な違いは「審査」の有無と性質です。
助成金は雇用関連が多く、定められた要件(例:若者の正社員化)を満たせば原則として支給されます。
一方、補助金は応募者同士が競争する形となり、事業計画の内容や実現可能性などが評価され、予算の範囲内で採択が決まります。
典型的なケースを挙げると、「従業員の残業時間を減らすための設備投資」の場合:
- 厚生労働省の助成金:就業規則の変更や実績の報告など所定の要件を満たせば支給
- 経済産業省の補助金:他社と比較して革新性や効果が高いと評価された計画のみ採択
⚠️ 注意事項
「補助金は応募したらもらえる」という誤解が散見されますが、実際は競争率の高いコンテストのようなものです。準備と戦略が重要です。
これだけは押さえたい!頻出・重要用語集
補助金の世界には独特の専門用語が多数存在します。申請前にこれらを理解しておくことで、公募要領を読み解く際の大きな助けになります。
申請前〜申請時の用語
🔍 公募要領:
補助金の「説明書」とも言える文書で、目的、対象者、補助率、対象経費、申請方法など全ての重要事項が記載されています。
80ページを超える大部なものもあり、隅々まで読み込むことが重要です。
🔍 補助対象者:
補助金を申請できる資格を持つ事業者の条件です。
業種、企業規模(従業員数・資本金)、創業からの年数などが指定されています。
🔍 補助対象経費:
補助金の対象となる経費区分です。
例えば「機械装置費」「外注費」「専門家経費」など。公募要領に必ず一覧が記載されており、これに当てはまらない支出は補助されません。
🔍 補助対象外経費:
明確に対象外と定められている経費です。
多くの補助金で「消費税」「振込手数料」「汎用性の高い備品(一般的なパソコンなど)」は対象外とされています。
🔍 補助率:
対象経費に対する補助金の支給割合です。
「補助率2/3」なら、100万円の経費に対して約67万円が補助されます(上限額がある場合は別)。
🔍 補助上限額:
1事業者あたりの補助金支給上限額です。
「補助率2/3、上限500万円」の場合、どんなに経費が大きくても500万円以上は支給されません。
🔍 GビズID:
経済産業省関連の補助金申請に必要な事業者用のデジタルIDです。
「gBizIDプライム」の取得には2〜3週間かかるため、申請前の早めの準備が必須です。
🔍 jGrants:
経済産業省などの補助金申請をオンラインで行うシステムです。
GビズIDでログインして使用します。
採択後の用語
🔍 採択:
審査の結果、補助金の交付対象として選ばれることです。
ただし、この段階ではまだ正式な交付決定ではありません。
🔍 交付申請:
採択後に行う、補助金を正式に申請する手続きです。
詳細な事業計画や経費計画を提出します。
🔍 交付決定:
交付申請を受けて行政機関が出す正式な決定通知です。
この日以降に発生した経費のみが補助対象となるため、非常に重要な日付です。
例えば、
- 5月15日:採択通知
- 6月1日:交付決定
- 5月20日に購入した設備 → 補助対象外(交付決定前の支出)
- 6月5日に購入した設備 → 補助対象(交付決定後の支出)
🔍 補助対象期間:
補助対象となる経費の発生が認められる期間です。
「交付決定日から事業完了日(最長で〇年〇月〇日)まで」と定められています。
🔍 実績報告:
補助事業完了後に提出する報告書です。
実施内容と支出した経費の証拠書類(請求書、領収書、振込明細など)を提出します。
🔍 確定検査:
実績報告を受けて行われる検査です。
書類審査だけでなく、現地調査が行われることもあります。
🔍 精算払い:
確定検査後に行われる補助金の支払いです。
多くの補助金は後払い(実績に基づく精算払い)方式のため、事業完了から補助金入金まで数ヶ月かかることも珍しくありません。
🔍 収益納付:
補助事業により収益が生じた場合、その一部を国に納付する制度です。
特に研究開発系の補助金で適用されることがあります。
補助金申請の最大の落とし穴は「交付決定日」の誤解です。採択されても、交付決定前の支出は対象になりません。また、補助金は基本的に「後払い」なので、事業実施のための資金(つなぎ資金)を事前に確保しておく必要があります。
どんな補助金がある?自社に合う制度を見つけるヒント
さて、基本用語を理解したところで、次は具体的にどんな補助金があるのかを見ていきましょう。
数ある補助金の中から自社に最適なものを選ぶためのヒントをお伝えします。
中小企業向け代表的な補助金4選+α
中小企業が活用できる代表的な補助金を紹介します。
これらは毎年のように実施され、採択実績も多い主要な制度です。
① ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
目的:中小企業の設備投資や革新的なサービス開発を支援
対象者:中小企業・小規模事業者
補助額・補助率:
- 通常枠:100万円〜1,250万円、補助率1/2(小規模事業者等は2/3)
- 特別枠(グリーン、デジタル等):最大2,000万円、補助率1/2〜2/3
特徴:
- 設備投資を伴う事業が対象
- 採択率は30%〜60%程度(近年は競争激化で低下傾向)
- 事業計画書の作成が比較的複雑で専門的



銀行員時代の経験からすると、設備投資の資金調達として非常に強力な武器となる補助金です。
例えば、3,000万円の工作機械を導入する場合、最大2,000万円までの補助を受けられれば、自己資金や借入の負担が大幅に軽減されます。
② 小規模事業者持続化補助金
目的:小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援
対象者:小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、製造業等は20人以下)
補助額・補助率:
- 通常枠:上限50万円、補助率2/3
- 特別枠(賃上げ、創業等):上限200万円、補助率2/3〜3/4
特徴:
- 比較的小規模な取り組みに適している
- 商工会議所等の支援を受けながら申請することが基本
- ホームページ制作、店舗改装、チラシ作成などに活用可能



この補助金は小規模事業者にとって取り組みやすく、「補助金デビュー」としても適しています。
例えば、新商品の販促チラシ作成10万円、展示会出展費用30万円、ウェブサイト制作50万円などの場合、合計90万円の2/3である60万円までが補助上限内で対象となります。
③ 事業再構築補助金
目的:新分野展開や業態転換など事業再構築に挑戦する企業を支援
対象者:中小企業、中堅企業等(一定の売上減少要件あり)
補助額・補助率:
- 通常枠:100万円〜8,000万円、補助率1/2〜2/3
- 大規模枠:最大1億円以上、補助率1/2
特徴:
- 大がかりな事業転換に対応
- 審査が厳格で、詳細な事業計画書が必要
- 採択率は20〜30%程度と比較的厳しい



コロナ禍で登場した大型補助金ですが、ポストコロナでも業態転換支援として継続されています。
例えば、飲食店が食品製造業に参入するケースや、製造業が新分野の製品開発に乗り出すケースなどが採択されています。
④ IT導入補助金
目的:中小企業のデジタル化・IT活用を促進
対象者:中小企業・小規模事業者
補助額・補助率:
- 通常枠:5万円〜350万円、補助率1/2
- デジタル化基盤導入枠:5万円〜350万円、補助率3/4〜2/3
特徴:
- IT製品・サービスの導入費用を補助
- 事前に登録されたITツール・ベンダーから選定する必要あり
- 比較的採択率が高い(60〜80%程度)



会計ソフト、顧客管理システム、ECサイト構築など、業務効率化やデジタル化に役立つITツール導入に活用できます。
例えば、クラウド型の販売管理システム導入(ライセンス料、導入支援費用等)で100万円かかる場合、最大50万円が補助されます。
2025年注目の新設補助金
2025年に向けて以下のような新設補助金も注目です。
- 中小企業成長加速化補助金:中堅企業への成長を目指す中小企業の設備投資を支援
- 特徴:売上100億円を目指す企業向け、大型投資に対応
- 新事業進出補助金:事業再構築補助金の後継となる新しい枠組み
- 特徴:賃上げ要件等あり、新分野展開を支援
- 省力化投資補助金:人手不足対策のための設備投資を支援
- 特徴:労働生産性向上に資する投資が対象
💡 ワンポイントアドバイス
補助金は「情報戦」です。最新の政策動向や予算情報をチェックし、公募開始前から情報収集と準備を始めることが重要です。中小企業庁のメールマガジンやミラサポplusへの登録がおすすめです。
自社に最適な補助金を選ぶ3つの視点
数ある補助金の中から自社に合った制度を選ぶには、以下の3つの視点が役立ちます。
視点①:事業目的の合致度
補助金はそれぞれ異なる政策目的を持っています。
自社の計画と補助金の目的が合致しているかを見極めましょう。
- 設備投資が主目的:ものづくり補助金、省力化投資補助金など
- 販路開拓が主目的:持続化補助金など
- 業態転換・新分野展開:事業再構築補助金、新事業進出補助金など
- IT化・デジタル化:IT導入補助金など
例えば、「従来よりも生産性の高い最新機械を導入したい」というニーズならものづくり補助金、「新商品のPRや販売チャネルを増やしたい」なら持続化補助金が適しています。
視点②:企業規模・業種の適合性
各補助金には対象となる企業規模や業種に条件があります。
- 小規模事業者(商業・サービス業5人以下、製造業20人以下):持続化補助金が最適
- 中規模の中小企業(製造業300人以下等):ものづくり補助金、事業再構築補助金など
- 特定業種向け:農林水産業、医療福祉、観光業など業種別の専門補助金も多数



私がコンサルタント時代に支援した例では、従業員3名の小さな町工場が「持続化補助金」を活用して展示会出展を実現し、大手メーカーとの取引につながったケースがあります。
企業規模に合った補助金を選ぶことで、採択確率も高まります。
視点③:申請難易度と自社リソース
補助金によって申請の難易度、必要な準備期間、事務負担は大きく異なります。
- 難易度・低:持続化補助金、IT導入補助金など
- 特徴:申請書類が比較的シンプル、専門家サポートあり
- 難易度・中:ものづくり補助金など
- 特徴:ある程度詳細な事業計画書が必要
- 難易度・高:事業再構築補助金など
- 特徴:詳細な事業計画、財務計画、市場分析が必要
自社のリソース(人員、時間、専門知識)と補助金の難易度を照らし合わせ、無理なく取り組める制度を選びましょう。
例えば、総務担当者がいない小規模事業者が初めて補助金に挑戦する場合は、商工会議所のサポートを受けられる持続化補助金から始めるのが現実的です。
補助金選びで最も大切なのは「目的の明確化」です。「補助金をもらうため」の計画ではなく、「自社の成長のために必要な計画」があり、それに合った補助金を選ぶという順序を守りましょう。
メリットだけじゃない!補助金活用の注意点とデメリット
補助金は有効な資金調達手段ですが、メリットだけでなくデメリットも理解した上で活用すべきです。
ここでは両面を冷静に分析します。
補助金活用の主なメリット
- 資金調達コストの削減:返済不要の資金を調達できるため、投資効率が高まります。
例:1,000万円の設備を導入する際、補助率1/2なら実質500万円の負担 - 事業計画の精緻化:申請過程で事業計画を練り上げることで経営戦略が明確になります。
私の支援先でも、補助金申請を通じて初めて5年先の経営ビジョンを明文化できた企業が多くあります - 信用力の向上:補助金採択実績は、融資審査などでもプラス評価されることがあります。
銀行員時代の経験では、「国の審査を通った事業計画」として信頼度が高まる効果がありました
補助金活用の主な注意点・デメリット
- 資金繰り負担(後払い方式):多くの補助金は事業完了後の精算払いです。
例:1,000万円の事業で補助率1/2の場合、いったん1,000万円全額を支払い、数ヶ月後に500万円が補助金として入金されます。
→私の持論「キャッシュは企業の血液」の観点からも、この「つなぎ資金」の準備は極めて重要です。 - 手続きの煩雑さと時間的コスト:申請から精算まで多くの書類作成や手続きが必要です。
→ある製造業の社長は「補助金の手続きのために延べ100時間以上を費やした」と話していました。 - 不採択リスク:審査に通らない可能性があり、準備に費やした時間が無駄になることもあります。
→採択率は補助金により30%〜80%と幅があります。 - 計画変更の制約:交付決定後の計画変更には厳格な手続きが必要です。
例:導入予定の機械を別メーカーの同等品に変更するだけでも承認手続きが必要。 - 補助金依存のリスク:補助金前提の経営は、制度がなくなった時に立ち行かなくなる恐れがあります。
→本来は「補助金があるから取り組む」ではなく「取り組むべきことに補助金を活用する」という姿勢が健全です。
⚠️ 注意事項
銀行員時代に見てきた失敗例の筆頭は「つなぎ資金の準備不足」です。補助金は後払いが基本なので、事業実施に必要な全額を一時的に準備する必要があります。自己資金や融資枠を事前に確保しておきましょう。
補助金活用を検討する際は、これらのメリット・デメリットを冷静に比較検討し、自社の経営戦略や資金繰り計画にどう影響するかを総合的に判断することが大切です。
採択される計画書はここが違う!審査を突破する6つのポイント
ここからは、補助金申請の最大の壁である「審査」をクリアするための具体的なポイントを解説します。
採択率が低下傾向にある昨今、計画書の質は採否を分ける決定的な要素となっています。
審査員は何を見ている?評価される事業計画の共通点
まず審査のメカニズムについて理解しておきましょう。
審査員は数百、時には数千もの申請書類を限られた期間で評価します。そのため、一件あたりに費やす時間は非常に限られています。
審査員の目に留まり、高評価を得る計画書に共通する要素は以下の通りです。
- 見やすさ・読みやすさ:整理された構成、図表活用、要点の強調
- 具体性と論理性:抽象的な表現ではなく、具体的な数値や事実に基づく説明
- 一貫性:目的から手段、期待効果までの筋道が通っている
- 誠実さ:実現可能性の高さ、現実的な計画
- 熱意と覚悟:取り組む意欲や覚悟が伝わってくる内容
コンサルタント時代の経験では、同じ内容でも「書き方」によって評価が大きく変わることを数多く目にしてきました。
特に、煩雑に書かれた計画書と、要点が整理された計画書では、後者の方が採択率が明らかに高いのです。
📝 ポイントまとめ
審査員の立場に立って考えると、「この人に税金を使った支援をしたい」と思わせる計画書が評価されます。そのために、以下7つのポイントを押さえましょう。
ポイント①:補助金の「目的」と事業計画の一致を明確に示す
補助金はそれぞれ固有の政策目的を持っています。
申請計画がその目的にどう合致するかを明確に示すことが最重要です。
具体的には、
- 公募要領の「1. 事業の目的」部分を熟読する
- その目的に関連する自社の取り組みを洗い出す
- 計画書の冒頭部分で両者の関連性を明記する
例えば、「ものづくり補助金」の目的は「中小企業の革新的な製品・サービス開発や生産性向上の取り組みを支援すること」です。この場合:
× 悪い例:「当社は設備の老朽化に伴い、機械を更新したいと考えています」
○ 良い例:「当社は、本事業を通じて最新の自動化設備を導入し、生産性を現状比30%向上させることで、国内製造業の競争力強化という政策目的に貢献します」



銀行の融資審査でも同様ですが、「なぜその資金が必要か」「どのような効果があるか」を明確に示せる事業者は高く評価されます。
ポイント②:具体性と実現可能性を「数値」で示す
審査員を納得させるために、計画の具体性と実現可能性を数値で示すことが効果的です。
具体的には、
- 現状の課題を数値で示す
例:「現在の生産能力は月産1,000個、稼働率85%で生産限界に近づいている」 - 取り組み内容を具体的に記述する
例:「A社製自動梱包機(型番B-123)を導入し、梱包工程の自動化を実現する」 - 期待効果を数値で提示する
例:「梱包工程の人員を3名から1名に削減でき、人件費を年間600万円削減」 - スケジュールを明確に示す
例:「交付決定後1ヶ月以内に発注、3ヶ月後に設置、4ヶ月後から本格稼働」
例えば、ある製造業の採択された計画書では、
【現状】手作業での検査工程に4名が従事、月間不良率2.5%、人件費年間1,680万円
【計画】画像検査装置(1,200万円)を導入し、検査を自動化
【効果】検査人員を4名→1名に削減(年間1,260万円の人件費削減)、不良率を2.5%→0.5%に改善(年間約300万円の損失削減)
【スケジュール】交付決定後2週間で発注、2ヶ月後に納品・設置、3ヶ月目から本格運用このように具体的な数値を盛り込むことで、「絵に描いた餅」ではなく、実現可能な計画であることを示します。
ポイント③:自社の強みと事業の「独自性・革新性」をアピール
補助金は限られた予算で最大の効果を生み出したいという意図があります。
そのため、「ありきたりの取り組み」より「独自性や革新性のある取り組み」が評価されます。
具体的には、
- 自社の強み・独自性を明確にする
例:「当社は〇〇分野で20年の実績があり、特許技術を5件保有」 - 競合や従来手法との差別化ポイントを示す
例:「従来の方式と比較して消費電力を40%削減できる独自方式を採用」 - 新規性・革新性を具体的に説明する
例:「国内初となる〇〇技術の実用化」「地域内では唯一の〇〇サービス」
私がコンサルティングした成功事例では、単なる「設備更新」ではなく「独自の改良を加えた設備導入」としてアピールすることで採択率が向上しました。
💡 ワンポイントアドバイス
「革新性」は必ずしも「世界初の技術」である必要はありません。「自社にとっての革新」「地域内での革新」など、規模感を考慮した革新性で構いません。大切なのは、その取り組みにより従来と比べて何がどう変わるのかを具体的に示すことです。
ポイント④:「社会的意義・波及効果」を忘れずに盛り込む
補助金の財源は税金です。そのため、単に自社の利益だけでなく、社会や地域にどのようなプラスの影響をもたらすかを示すことが重要です。
具体的には以下のような波及効果を盛り込みましょう。
- 雇用への貢献
例:「本事業により新たに3名の正社員を雇用」「地元の若者の雇用機会創出」 - 地域経済への貢献
例:「地元の協力企業5社との取引拡大」「年間〇〇億円の経済波及効果」 - 社会課題解決への貢献
例:「高齢者の生活支援」「環境負荷の低減」「地域の伝統技術の継承」 - 業界への波及効果
例:「同業他社への技術普及」「業界標準となるモデルケースの創出」
銀行での融資審査経験からも言えますが、「自社だけが儲かる」計画より「社会全体に良い影響がある」計画の方が評価されます。これは補助金審査でも同様です。
ポイント⑤:加点項目を漏れなくチェックし、最大限活用する!
多くの補助金では、特定の取り組みや認定を受けている場合に審査で加点される「加点項目」があります。
これらを最大限活用することが採択への近道です。
最新の分析によれば、「加点数が多い申請ほど採択率が高い」という明確な相関関係が見られます。
例えば、あるものづくり補助金では、
- 加点0個の場合:採択率22%
- 加点2個の場合:採択率38%
- 加点4個の場合:採択率63%
というデータがあります。
代表的な加点項目例:
- 賃上げ計画(多くの補助金で加点対象)
- 経営革新計画など各種認定取得
- 事業継続力強化計画の認定
- 過去の補助金で一定の成果を出している
- 地域未来牽引企業、地域経済牽引事業計画の承認
- パートナーシップ構築宣言の作成
これらは事前に準備可能なものが多いので、公募開始前から取り組んでおくことをお勧めします。
例えば、経営革新計画の認定は都道府県で随時受け付けており、取得に1〜3ヶ月程度かかります。
「うちは小さな会社だから加点は無理だろう」と諦める事業者がいますが、規模に関係なく取得可能な認定も多くあります。むしろ小規模事業者こそ、加点で差をつけることが重要です。
ポイント⑥:説得力のある「財務状況」と無理のない「資金計画」
補助事業を確実に遂行できる財務基盤があるかどうかも重要な審査ポイントです。
銀行員の視点から特に強調したいのは以下の2点です。
1. 健全な財務状況を示す
決算書から見て明らかに経営が危ういと判断される場合、補助事業の継続性に疑義が生じます。
基本的な財務指標(自己資本比率、借入金月商倍率など)が著しく悪い場合は、その改善計画も含めて説明することが重要です。
例えば、「現在は自己資本比率が10%と低いが、本事業により収益力が向上し、3年後には20%に改善する計画」といった具体的な見通しを示します。
2. 現実的な資金調達計画を提示
補助金は後払いが原則のため、事業実施に必要な全額を一時的に調達する計画が必須です。
例:補助対象事業費1,000万円、補助率1/2の場合
- 必要資金:1,000万円(全額を一時的に支払う必要あり)
- 資金調達計画:自己資金300万円+銀行融資700万円
- 補助金入金(約500万円)後の返済計画:融資700万円のうち500万円を一括返済
このように、補助金入金までのつなぎ資金をどう確保するかを明確に示すことが重要です。
銀行融資を予定している場合は、可能であれば「融資の事前相談済み」といった裏付けがあると説得力が増します。
🎯 実践ステップ
元銀行員として強調したいのは、「補助金が入るから大丈夫」という楽観的な考えは危険だということです。補助金入金までの期間(通常6ヶ月〜1年以上)、資金繰りが回るかどうかを綿密に計画しましょう。キャッシュフローシミュレーションを作成し、最悪のケース(入金が3ヶ月遅れるなど)も想定することをお勧めします。
申請から受給までの流れと準備すべきこと
ここからは、補助金申請から受給までの具体的なプロセスと、各段階で準備すべきことを解説します。
全体の流れを把握し、計画的に準備を進めることが成功の鍵です。
【完全ガイド】補助金申請の10ステップ(情報収集~事後報告まで)
補助金申請から受給までのプロセスを10のステップに分けて解説します。
ステップ1:情報収集と制度理解
やるべきこと:
- 自社に合った補助金を探す
- 公募要領を入手し隅々まで読み込む
- 公募説明会があれば参加する
期間目安:公募開始の1〜3ヶ月前から
注意点:
補助金情報は中小企業庁、各省庁、自治体のウェブサイト、ミラサポplusなどで収集できます。また、商工会議所や地域の支援機関も情報源として活用しましょう。
実践例:
ある製造業では、毎月1回「補助金チェックの日」を設け、最新情報を収集する習慣をつけていました。その結果、公募開始と同時に準備を始めることができ、高い確率で採択を獲得しています。
ステップ2:GビズIDの取得(電子申請の場合)
やるべきこと:
- gBizIDプライムの取得手続きを行う
- 必要書類(印鑑証明書など)を準備する
期間目安:2〜3週間(余裕を持って1ヶ月前までに)
注意点:
GビズIDの取得には時間がかかります。公募開始後に慌てて申請しても間に合わないことがあるため、あらかじめ取得しておきましょう。
ステップ3:事業計画の策定
やるべきこと:
- 自社の現状と課題を整理
- 具体的な事業計画を練る
- 数値目標を設定
- 実施スケジュールを作成
期間目安:2週間〜1ヶ月
注意点:
この段階で前述の「7つのポイント」を意識して計画を練ります。特に数値目標は具体的かつ現実的なものにしましょう。
ステップ4:必要書類の準備
やるべきこと:
- 申請書類一式を準備
- 添付書類(登記簿、決算書等)を収集
- 見積書の取得
期間目安:2週間程度
注意点:
見積書は複数社から取得するケースが多いです。また、登記簿謄本や納税証明書など取得に時間がかかる書類もあるため、早めに準備しましょう。
ステップ5:申請書の提出
やるべきこと:
- 申請書類のダブルチェック
- オンライン申請または郵送での提出
期間目安:提出期限の1週間前までに
注意点:
締切直前はシステムが混雑したり、不測の事態が起きる可能性があります。最低でも締切の3日前までには提出を完了させることをお勧めします。
実践例:
あるIT企業は、jGrants(電子申請システム)で申請する際、締切日当日にアクセスが集中してシステムに繋がらず、申請できませんでした。この教訓から、以降は必ず締切の1週間前に申請を完了するよう社内ルール化しています。
ステップ6:審査・採択
やるべきこと:
- 審査結果を待つ
- 必要に応じて事務局からの問い合わせに対応
期間目安:1〜3ヶ月
注意点:
審査中は事業着手せず、採択を待ちましょう。この段階では経費を発生させても補助対象にはなりません。
ステップ7:交付申請・交付決定
やるべきこと:
- 採択通知を受けたら交付申請書を提出
- 交付決定通知を受け取る
期間目安:採択から2週間〜1ヶ月
注意点:
ここでの最大の注意点は、「採択≠交付決定」ということです。交付決定日以降に発生した経費のみが補助対象となるため、決定通知を受けるまで事業着手を待つことが原則です。
実践例:
ある小売業は採択通知を受け取った後、「もう大丈夫だろう」と考えて店舗改装工事を発注。しかし、実際の交付決定は3週間後でした。結果、その間に支払った工事代金約200万円が補助対象外となってしまいました。
ステップ8:事業実施
やるべきこと:
- 計画に沿って事業を実施
- 経費の証拠書類を適切に保管
- 経費は補助対象期間内に支払い完了
期間目安:数ヶ月〜1年(補助金により異なる)
注意点:
事業実施中は経費管理が極めて重要です。見積書、発注書、納品書、請求書、領収書(振込明細)などの証拠書類を全て保管しましょう。また、計画に大きな変更がある場合は、必ず事前に事務局に相談し、計画変更の手続きを行う必要があります。
ステップ9:実績報告・確定検査
やるべきこと:
- 事業完了後、実績報告書を提出
- 証拠書類を整理して添付
- 確定検査(書面または現地)に対応
期間目安:事業完了後30日以内または指定期日まで
注意点:
実績報告書は非常に重要です。支出内容が計画と一致しているか、証拠書類は漏れなくあるか、経費は全て補助対象期間内に支払われているかなど、細心の注意を払って準備します。確定検査では実際に購入した設備等の現物確認が行われることもあります。
ステップ10:補助金受給・事後報告
やるべきこと:
- 補助金の請求手続き
- 入金確認
- 事後報告(必要な場合)
期間目安:実績報告から1〜3ヶ月
注意点:
補助金受給後も、一定期間は事業化状況や収益状況などの報告が必要なケースがあります。また、設備などを処分する場合は、一定期間(通常3〜5年)は財産処分制限があることも忘れないでください。



申請から入金までの平均期間は約10〜14ヶ月です。
特に大型補助金ほど時間がかかる傾向があります。この間のキャッシュフロー計画は特に重要です。
これで安心!必要書類チェックリスト
補助金申請で必要な書類は種類によって異なりますが、一般的に以下のものが求められます。
申請前にこのチェックリストで漏れがないか確認しましょう。
基本書類(ほぼ全ての補助金で必要)
□ 補助金申請書(指定様式)
□ 事業計画書(指定様式)
□ 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
□ 決算書(直近1〜3期分 ※設立間もない場合は創業計画書等)
□ 納税証明書(税務署発行のもの、通常「その3の3」)
□ 見積書(原則複数社からの取得が必要)
追加書類(補助金により必要な場合あり)
□ 経営革新計画承認書(加点対象となる場合)
□ 認定支援機関確認書(事業再構築補助金等で必要)
□ 雇用契約書・賃金台帳(雇用関連の取り組みの場合)
□ 設備のカタログ・仕様書(設備投資の場合)
□ 工事図面・平面図(店舗改装等の場合)
□ 既存設備の写真(設備更新の場合)
□ 補助事業の具体的な説明資料(必要に応じて)
電子申請の場合の追加事項
□ GビズIDの取得(プライム)
□ jGrants等の申請システムへの登録
□ 提出書類の電子化(PDF等)
書類作成のコツ:
- 最新の様式を使用する:公募のたびに様式が若干変更されることがあります。必ず最新の様式を使いましょう。
- 記入漏れ・押印漏れをチェック:些細な書類不備でも審査対象外となる可能性があります。
- 書類はクリアファイルなどで整理:大量の書類を提出する場合は、インデックスをつけるなど整理して提出すると好印象です。
- 提出前に第三者チェック:可能であれば、商工会議所の経営指導員や専門家に確認してもらうと安心です。
⚠️ 注意事項
銀行での与信審査経験からも言えますが、書類の不備や不足は「経営の不備」と同様に見られがちです。「細部にも気を配れる経営者か」という点も間接的に評価されていると考えましょう。
意外と知らない?補助対象経費のルールと注意点
補助金で最も混乱しやすいのが「何が補助対象経費になるのか」という点です。
ここでは主な補助対象経費とよくある勘違いについて解説します。
主な補助対象経費(一般的な例)
- 機械装置・システム構築費:生産設備、検査装置、専用ソフトウェア等
- 技術導入費:専用ソフトウェア、特許権等の導入費
- 専門家経費:コンサルタント、専門家への相談費用
- 運搬費:設備等の運搬費用
- クラウドサービス利用費:クラウドサービスの利用料(一定期間)
- 外注費:一部の作業を外部に委託する費用
- 広報費:PRのための広告費用、展示会出展費等
- 販売促進費:販路開拓のためのサンプル作成費等
よくある補助対象外経費
- 消費税:ほぼ全ての補助金で対象外
- 汎用性の高い備品:一般的なパソコン、プリンター、スマートフォン等
- 中古品(一部例外あり)
- 人件費(一部例外あり)
- 使用実績のない経費:契約したが未使用のサービス等
- 公募前に発注した経費
- 交付決定前に発注・購入した経費
- 補助対象期間外に支払った経費
経費計上でよくある勘違い・失敗例
⚠️ 交付決定前の発注
- NG例:採択通知を受けたら、交付決定を待たずに機械を発注してしまった
- 正しい対応:交付決定通知を受けてから発注する
⚠️ 支払方法の誤り
- NG例:個人のクレジットカードで支払った、現金払いで領収書をもらい忘れた
- 正しい対応:原則として法人名義の銀行振込で支払い、振込明細を保管する
⚠️ 経費計上漏れ
- NG例:事業計画書に記載していなかった経費を後から計上しようとした
- 正しい対応:事業計画時点で必要経費を漏れなく記載する
⚠️ 補助対象外経費の混同
- NG例:汎用的な事務用パソコンを「IT化のための設備」として申請
- 正しい対応:専用用途であることを明確にできる設備を選定する
経費計上で迷った場合は、必ず事前に事務局に確認することをお勧めします。事後的な判断では対象外となるリスクがあります。また、見積書取得の段階で補助対象となる仕様かどうかを確認し、必要に応じて購入予定機器の詳細仕様やカタログを申請書に添付するとより安全です。
知らないと損!補助金申請でよくある失敗例と回避策
最後に、多くの中小企業が陥りがちな失敗例と、その回避策を紹介します。
これらを知っておくことで、補助金申請の成功確率が大きく高まります。
申請準備段階での落とし穴(締切、要件誤認、書類不備)
失敗例①:締切への対応遅れ
ケーススタディ:
A社は補助金公募開始の2週間後に情報を知り、申請準備を始めました。しかし、GビズIDの取得に3週間、金融機関からの融資証明書の取得に1週間かかることが判明。結局、書類を揃えた時には締切を過ぎていました。
回避策:
- 補助金情報を定期的にチェックする習慣をつける
- 公募開始と同時に準備を始める
- 締切の最低2週間前までに申請完了を目指す
失敗例②:応募要件の誤認
ケーススタディ:
B社は「小規模事業者持続化補助金」に申請しようとしましたが、従業員数が要件を超えていることに気づかず、準備を進めていました。申請直前に商工会議所で指摘を受け、別の補助金に切り替える必要が生じ、準備時間を無駄にしました。
回避策:
- 公募要領の「対象者要件」を最初に確認する
- 不明点は早めに事務局や支援機関に確認する
- 複数の補助金を並行して検討しておく
失敗例③:書類不備・記入ミス
ケーススタディ:
C社は申請書を提出したものの、代表者印の押印漏れがあり、審査対象外となりました。また、決算書の添付が1期分のみだったのに対し、要件では3期分必要でした。
回避策:
- 提出前チェックリストを作成する
- 可能であれば第三者(専門家等)にチェックしてもらう
- 提出書類一式のコピーを保管する
🧠 考えてみよう
銀行員時代の経験則ですが、融資でも補助金でも「準備は早すぎることはない」と言えます。公募開始前から情報収集と計画策定を始め、公募開始と同時に申請できる状態を目指すのが理想的です。
採択後に注意すべきこと(交付決定前の支出、経費管理ミス)
失敗例④:交付決定前の発注・支出
ケーススタディ:
D社は採択通知を受け取った喜びから、すぐに設備発注を行いました。しかし、交付決定は3週間後。結果、約300万円の設備投資が補助対象外となってしまいました。
回避策:
- 「採択≠交付決定」を理解する
- 必ず交付決定通知を受け取ってから発注・契約する
- スケジュールに余裕を持たせる
失敗例⑤:経費管理・証憑保存のミス
ケーススタディ:
E社は設備導入後、請求書は保管していましたが、発注書と納品書を紛失。また、一部経費を代表者の個人口座から支払っていたため、法人の支出と認められず、補助金額が減額されました。
回避策:
- 経費関連書類は全て専用ファイルで保管する
- 支払いは必ず法人名義の銀行振込で行う
- 経費台帳を作成し、漏れなく記録する
失敗例⑥:計画変更手続きの不備
ケーススタディ:
F社は事業実施中に、当初予定していた設備よりも性能の良い新モデルが発売されたため、計画を変更。しかし、事前の変更手続きを行わなかったため、その設備費用が補助対象外となりました。
回避策:
- 計画に変更が生じた場合は、必ず事前に事務局に相談する
- 軽微な変更でも書面で報告する
- 変更内容と理由を具体的に説明できるようにしておく
💯 成功事例
あるIT企業では、採択後に「補助金管理専任者」を指名し、発注から支払いまでの全プロセスをチェックする体制を整えました。その結果、書類の不備や手続きミスがなくなり、満額の補助金を受け取ることができました。
意外と見落としがち?補助金受給後の税金と報告義務
失敗例⑦:税金対策の不備
ケーススタディ:
G社は1,000万円の補助金を受け取りましたが、税務上の処理について考慮していなかったため、翌年度に約300万円の法人税等の追加負担が発生。資金繰りが一時的に悪化しました。
回避策:
- 補助金は原則として益金(課税対象)になることを理解する
- 圧縮記帳などの税務上の特例措置を検討する
- 税理士に事前に相談する
圧縮記帳の効果(シミュレーション):
設備投資1,000万円、補助金500万円のケース
- 圧縮記帳なし:補助金500万円が課税対象→約150万円の税負担
- 圧縮記帳あり:設備の帳簿価額を500万円減額→減価償却費が減少するが、一時的な税負担を繰り延べ可能
失敗例⑧:事後報告・財産処分制限の違反
ケーススタディ:
H社は補助金で購入した設備を3年後に売却しましたが、財産処分制限期間(5年)内だったため、補助金の一部返還を求められました。また、事業化状況報告を怠ったため、次回の補助金申請で減点対象となりました。
回避策:
- 財産処分制限期間(通常3〜5年)を確認する
- 事後報告義務を確認し、期限を管理する
- 設備等の処分を検討する場合は事前に財産処分の承認申請を行う



補助金受給後の税務処理は複雑なため、必ず税理士に相談することをお勧めします。
圧縮記帳の適用可否や手続き方法は補助金の種類や設備の種類によって異なります。
また、財産処分制限については交付決定通知書に記載されている内容を確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
ここでは、補助金申請に関してよく寄せられる質問に答えます。初めての方でもよくある疑問点をカバーしていますので、参考にしてください。
Q: 補助金申請は素人でもできますか?専門家に頼むべき?
A: 補助金の種類や規模によります。小規模なものなら自力申請も可能ですが、大型補助金や初めての場合は専門家(行政書士、中小企業診断士、コンサルタント等)の活用も有効です。専門家費用はかかりますが、採択率向上や手間削減のメリットがあります。まずは無料相談などを利用してみましょう。
自力申請に適した補助金としては、「持続化補助金」などがあります。商工会議所のサポートを受けられるため、初心者でも比較的取り組みやすいでしょう。一方、「事業再構築補助金」のような大型案件は専門的な知識が必要なケースが多いです。
Q: 申請に費用はかかりますか?
A: 申請自体に手数料はかかりませんが、書類準備(証明書取得費など)や、専門家に依頼する場合の報酬が発生します。また、採択された場合、補助金は後払いが原則なので、事業実行のための自己資金(または融資)が一時的に必要になります。
専門家への報酬相場は、補助金の種類や金額によって異なりますが、一般的には、
- 小規模な補助金(~100万円程度):5〜10万円程度
- 中規模な補助金(~500万円程度):10〜30万円程度
- 大規模な補助金(500万円以上):30〜50万円程度、または成功報酬(補助金額の5〜10%)
実績のある専門家に依頼することで採択率が高まる傾向がありますので、費用対効果を考慮して判断するとよいでしょう。
Q: 採択されなかったらどうすればいいですか?
A: 不採択の理由は開示されないことが多いですが、諦めずに原因を分析し、事業計画を改善して次回の公募に再チャレンジすることが重要です。審査員からのフィードバックが得られる場合もあります。また、別の補助金を探すという選択肢もあります。
コンサルタント時代の経験では、1回目で不採択だった企業が計画を見直して2回目で採択されるケースも珍しくありません。不採択の主な原因としては、
- 計画の具体性・実現可能性が低い
- 補助金の目的との整合性が不十分
- 社会的意義・波及効果の説明が弱い
- 加点項目の活用が不十分
などが考えられます。これらの点を見直し、より具体的かつ説得力のある計画に練り上げることで、次回の採択確率を高めることができます。
Q: 補助金は本当に返済不要ですか?
A: はい、原則として返済は不要です。ただし、不正受給が発覚した場合や、補助事業の目的外使用、財産処分制限期間内の無断処分など、ルール違反があった場合は返還を求められます。また、事業で大きな収益が出た場合に一部返納(収益納付)が必要なケースもあります。
収益納付は主に研究開発系の補助金で見られる制度で、例えば補助事業で開発した製品の販売により大きな利益が出た場合、その一部を国に納付するというものです。ただし、多くの設備投資系・販路開拓系の補助金では、通常の事業収益に対する収益納付は求められません。
Q: 創業したばかりでも申請できますか?
A: 補助金によります。創業間もない企業を対象とした補助金もありますし、一部の補助金では創業年数や決算実績が要件となる場合もあります。公募要領で対象者要件を確認することが重要です。創業融資など他の資金調達手段と組み合わせることも検討しましょう。
創業者向けの補助金としては、
- 「創業補助金」(自治体によって実施)
- 「小規模事業者持続化補助金」の創業枠
- 「IT導入補助金」(創業間もない企業も申請可)
などがあります。また、創業計画が具体的であれば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」との併用も効果的な資金調達戦略となります。
補助金は「手段」であって「目的」ではありません。自社の成長戦略に合致する場合に活用するものであり、「補助金ありき」で事業を考えるのは逆転の発想です。まずは自社のあるべき姿を描き、その実現に必要な取り組みを検討し、それに合った補助金を探すというアプローチが望ましいでしょう。
まとめ
この記事では、補助金の基礎知識から審査ポイント、申請手続き、注意点まで幅広く解説してきました。
最後に重要なポイントをまとめます。
補助金は中小企業の成長を後押しする強力な資金調達手段です。
返済不要という大きなメリットがある一方で、競争的審査があり、事業完了後の精算払いという特徴を持ちます。
成功のカギは以下の3点に集約されます。
- 正しい理解と計画的な準備:
補助金の仕組みを理解し、公募前から情報収集と準備を進めることが重要です。特に「採択≠交付決定」という点や、資金繰り計画の重要性は忘れないでください。 - 政策目的との整合性を意識した事業計画:
補助金は税金を原資とした政策実現の手段です。自社の取り組みが社会や地域にどう貢献するかを明確に示すことで、採択率が高まります。 - 細部まで注意を払った経費管理:
交付決定後の経費管理、証憑保存は非常に重要です。些細なミスが補助金減額につながることもあるため、細心の注意を払いましょう。
「キャッシュは企業の血液」という観点からも、補助金は資金繰りを改善し、成長投資を加速する貴重な機会です。
しかし、後払い方式という特性上、つなぎ資金の確保が不可欠です。
銀行融資との組み合わせなど、総合的な資金調達戦略を検討することをお勧めします。



今日から始められるアクションとしては、まず自社にとって関心のある補助金の公募情報をチェックしてみましょう。
中小企業庁のウェブサイトやミラサポplusなどで最新情報が得られます。
また、地元の商工会議所や金融機関に相談するのも有効な一歩です。
補助金申請は決して難しいものではありません。
正しい知識と適切な準備があれば、皆さんの企業も必ず補助金を活用した成長を実現できるはずです。
この記事が皆さんの成功の一助となれば幸いです。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消