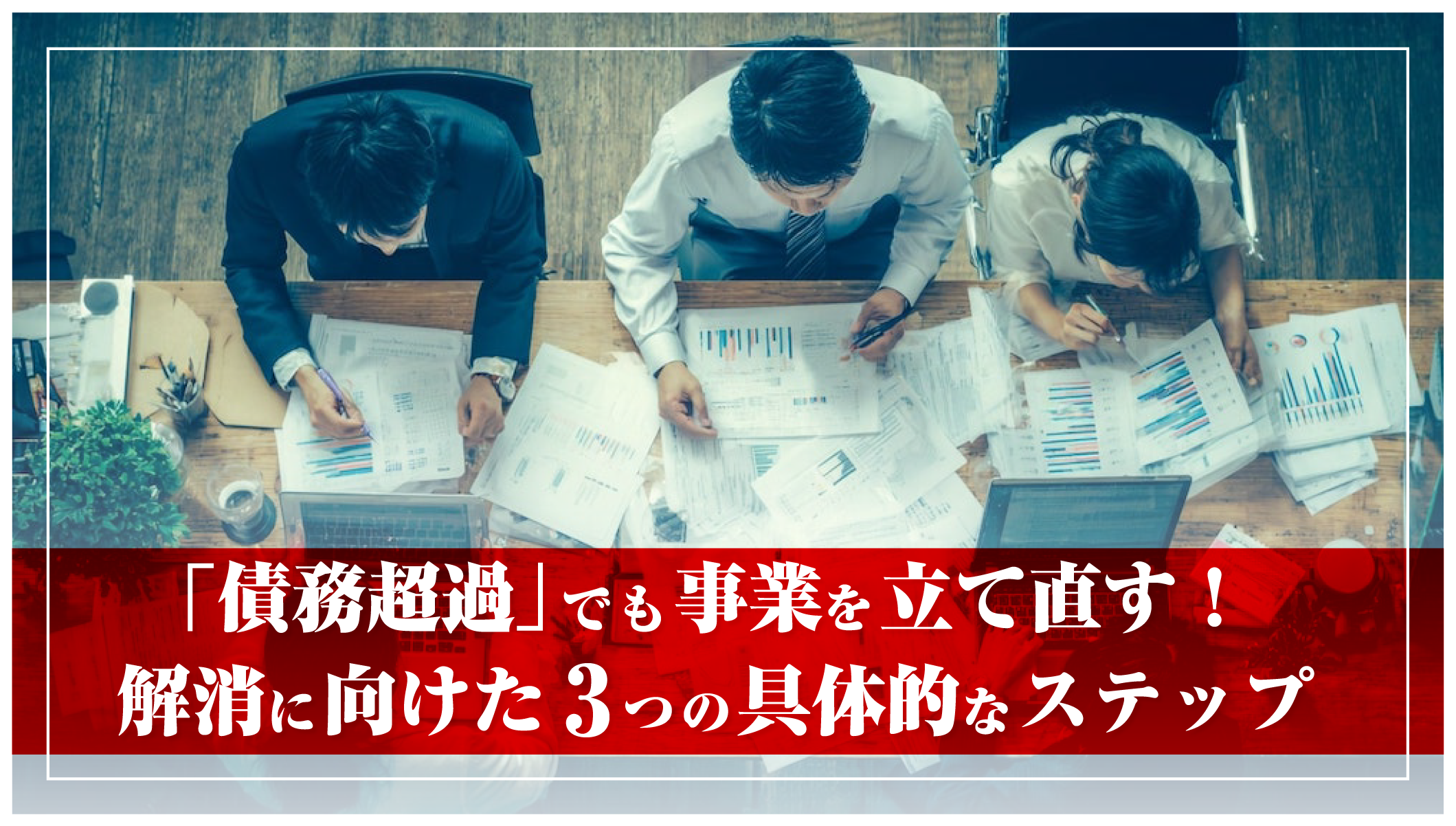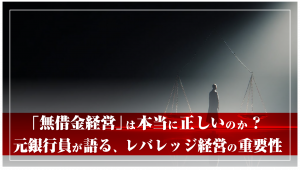「自社の貸借対照表を見て、純資産の部がマイナスに…」
経営者であれば、誰もが背筋の凍る瞬間ではないでしょうか。会議室の重い空気、数字が突きつける現実に、冷たい汗が背中を伝う感覚は私もよく知っています。
私は元銀行員として融資審査を、経営コンサルタントとして数々の企業の財務改善を支援してきました。その経験から断言します。
 佐藤 真由美
佐藤 真由美債務超過は、倒産の宣告ではありません。むしろ、正しい手順で対処すれば「より筋肉質な経営体制」へと生まれ変わる絶好の転機です。
もう一人で悩むのは終わりにしましょう。債務超過を乗り越えるための「3つの実践ステップ」を、元銀行員の視点から徹底解説します。
【この記事の結論】債務超過から脱却する3つのステップ
| 疑問・課題 | 結論・解決策 |
|---|---|
| 債務超過とは? | 会社の総資産を使っても借金を返済しきれない状態(資産 < 負債)。放置すると融資停止や倒産のリスクが急増します。 |
| どうすれば解消できる? | 「3つの具体的ステップ」 を実行します。①負債を減らす、②資本を増やす、③利益を出す体質に変える、ことが重要です。 |
| まず何から始めるべき? | 「経営改善計画書」の作成です。現状分析と具体的な再建プランを明記し、金融機関からの信頼を得ることが再建の第一歩となります。 |
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
そもそも債務超過とは?赤字との違いを貸借対照表で理解する
債務超過は「資産<負債」の状態
会社の全財産をかき集めても、借金を返しきれない状態。
それが債務超過です。
貸借対照表(バランスシート)で見てみましょう。
【正常な状態】 【債務超過の状態】
資産 100 │ 負債 80 資産 100 │ 負債 120
│ 純資産 20 │ 純資産 -20
─────┼───── ─────┼─────
合計 100 │ 合計 100 合計 100 │ 合計 100左側の「資産」は会社が持つプラスの財産。
右側の「負債」は返すべき借金。
そして「純資産」は、いわば会社の体力そのものです。
債務超過とは、この体力ゲージがゼロを通り越し、マイナスに振り切れてしまっている状態です。
「赤字」との決定的な違いは時間軸
- 赤字:特定の期間(例:1年間)の成績です。損益計算書(PL)に記載され、「フロー」の情報と呼ばれます。
- 債務超過:これまでの成績が積み重なった結果です。貸借対照表(BS)に記載され、「ストック」の情報と呼ばれます。
毎年赤字という出血が続いた結果、会社の体力(純資産)をすべて削り切ってしまい、債務超過という瀕死の状態に陥る。
これが、最も典型的なパターンです。
【元銀行員が語る】実質債務超過の怖さ
私が銀行の審査部にいた頃、決算書をただの数字として見ることはありませんでした。
私たちは、その数字の裏にある「現実」を見ています。
帳簿上は資産があっても、
「この売掛金、本当に回収できるのか?」
「この在庫、何年も倉庫に眠っていないか?」
「この土地の価値、今も本当にこの金額か?」
と、資産を厳しく評価し直します。
その結果、帳簿上は資産超過でも、実態は債務超過である「実質債務超過」の会社は少なくありません。
融資審査では、この実態こそが最も重要視されます。
決算書の数字だけを見て安心するのは、非常に危険なのです。
債務超過を放置する3つの深刻なデメリット【融資審査の視点】
1. 金融機関からの新規融資が絶望的に困難になる
もし、あなたの会社のメインバンクの担当者から、改まった表情でこう告げられたらどうしますか?
「大変申し上げにくいのですが、今後の追加融資は難しい状況です」
債務超過の決算書は、融資審査の会議では「赤札」案件として扱われます。
返済能力への信頼が根本から揺らいでいるため、追加融資は原則NG。
それどころか、既存融資の一括返済を求められるリスクすらあります。
会社の血液であるキャッシュの供給が、完全にストップしてしまうのです。
2. 取引先からの信用を失い、事業継続が困難になる
信用調査会社のレポートなどで財務状況の悪化が知れ渡れば、取引先との関係も変わります。
「申し訳ないが、今後は現金取引でお願いしたい」
「次の契約更新は見送らせてほしい」
このように取引条件が悪化したり、取引そのものを打ち切られたりする。
それは、じわじわと社会から孤立していくような、冷たい感覚を伴います。
この状況はキャッシュフローの悪化に直結し、たとえ黒字であっても倒産する危険性を一気に高めます。
3. 倒産のリスクが現実味を帯びる
債務超過が、即、倒産を意味するわけではありません。
しかし、それは倒産という崖っぷちに立っているのと同じです。
新たな資金調達はできず、取引先からの締め付けは厳しくなる。
資金繰りは日に日に悪化し、やがて「資金ショート」という最悪の事態を迎える。
足元の小石が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていくのが聞こえるようです。
一刻も早い対処が求められます。
【実践編】債務超過を解消し事業を立て直す3つの具体的ステップ
ステップ1:負債を減らす(デットの改善)
まずは、重くのしかかる負債という重荷を軽くする「外科手術」から始めます。
遊休資産の売却による借入金返済
事業に使っていない不動産、政策保有の株式、過剰な設備など、眠っている資産はありませんか?
これらを売却し、その資金で借入金を返済します。
即効性が高く、バランスシートをすぐにスリム化できる有効な手段です。
ただし、どの資産を売るべきか、将来の事業への影響を慎重に見極める必要があります。
DES(デット・エクイティ・スワップ)の活用
これは、中小企業にとって非常に有効な「錬金術」です。
特に、経営者が会社に貸し付けている「役員借入金」を、資本金に振り替える(現物出資する)手法を指します。
- Before: 負債(役員借入金)
- After: 純資産(資本金)
これにより、負債が減り、自己資本が増強されるため、金融機関からの評価が劇的に改善することがあります。
ただし、税務上の注意点もあるため、必ず税理士などの専門家へ相談してください。
ステップ2:資本を増やす(エクイティの改善)
次に、会社の体力そのものである自己資本(純資産)に、新たな血液を注ぎ込む「輸血」を行います。
増資(第三者割当・株主割当)の実施
新たな出資者を募ったり(第三者割当)、既存の株主に追加出資を依頼したり(株主割当)する方法です。
しかし、これは簡単なことではありません。
事業の将来性や、後述する再建計画に絶対的な説得力がなければ、誰も大切なお金を出してはくれません。
あなたの会社の未来という「物語」で、人の心を動かせるかが問われます。
役員からの借入金を資本金に振り替える
これはステップ1で解説したDESの一種ですが、中小企業において最も現実的で実行しやすい資本増強策です。
経営者自身が、会社への貸付金を「出資」という形に変えることで、会社の体力を回復させます。
手続きは司法書士に、税務的な影響は税理士に、必ず確認しながら進めましょう。
ステップ3:利益を創出する(収益力の改善)
外科手術と輸血で延命しても、体質そのものが変わらなければ意味がありません。
最後のステップは、自らの力で利益を生み出す筋肉質な体を作るための「トレーニング」です。
不採算事業からの撤退・コスト削減
まずは、出血を止めることが最優先です。
赤字を垂れ流している事業や店舗からは、勇気をもって撤退する決断も必要です。
そして、聖域なきコストカット。
特に、毎月固定で出ていく家賃や人件費、リース料などの固定費にメスを入れられるかが鍵となります。
固定費の削減については以下の記事も参考になります。
売上向上と利益率改善の具体策
コスト削減だけでは、会社は縮む一方です。
攻めの姿勢も忘れてはいけません。
私が常に重視するのは、単なる売上ではなく「粗利率」です。
- 価格戦略を見直し、安売りから脱却する。
- より付加価値の高い商品・サービスへシフトする。
- 利益率の高い顧客層にアプローチを集中する。
売上を追いかけるだけでなく、一件一件の取引から、いかに多くのキャッシュを残すか。
この視点が、会社の収益構造を根本から変えるのです。
立て直しの羅針盤!金融機関を納得させる経営改善計画書の作り方
これらのステップを実行に移す上で、絶対に不可欠なものがあります。
それが「経営改善計画書」です。
なぜ経営改善計画書が重要なのか?
金融機関が融資の継続や返済猶予(リスケジュール)を判断する際、最も重視するのがこの書類です。
これは、単なる作文ではありません。
未来への具体的な道筋と、経営者の本気度を示す「約束の書」なのです。



私が融資担当者として見てきた「通る計画書」と「通らない計画書」の差は、この「本気度」が数字と行動に裏付けられているかどうかに尽きました。
【元融資担当者が教える】計画書に盛り込むべき5つの必須項目
説得力のある計画書には、必ず以下の5つの要素が含まれています。
1. 現状分析と課題認識
なぜ債務超過に陥ったのか。
外部環境(市場の変化)と内部環境(自社の弱み)の両面から、客観的かつ冷静に分析します。
2. 具体的な改善策(アクションプラン)
先ほど解説した3つのステップを、自社の状況に合わせて具体的に記述します。
「いつまでに」「誰が」「何を」「どのように」実行するのかを明確に示します。
3. 数値計画(損益・資金繰り)
3〜5年程度の具体的な数値目標(売上、利益、キャッシュフロー)を策定します。
金融機関は「3年以内の経常利益黒字化」「5年以内の実質債務超過解消」といった具体的なマイルストーンを重視します。絵に描いた餅にならないよう、全ての数字に根拠が必要です。
4. 返済計画
改善によって生み出されたキャッシュから、今後どのように返済を進めていくのかを具体的に示します。
5. モニタリング体制
計画の進捗をどのように管理し、定期的に金融機関へ報告するかの体制を明記します。
これが「約束」を守る姿勢の証明になります。
計画書の説得力を高める「リアル感のある例示」
例えば、数値計画では以下のような具体的な数字が説得力を生みます。
| 項目 | 現状 | 1年後目標 | 3年後目標 | 5年後目標 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,000 | 10,500 | 11,500 | 12,000 | 客単価5%UP、新規顧客10%増 |
| 粗利率 | 20% | 22% | 25% | 25% | 高付加価値商品へのシフト |
| 固定費 | 3,000 | 2,800 | 2,700 | 2,700 | 事務所移転、リース契約見直し |
| 経常利益 | △1,000 | △510 | 175 | 300 | 3年後黒字化達成 |
| 純資産 | △500 | △1,010 | △835 | △535 | 債務超過解消へ |
「コストを5%削減し、客単価を10%上げることで、3年後には黒字化、5年後には債務超過解消を目指す」
このような、行動と数字が連動したリアルな物語こそが、金融機関の心を動かすのです。
よくある質問(FAQ)
Q: 債務超過でも融資を受けられる可能性はありますか?
A: 可能性はゼロではありませんが、極めて困難です。ただし、日本政策金融公庫の「企業再建資金」のようなセーフティネット融資や、今回解説したような説得力の高い経営改善計画書を提出し、事業の将来性を認められた場合に限り、例外的に融資が実行されるケースもあります。まずは計画書の作成から始めましょう。
Q: 債務超過はどのくらいの期間で解消すべきですか?
A: 一概には言えませんが、金融機関の一般的な目線としては「5年〜10年以内」での解消を目指す計画が求められることが多いです。重要なのは期間の長さよりも、計画の実現可能性と着実な進捗です。まずは3年以内の黒字化を現実的な目標にしましょう。
Q: 黒字なのに債務超過になるのはなぜですか?
A: 過去の赤字が累積している場合や、多額の設備投資を行った直後などで起こり得ます。例えば、過去に5,000万円の赤字が累積している場合、単年度で1,000万円の黒字を出しても、まだ4,000万円分の純資産マイナスが残っている状態です。黒字化は解消への第一歩ですが、それだけでは不十分な場合があります。
Q: 専門家にはどのタイミングで相談すべきですか?
A: 「債務超過かもしれない」と気づいた、まさにその時がベストなタイミングです。手遅れになる前が肝心です。税理士や中小企業診断士、私のような経営コンサルタントに相談することで、客観的な視点から有効な打開策を見つけやすくなります。初回の相談は無料で行っている専門家も多いので、まずは気軽に連絡してみることをお勧めします。
Q: 債務免除を金融機関にお願いすることはできますか?
A: 理論上は可能ですが、実現のハードルは非常に高いです。金融機関が債権放棄(債務免除)に応じるのは、法的整理(民事再生など)の場面や、再生計画全体のなかでそれが最も経済合理性が高いと判断された場合に限られます。安易に期待するのではなく、まずは自力での再建を目指すべきです。
まとめ
債務超過は、企業にとって深刻な事態であることは間違いありません。
しかし、それは事業の「終わり」を意味するものではないのです。



むしろ、これまで見過ごしてきた経営課題と正面から向き合い、会社をより強く生まれ変わらせるための「転機」と捉えるべきです。
本記事で解説した「負債を減らす」「資本を増やす」「利益を創出する」という3つのステップは、事業再生の王道です。
重要なのは、自社の状況を正確に把握し、実現可能な計画を立て、断固として実行すること。
さあ、まずはあなたの会社の貸借対照表をもう一度開いてみてください。
そのマイナスの数字は、絶望の烙印ではありません。
あなたがこれから描くべき、逆転の物語の序章です。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消