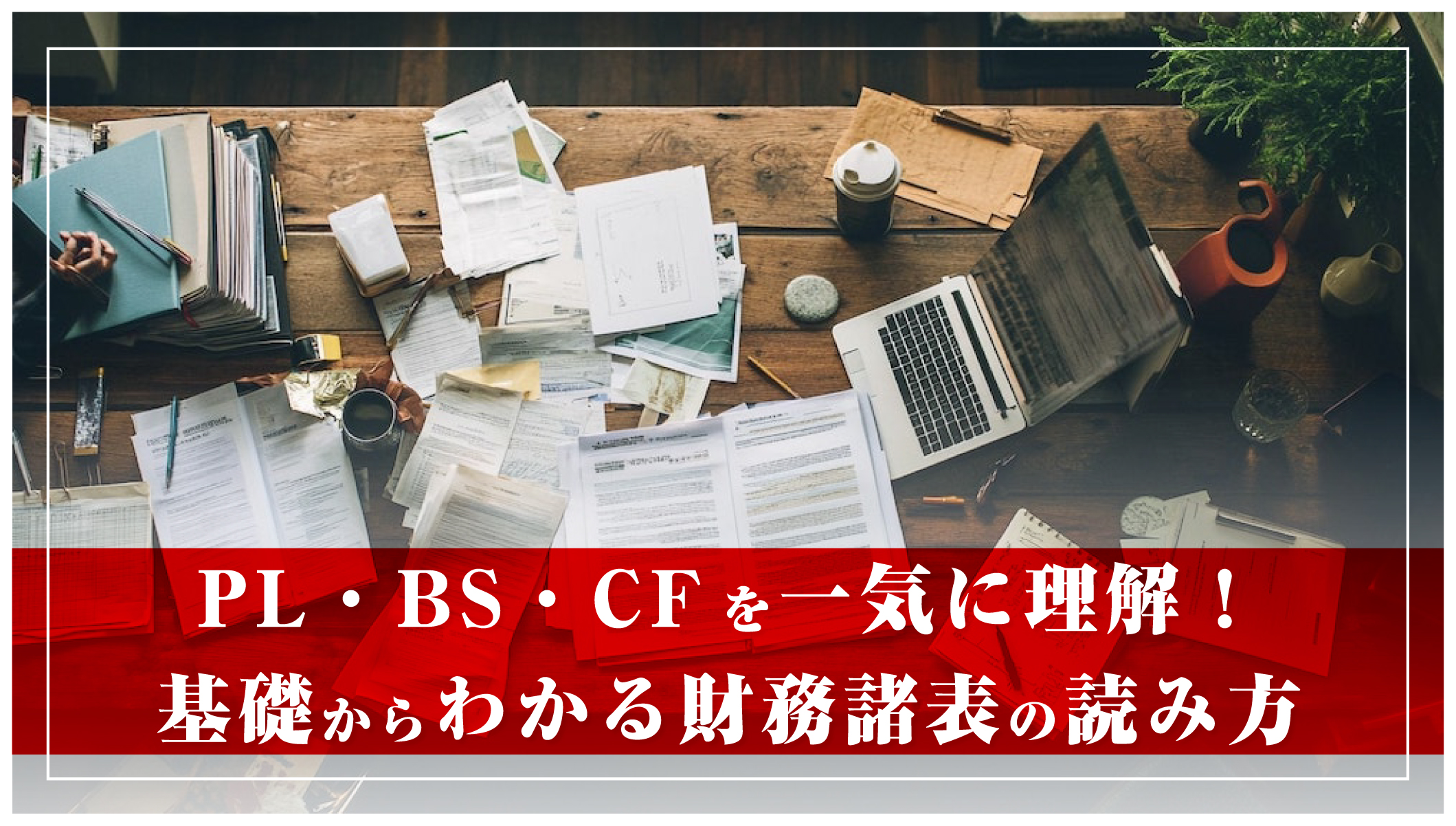会社の健康状態を示す「成績表」とも言える財務諸表。
しかし、PL・BS・CFという3つの書類を前に「どこから見ればいいの?」「数字が苦手で…」と悩んでいませんか?
特に中小企業の経営者の方からは、「売上は伸びているのに、なぜか資金繰りが楽にならない」「黒字のはずなのに、借入が増えてしまう…」といった切実な声をよく聞きます。
銀行で10年間融資審査を担当し、その後コンサルタントとして多くの中小企業の財務改善に携わった経験から言えるのは、PL(損益計算書)だけを見ていては会社の本当の姿は見えないということです。
 佐藤 真由美
佐藤 真由美実際、2020年に倒産した企業の約46.8%は「黒字倒産」だったというデータもあります。
この記事では、財務三表(PL・BS・CF)の基礎知識から、それぞれの繋がり、そして経営に活かすための読み解き方のポイントまで、初心者の方にも分かりやすく一気に解説します。
【この記事の結論】財務三表(PL・BS・CF)は「三位一体」で見ることが重要
会社の本当の健康状態は、PL(損益計算書)だけでは分かりません。「儲け」「財産」「お金の流れ」を示す3つの書類をセットで見ることで、「黒字倒産」のリスクを防ぎ、的確な経営判断が下せるようになります。
| 書類の種類 | 何がわかるか?(一言でいうと) | 特に注目すべきポイント |
|---|---|---|
| PL(損益計算書) | 会社の「儲け」 | 営業利益:本業で稼ぐ力を示す |
| BS(貸借対照表) | 会社の「財産と借金」のバランス | 自己資本比率:会社の安全性を測る |
| CF(キャッシュフロー計算書) | 会社の「リアルなお金の流れ」 | 営業CF:本業での現金創出力を見る |


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
資金繰り関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
なぜ財務三表? PL・BS・CFの基本と切っても切れない関係性
会社の健康診断書!財務諸表を読むことの本当の意味
「決算書なんて税理士に任せておけばいいんじゃないの?」
こんな声をよく聞きますが、これは大きな誤解です。
財務諸表は単なる税務申告のための書類ではなく、会社の健康状態を示す診断書であり、未来への羅針盤でもあります。
銀行で融資審査を担当していた頃、私はある製造業のA社を担当していました。
社長はカリスマ的な営業力を持ち、売上は右肩上がり。
しかし、決算書を見ると売掛金が膨らみ続け、在庫も山積み状態。いわゆる「黒字倒産」の予兆が見えていました。
私が懸念を伝えても「売上は伸びている」の一点張り。
その1年後、A社は資金ショートで倒産しました。
振り返れば、もし社長自身が財務諸表を読み解く力を持っていれば、資金繰り対策を早期に打てたはずです。
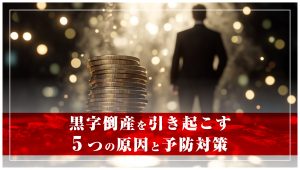
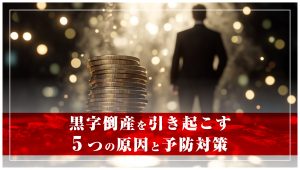
財務諸表を読むことには大きく3つの意義があります。
- 現状把握: 会社の健康状態(収益性・安全性・成長性)を客観的に診断できる
- 課題発見: 業績不振や資金不足などの問題を早期に発見できる
- 対策立案: 数字に基づいた具体的な経営改善策を考えられる
経営者が財務諸表を読みこなせれば、経営状態を十分に理解した上での経営判断が可能になるため、失敗リスクが低くなります。
銀行や取引先との交渉でも、自社の数字を理解していれば自信を持って臨めるでしょう。
💡 ワンポイントアドバイス
財務諸表は「過去の結果」を示すものですが、そこから「将来の予測」を行うために活用するものです。数字の裏にあるストーリーを読み解くことで、経営判断の質が大きく向上します。
PL・BS・CF、それぞれの役割は?サクッと概要理解
財務三表は、それぞれ会社の異なる側面を映し出す「三面鏡」のようなものです。
まずは各表の基本的な役割を押さえましょう。
PL(損益計算書)- 会社の「儲け」を表す表
PLは一定期間(通常1年間)の「収益 – 費用 = 利益」を示す表です。
これは人間で例えるなら「カロリー計算表」のようなもの。
1年間でどれだけの売上(摂取カロリー)があり、どれだけの費用(消費カロリー)がかかり、結果としてどれだけ儲かった(体重が増減した)かを示します。
PLの基本構造:
- 売上高(商品・サービスの販売で得た収入)
- 売上原価(商品・サービスの提供に直接かかったコスト)
- 販売費及び一般管理費(人件費、家賃、広告宣伝費など)
- 営業外収益・費用(本業以外での収支、利息など)
- 特別利益・損失(固定資産売却など一時的な損益)
BS(貸借対照表)- 会社の「財産と借金」を表す表
BSは特定の時点(通常、決算日)における「資産 = 負債 + 純資産」を示す表です。
人間で例えるなら「健康診断結果表」のようなもの。
その時点での会社の財産(資産)と借金(負債)、そして自己資本(純資産)のバランスを示します。
BSの基本構造:
- 資産(会社が持つ財産)
- 流動資産(現金、売掛金、在庫など1年以内に現金化できるもの)
- 固定資産(建物、機械、投資有価証券など長期的な財産)
- 負債(会社の借金)
- 流動負債(買掛金、短期借入金など1年以内に返済すべきもの)
- 固定負債(長期借入金など長期間にわたって返済するもの)
- 純資産(資本金、利益剰余金など会社の自己資本)
CF(キャッシュフロー計算書)- 会社の「お金の流れ」を表す表
CFは一定期間の「現金の流入 – 現金の流出 = 現金の増減」を示す表です。
人間で例えるなら「血流チェックレポート」のようなもの。資金がどこから来て、どこに使われたかを示します。
CFの基本構造:
- 営業CF(本業での現金の増減)
- 投資CF(設備投資や投資による現金の増減)
- 財務CF(借入れや返済、配当による現金の増減)
⚠️ 注意事項
中小企業ではCF計算書の作成が義務付けられていない場合が多いですが、資金繰り管理のためには作成することを強くお勧めします。会計ソフトで自動作成できるものもありますし、顧問税理士に依頼することも可能です。
【図解】PL・BS・CFはこう繋がっている!三位一体で見る理由
財務三表は別々のものではなく、密接に連動しています。
三表の関係性を理解することで、会社の状況を立体的に把握できるようになります。
PLとBSの関係
PLで計上された利益は、BS上の純資産(利益剰余金)に反映されます。
例:当期純利益1,000万円 → 利益剰余金が1,000万円増加 → 純資産が1,000万円増加PLとCFの関係
PLの利益とCFの現金増減は必ずしも一致しません。これが「黒字なのに資金不足」が起こる理由です。
例:売上1,000万円(売掛金)、利益200万円 → PLは利益が出ているが、
売掛金が未回収なら営業CFはマイナスになる可能性があるBSとCFの関係
BSの資産・負債の増減は、CFの各区分に影響します。
例:固定資産(機械設備)購入500万円 → 投資CFが500万円マイナス
銀行借入300万円 → 財務CFが300万円プラス三表の関係をシンプルな例で説明
ある小売店が以下の取引を行った場合:
- 商品100万円を仕入れ(掛け取引)
- そのうち80万円分を120万円で販売(現金取引)
- 仕入れた商品代金100万円を支払い(現金)
これを三表で表すと、
- 売上: 120万円
- 売上原価: 80万円
- 利益: 40万円
- 資産: 現金20万円(120万円-100万円)、在庫20万円(仕入れ100万円のうち未販売分)
- 負債: 0円(買掛金は支払済み)
- 純資産: 40万円(当期利益)
- 営業CF: 20万円(売上120万円-仕入代金支払100万円)
- 投資CF: 0円
- 財務CF: 0円
この例では利益40万円に対し、現金の増加は20万円にとどまります。これは在庫20万円分が現金化されていないためです。このような「利益」と「現金」のズレを理解することが、財務管理の基本です。
📝 ポイントまとめ
- PL:一定期間の儲け(収益性)を示す
- BS:特定時点の財政状態(安全性)を示す
- CF:一定期間の現金の動き(流動性)を示す
- 三表は相互に連動しており、すべてを見ることで初めて会社の全体像が見える
あなたの会社では、これら三表を総合的に見ていますか?
もし一つだけ(特にPLだけ)しか見ていないなら、会社の状況を一面的にしか捉えられていない可能性があります。
会社の「儲け」がわかる!PL(損益計算書)の読み方徹底ガイド
売上から利益まで、5つの利益で見る収益構造
PLには「売上高」から「当期純利益」に至るまでに、実は複数段階の利益が存在します。
これらは会社の収益構造を多角的に把握するために重要な指標です。
会社の収益力を示す5つの利益指標
1. 売上総利益(粗利益)
売上高 - 売上原価 = 売上総利益これは商品やサービスを提供する「本業の基本的な儲け」を示します。
例えば、100万円の商品を仕入れて150万円で売れば、売上総利益は50万円です。
2. 営業利益
売上総利益 - 販売費及び一般管理費 = 営業利益本業の活動全体での儲けを示します。
上記の例で、人件費や家賃などの経費が30万円かかれば、営業利益は20万円になります。
3. 経常利益
営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 = 経常利益本業に加えて、財務活動なども含めた通常の企業活動全体での儲けです。
例えば、受取利息1万円、支払利息3万円があれば、経常利益は18万円になります。
4. 税引前当期純利益
経常利益 + 特別利益 - 特別損失 = 税引前当期純利益臨時的な利益や損失も含めた、税金を引く前の最終的な儲けです。
例えば、遊休資産の売却で5万円の特別利益があれば、税引前当期純利益は23万円になります。
5. 当期純利益
税引前当期純利益 - 法人税等 = 当期純利益すべての活動を通じた、税金を差し引いた後の最終的な儲けです。
これが会社のいわゆる「黒字」「赤字」を決める数字です。
税率30%とすると、当期純利益は16.1万円となります。



私が銀行で融資審査をしていた頃、特に注目していたのは「営業利益」です。これが継続的にプラスであれば、本業で稼ぐ力があると判断できるからです。
一方、営業利益が赤字で経常利益だけが黒字という場合は、本業以外の収入(例:不動産収入など)に依存している可能性があり、注意が必要です。
PL分析のキホン:利益率と前年比較で課題発見
PLを単に見るだけでなく、分析することで会社の収益性や課題を見出すことができます。
主要な利益率指標とその意味
1. 売上総利益率(粗利率)
売上総利益 ÷ 売上高 × 100 = 売上総利益率(%)目安:業種によって大きく異なりますが、一般的に小売業で20~30%、製造業で30~40%、サービス業で50~70%程度です。
意味:商品やサービスの価格設定や仕入れコスト管理の適切さを示します。
例:A社(小売業)の売上高1億円、売上総利益2,000万円の場合
2,000万円 ÷ 1億円 × 100 = 20%→ 小売業としては一般的なレベルの粗利率です。
2. 営業利益率
営業利益 ÷ 売上高 × 100 = 営業利益率(%)目安:業種にもよりますが、中小企業では5~10%が一つの目安です。
意味:本業での効率的な利益創出能力を示します。販管費のコントロールがうまくいっているかどうかも分かります。
例:上記A社の営業利益が500万円の場合
500万円 ÷ 1億円 × 100 = 5%→ 最低限のラインはクリアしていますが、改善の余地があります。
3. 経常利益率
経常利益 ÷ 売上高 × 100 = 経常利益率(%)目安:中小企業では3~8%程度が一般的です。
意味:財務活動も含めた企業の総合的な収益力を示します。
例:上記A社の経常利益が450万円の場合
450万円 ÷ 1億円 × 100 = 4.5%→ 支払利息などが利益を圧迫している可能性があります。
前年比較分析(トレンド分析)
単年度の数字だけでなく、前年との比較を行うことで、会社の成長性や問題点を把握できます。
例:A社の2年分データ
| 項目 | 前年 | 当年 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,000万円 | 1億円 | +1,000万円 | +11.1% |
| 売上総利益 | 1,900万円 | 2,000万円 | +100万円 | +5.3% |
| 営業利益 | 600万円 | 500万円 | -100万円 | -16.7% |
この分析から分かること:
- 売上は11.1%伸びているのに、売上総利益の伸びは5.3%にとどまっている → 原価率の悪化
- 売上総利益は増えているのに、営業利益は減少している → 販管費の増加
こうした分析から、「原価率の悪化」と「販管費の増加」という2つの課題が見えてきました。
さらに詳しく調べれば、原価率悪化の原因(仕入価格の上昇?値引き販売の増加?)や、増えた販管費の内訳(人件費?広告費?)が分かります。
自社のPLを用意し、上記の利益率を計算してみましょう。さらに可能であれば、過去2~3年分の推移を確認し、数字が改善しているか、悪化しているかをチェックしてみてください。その上で「なぜそうなったのか?」を考えることが重要です。
皆さんの会社のPLを分析すると、どのような特徴や課題が見えてきますか?
もし利益率が業界平均より低かったり、前年より悪化していたりする場合は、原因を探り、対策を考える必要があります。
会社の「財産と借金」がわかる!BS(貸借対照表)の読み方徹底ガイド
資産・負債・純資産のバランスをチェック!BSの基本構造
BSは「会社の財政状態を示す表」であり、資産・負債・純資産の3つの要素で構成されています。
BSの基本的な構造と見方
資産の部(会社が持っている財産)
- 流動資産:1年以内に現金化できる資産
- 現金預金:すぐに使える資金
- 売掛金:販売したけどまだ回収できていないお金
- 棚卸資産(在庫):販売前の商品や材料
- 固定資産:長期間保有する資産
- 有形固定資産:建物、機械、車両など
- 無形固定資産:特許権、ソフトウェアなど
- 投資その他の資産:投資有価証券、敷金など
負債の部(会社の借金)
- 流動負債:1年以内に返済すべき負債
- 買掛金:仕入れたけどまだ支払っていないお金
- 短期借入金:1年以内に返済予定の借入金
- 未払費用:発生したけどまだ支払っていない経費
- 固定負債:返済まで1年以上ある負債
- 長期借入金:返済まで1年以上ある借入金
- 社債:社債発行による借入金
- 退職給付引当金:将来の退職金支払いのための引当金
純資産の部(会社の自己資本)
- 資本金:会社設立時や増資時に出資されたお金
- 資本剰余金:資本金以外の出資金や資本取引で生じた剰余金
- 利益剰余金:過去の利益の蓄積
BSを読む際の重要ポイント
🔍 資産の中身をチェック
- 現預金の額は十分か?(最低でも月商の1~2ヶ月分あるのが理想)
- 売掛金の金額は適正か?(回収がスムーズに行われているか)
- 在庫は適正水準か?(過剰在庫になっていないか)
🔍 負債の状況をチェック
- 借入金の総額は適切か?(過剰借入になっていないか)
- 短期借入金と長期借入金のバランスは?(短期に偏っていないか)
- 買掛金の水準は適正か?(支払いサイトは適切か)
🔍 純資産の充実度をチェック
- 利益剰余金はプラスで増加傾向か?(継続的に利益を出せているか)
- 自己資本は十分か?(借入金に頼りすぎていないか)
💡 ワンポイントアドバイス
BSは「スナップショット(一時点の状況)」です。つまり、決算日という特定の日の状況を表しています。そのため、決算対策で一時的に数字を良く見せている可能性もあります。できれば月次BSも確認し、年間を通じた傾向を把握することをお勧めします。
安全性は大丈夫?自己資本比率と流動比率で健全性チェック
BSからは会社の財務健全性(安全性)を示す重要な指標を算出できます。特に重要なのが以下の指標です。
重要な安全性指標とその意味
1. 自己資本比率
純資産 ÷ 総資産 × 100 = 自己資本比率(%)目安:業種によって異なりますが、中小企業では20~30%以上あれば一応安心できるレベルです。銀行融資では一般的に自己資本比率が20%以上あることが最低ラインとされることが多いです。
意味:会社の財務体質の強さ、負債への依存度を示します。比率が高いほど倒産リスクが低く、財務基盤が安定していると判断できます。
例:B社の総資産5,000万円、純資産1,000万円の場合
1,000万円 ÷ 5,000万円 × 100 = 20%→ 一般的な基準はクリアしていますが、余裕があるとは言えません。
2. 流動比率
流動資産 ÷ 流動負債 × 100 = 流動比率(%)目安:一般的に100%以上が最低ライン、150%以上あれば安心です。
意味:短期的な支払能力を示します。1年以内に支払うべき負債を、1年以内に現金化できる資産でどれだけカバーできるかを表します。
例:B社の流動資産2,000万円、流動負債1,500万円の場合
2,000万円 ÷ 1,500万円 × 100 = 133.3%→ 100%は超えていますが、安全マージンは少なめです。
3. 当座比率
(現金預金 + 売掛金 + 有価証券)÷ 流動負債 × 100 = 当座比率(%)目安:一般的に100%以上が理想とされます。
意味:流動比率よりもさらに短期的な支払能力を示します。在庫など換金に時間がかかる資産を除いた、より即時的な支払能力を見ます。
例:B社の現金預金500万円、売掛金1,000万円、流動負債1,500万円の場合
(500万円 + 1,000万円) ÷ 1,500万円 × 100 = 100%→ ギリギリ100%をクリアしています。在庫が多いケースでは当座比率と流動比率の差が大きくなります。
4. 固定比率
固定資産 ÷ 純資産 × 100 = 固定比率(%)目安:100%以下が理想です。
意味:長期的な資金調達(自己資本)に対して、固定資産への投資がどの程度行われているかを示します。100%を超えると、固定資産の一部を借入金で賄っていることになります。
例:B社の固定資産3,000万円、純資産1,000万円の場合
3,000万円 ÷ 1,000万円 × 100 = 300%→ 300%は高すぎです。固定資産の多くを借入金で賄っており、長期的な財務バランスを見直す必要があります。
銀行融資審査で見られるポイント
私が銀行の融資審査担当だった経験からお伝えすると、銀行はBSを特に重視して審査を行います。
具体的には、
- 債務償還年数(有利子負債 ÷ 営業キャッシュフロー):何年で借金を返済できるかを示す指標。一般的に10年以内が望ましい
- インタレスト・カバレッジ・レシオ(営業利益 ÷ 支払利息):利息の支払能力を示す指標。最低でも1以上、できれば3以上が望ましい
- 借入金依存度(有利子負債 ÷ 総資産):借入金への依存度を示す指標。30%以下が理想
🔄 よくある誤解
「借入はできるだけ少ない方がいい」という考えは必ずしも正しくありません。重要なのは借入金の「絶対額」ではなく、「返済能力とのバランス」です。成長投資のためであれば、返済計画を立てた上で適切に借入を活用することが経営戦略となります。
あなたの会社のBSから安全性指標を計算してみると、どのような結果になりますか?
もし指標が目安を下回っている場合は、財務体質の改善が必要かもしれません。
会社の「お金の流れ」がわかる!CF(キャッシュフロー計算書)の読み方徹底ガイド
なぜCFが重要?「黒字倒産」を防ぐカギはここにある!
「利益が出ているのに、なぜお金が足りないんだ?」
この疑問は多くの経営者が抱える悩みです。
東京商工リサーチの調査によれば、2020年に倒産した企業7,773社のうち、約46.8%は「黒字倒産」だったとされています。
この「利益と現金の不一致」こそ、CFの重要性を物語っています。
利益(PL)と現金(CF)がズレる主な理由
1. 売掛金の発生
PLでは売上計上時に利益を認識しますが、実際の現金は回収時にしか入りません。
例:3月に1,000万円の商品を販売(掛け取引)した場合
- PL:3月に1,000万円の売上(+ 利益)を計上
- CF:実際のお金は4月や5月にならないと入金されない
2. 棚卸資産(在庫)の増加
在庫を購入する際にはお金を支払いますが、PLでは販売時まで費用計上されません。
例:仕入れ500万円を行ったが、まだ販売していない場合
- PL:費用はまだ計上されない(売上時に原価として計上される)
- CF:500万円の現金流出が発生
3. 減価償却費の影響
減価償却費はPLで費用計上されますが、実際の現金支出はありません。
例:5,000万円の機械を購入し、10年で償却する場合
- PL:毎年500万円の減価償却費を計上
- CF:実際の現金支出は購入時の1回のみ
4. 借入金の返済
借入金の返済はPLに計上されませんが、CFでは現金の流出となります。
例:借入金の月々の返済100万円
- PL:元本の返済は費用にならない(利息部分のみ費用)
- CF:100万円の現金流出(元本返済+利息)
黒字倒産のメカニズムと防止策
黒字倒産の典型的なケース:
急成長している会社が、売上増加に伴って売掛金や在庫が膨らみ、資金繰りが追いつかなくなるケースが多いです。
また、設備投資を行った直後も要注意期間です。
実際の事例から学ぶ:
私がコンサルティングを担当したC社(卸売業)は、売上高2億円、経常利益2,000万円の黒字企業でした。
しかし、売掛金が徐々に増加し(売上の4ヶ月分、約7,000万円)、さらに在庫も1億円まで膨らんでいました。
その結果、毎月の資金繰りが苦しくなり、支払遅延が発生。
取引先からの信用を失い、最終的には倒産寸前まで追い込まれました。
黒字倒産を防ぐためのポイント:
- キャッシュフロー計算書を作成する:法的義務がなくても、自社のためにCF計算書を作成しましょう
- 資金繰り表で予測管理を行う:少なくとも3ヶ月先までの入出金予測を立てて管理する
- 売掛金を適正に管理する:回収サイトの短縮、必要に応じてファクタリングなどの活用
- 在庫を適正水準に保つ:在庫管理システムの導入、定期的な在庫分析
- 運転資金の調達手段を確保する:当座貸越や短期融資枠を事前に確保しておく



「黒字」と言っても、それは必ずしも「お金がある」ということではありません。PLの利益と実際の現金の動きは別物です。
特に成長期には「黒字資金ショート」のリスクが高まるため、CF管理を徹底してください。


営業・投資・財務CFから読み解く!会社のリアルな資金状況
キャッシュフロー計算書は、お金の流れを3つの区分(営業CF・投資CF・財務CF)に分けて示します。
各区分のプラス・マイナスの組み合わせで、会社の現在のステージや課題が見えてきます。
3つのCF区分とその意味
1. 営業CF:本業の活動によるお金の増減
- 主な内容:売上回収、仕入・経費支払い、給与支払いなど
- プラスなら:本業でキャッシュを生み出せている
- マイナスなら:本業の資金繰りが悪い(危険信号)
2. 投資CF:将来のための投資活動によるお金の増減
- 主な内容:設備投資、有価証券購入・売却、子会社株式取得など
- マイナスなら:将来に向けた投資を行っている
- プラスなら:投資資産を売却して現金化している
3. 財務CF:資金調達や返済によるお金の増減
- 主な内容:借入・返済、増資、配当支払いなど
- プラスなら:外部から資金調達している
- マイナスなら:借入返済や配当で資金流出している
CF区分の組み合わせパターンで見る会社の状況
| 営業CF | 投資CF | 財務CF | 会社の状況 |
|---|---|---|---|
| + | – | + | 成長期:本業で稼ぎつつ、積極投資のため借入も行っている |
| + | – | – | 成熟期:本業の稼ぎで投資しながら借入も返済している |
| + | + | – | 縮小期:投資を抑え、資産売却も行いながら借入返済を進めている |
| – | – | + | 危険期:本業で赤字なのに投資を続け、借入に依存している |
| – | + | + | 再建期:本業が赤字で、資産売却と借入で資金をつないでいる |
具体例で理解する:
D社(製造業)の3年間のCF推移
1年目:営業CF +5,000万円、投資CF -8,000万円、財務CF +3,000万円
2年目:営業CF +6,000万円、投資CF -3,000万円、財務CF -2,000万円
3年目:営業CF +7,000万円、投資CF +1,000万円、財務CF -8,000万円この推移から、D社は成長投資期→成熟期→投資回収・財務改善期へと移行していることが読み取れます。
最初は設備投資に借入金も活用していましたが、徐々に本業の稼ぎを高め、最終的には投資を抑えて借入返済を進めています。
フリーキャッシュフローの重要性
フリーキャッシュフロー(FCF)は「営業CF + 投資CF」で計算される、企業が自由に使えるキャッシュの額を示します。
フリーキャッシュフロー = 営業CF + 投資CFFCFがプラスであれば、本業で稼いだお金で投資もカバーでき、さらに借入返済や配当にも回せるお金があることを意味します。
例:E社のケース
営業CF +3,000万円、投資CF -2,000万円、財務CF -1,000万円
→ フリーキャッシュフロー = +3,000万円 + (-2,000万円) = +1,000万円E社はFCFが+1,000万円なので、本業の稼ぎで投資をカバーでき、その上で借入返済にも資金を回せています。
これは理想的な資金循環と言えます。
中小企業庁の調査によれば、継続的に成長している中小企業の約7割は営業CFが3期連続でプラスを維持しているというデータがあります。逆に、営業CFが2期連続でマイナスの企業の約4割が、その後3年以内に経営危機に陥るというデータもあります。
あなたの会社のCFはどのようなパターンになっていますか?
もし営業CFがマイナスなら、本業での現金創出力を高める取り組みが急務です。
また、投資CFと財務CFのバランスも適切か検討してみましょう。
財務三表を分析して「経営改善」に活かす実践ステップ
自社の決算書でやってみよう!簡単・財務分析チェックリスト
これまでの解説を踏まえ、実際に自社の財務諸表を分析するためのチェックリストをご紹介します。
財務三表分析チェックリスト
PLのチェックポイント:
□ 売上高は前年比でどう変化している?(±○○%)
□ 売上総利益率(粗利率)は適正か?(○○%、前年比±○○ポイント)
□ 営業利益率は業界平均と比べてどうか?(○○%、業界平均○○%)
□ 売上が増えているのに利益が減っている場合、原因は何か?
□ 固定費(人件費、家賃等)の売上高に対する比率は適正か?
BSのチェックポイント:
□ 現預金の残高は月商の何ヶ月分あるか?(○○ヶ月分)
□ 売掛金回転期間は適正か?(○○日、前年○○日)
売掛金回転期間 = 売掛金 ÷ 売上高 × 365日□ 在庫回転期間は適正か?(○○日、前年○○日)
在庫回転期間 = 棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365日□ 自己資本比率は安全なレベルか?(○○%、業界平均○○%)
□ 流動比率・当座比率は十分か?(流動比率○○%、当座比率○○%)
CFのチェックポイント:
□ 営業CFはプラスか?過去3期の推移はどうか?
□ 投資CFと営業CFのバランスはどうか?(投資CFは営業CFの範囲内か)
□ 財務CFと有利子負債の状況はどうか?(返済・調達のバランス)
□ フリーキャッシュフロー(営業CF+投資CF)はプラスか?
実際に自社の財務諸表で分析してみましょう
例えば、ある製造業F社のケースで考えてみます。
PLから分かる課題:
- 売上高は前年比10%増だが、売上総利益率は前年の35%から32%に低下
- 営業利益率も8%から6%に低下
→ 原価率の上昇と販管費の増加が課題
BSから分かる課題:
- 売掛金回転期間が60日から75日に延長
- 在庫回転期間も45日から60日に延長
- 自己資本比率は25%で前年と変わらず
→ 売掛金と在庫の管理が課題
CFから分かる課題:
- 営業CFが前年の2,000万円から1,000万円に減少
- 投資CFは-1,500万円(設備投資を実施)
- 財務CFは+500万円(借入金が増加)
→ 本業の資金創出力が低下し、不足分を借入で補っている状態
以上の分析から、F社の場合は「原価率の改善」「売掛金の早期回収」「在庫の適正化」が重要課題であることが分かります。
💯 成功事例
私がコンサルティングしたG社では、同様の分析後、売掛金回収条件の見直し(手形からファクタリングへの切替)と在庫適正化(在庫分析による滞留品処分)を実施。その結果、営業CFが前年比で60%増加し、資金繰りが大幅に改善しました。
数字から課題発見!具体的な経営改善アクションプラン例
財務分析で見つかった課題を解決するための具体的なアクションプランをご紹介します。
収益性の改善(PL改善)策
1. 売上総利益率(粗利率)の改善
- ✓ 仕入先・外注先の見直しやコスト交渉
- ✓ 製造工程の効率化、歩留まり率の向上
- ✓ 高粗利商品・サービスへの注力
- ✓ 適正な価格設定(値上げや割引率の見直し)
2. 販管費の削減と効率化
- ✓ 固定費の見直し(家賃、通信費、保険料等)
- ✓ 人件費の適正化(業務効率化、適正人員配置)
- ✓ 広告宣伝費のROI分析と効率的な配分
- ✓ 経費精算システム導入による無駄な支出の可視化
資産効率の改善(BS改善)策
1. 売掛金回収の改善
- ✓ 回収条件の見直し(支払期日の短縮、前受金の導入)
- ✓ 入金管理の強化(入金予定管理表の作成)
- ✓ ファクタリングの活用(特に大口取引先や回収期間の長い取引)
- ✓ 与信管理の強化(新規取引先の信用調査)
2. 在庫管理の最適化
- ✓ ABC分析による在庫の優先順位付け
- ✓ 適正在庫水準の設定とモニタリング
- ✓ 滞留在庫の早期処分(値引販売、転用など)
- ✓ 発注頻度・発注量の最適化(小ロット・高頻度化)
3. 自己資本比率の向上
- ✓ 利益の内部留保(配当抑制)
- ✓ 不要資産の売却と借入金返済
- ✓ 増資の検討(事業承継を見据えた場合も)
- ✓ 設備投資計画の見直しと優先順位付け
キャッシュフロー改善(CF改善)策
1. 営業CFの増加
- ✓ PL改善策+BS改善策の実行
- ✓ 前受金の増加(長期契約の前受化など)
- ✓ 支払条件の見直し(支払サイトの延長交渉)
- ✓ キャッシュディスカウント(早期支払による値引)の活用
2. 投資CFの最適化
- ✓ 設備投資の優先順位付けと分散実施
- ✓ リースやレンタルの活用(初期投資抑制)
- ✓ 投資効果の測定と投資判断基準の明確化
- ✓ 遊休資産の売却によるキャッシュイン
3. 財務CFの適正化
- ✓ 借入金の借換え(金利・返済条件の改善)
- ✓ 借入ポートフォリオの見直し(短期・長期のバランス)
- ✓ 資本政策の検討(自己資本と他人資本のバランス)
- ✓ 公的支援・補助金の活用
ケーススタディ:経営改善プランの実例
課題シナリオ:H社(小売業)は売上3億円、経常利益1,500万円の黒字企業だが、売掛金が増加し、在庫も膨らみ、資金繰りが悪化。自己資本比率も15%と低め。
改善プラン:
| 課題 | 具体的施策 | 改善目標 | 期待効果 |
|---|---|---|---|
| 売掛金増加 | 大口顧客への回収交渉、一部ファクタリング導入 | 回収期間を60日から45日に短縮 | +2,500万円の資金改善 |
| 在庫過多 | ABC分析による在庫適正化、滞留品処分 | 在庫回転率を年6回から8回に向上 | +2,000万円の資金改善 |
| 粗利率低下 | 仕入先交渉、高粗利商品へのシフト | 粗利率を30%から32%に改善 | +600万円の利益改善 |
| 自己資本不足 | 利益の内部留保、不要資産売却 | 自己資本比率を15%から20%に向上 | 財務基盤強化 |
この改善策を実行した結果、H社は1年後に営業CFが3,000万円増加し、借入金も1,000万円削減できました。
銀行からの評価も向上し、新規事業のための融資も獲得できたという実例です。
🧠 考えてみよう
あなたの会社の財務分析結果に基づいて、どのような改善プランが考えられますか?まずは「最も効果が大きく、比較的取り組みやすい施策」から始めることをお勧めします。
専門家やツールも活用!継続的なモニタリングのすすめ
財務諸表の分析と改善は一度きりではなく、継続的に行うことが重要です。
効率的に継続するためのツールや専門家の活用方法をご紹介します。
継続的なモニタリングの仕組み作り
1. 月次決算の実施
- 毎月、簡易的なPLとBSを作成する
- 予算と実績の差異分析を行う
- 主要KPI(売上、粗利率、営業利益率など)の推移をグラフ化
2. 資金繰り表の活用
- 少なくとも3ヶ月先までの入出金予測を立てる
- 週次または月次で更新し、予測と実績の差を検証
- 資金不足が予測される月は早めに対策を講じる
3. 財務KPIのダッシュボード化
- 経営者が一目で把握できる指標をまとめたダッシュボードを作成
- 例:売上・粗利推移、現預金残高、売掛金・在庫の推移、借入金残高など
- 異常値にはアラートを設定し、早期発見できるようにする
活用すべきツールとサービス
1. クラウド会計ソフト
- freee、マネーフォワード、弥生会計などのクラウド会計ソフトで財務データを自動集計
- リアルタイムに近い形で財務状況を把握
- 多くのソフトは財務分析機能も搭載しており、グラフなども自動生成
2. 経営管理ツール
- スプレッドシート(Excel、Googleスプレッドシート)を活用した自社用ダッシュボード
- BIツール(Power BI、Tableauなど)を使った高度な分析(規模が大きい企業向け)
- プロジェクト管理ツール(Trello、Asanaなど)で改善タスクを管理
3. 専門家の活用
- 税理士:月次決算の支援、税務の観点からのアドバイス
- 中小企業診断士:財務分析に基づく経営改善提案
- 金融機関の経営支援担当:融資以外にも経営支援サービスを提供していることが多い
- 公的支援機関:よろず支援拠点、商工会議所などの無料相談サービス
専門家と連携するときのポイント
1. 自社の課題を明確にする
- 「資金繰りを改善したい」「借入金を減らしたい」など具体的な悩みを伝える
- 数字での現状と目標を示す(例:「売掛金回収を現在の60日から45日に短縮したい」)
2. 定期的なミーティングを設定する
- 月次決算後のレビューミーティングを習慣化
- 改善計画の進捗確認と軌道修正の機会とする
3. データを共有しやすい環境を作る
- クラウド会計ソフトのアドバイザー機能を活用
- 財務データを適切に整理して提供する



経営改善をさらに深めたい方は、中小企業庁の「経営力向上計画」の策定も検討してください。
この計画を策定することで、税制優遇や金融支援などのメリットが得られる場合があります。
また、地域の商工会議所などでは無料の経営相談会も実施されていますので、積極的に活用しましょう。
皆さんは、どのような形で財務モニタリングを行っていますか?
まだ仕組みができていない場合は、まず月次の売上・粗利・営業利益のグラフ化から始めてみてはいかがでしょうか。
可視化するだけでも、意外な傾向や課題が見えてくることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q: 財務諸表って、簿記を知らないと読めませんか?
A: 結論から言うと、簿記の知識がなくてもポイントを押さえれば読めるようになります。
確かに仕訳の仕組みなど簿記の基礎知識があれば理解が深まりますが、経営判断のための読み方なら、この記事で解説した各表の役割や重要指標の意味を理解することから始めましょう。
特に重要なのは、PLの「営業利益」、BSの「自己資本比率」と「流動比率」、可能ならCFの「営業キャッシュフロー」の4つを押さえることです。これらの数字とその推移を見るだけでも、会社の健康状態がかなり分かります。
もちろん、時間があれば簿記3級程度の知識を習得すると、より深く理解できるようになります。オンライン講座なら20時間程度の学習で基礎は身につきます。
Q: PLで利益が出ているのに、なぜお金が足りなくなるのですか?
A: これは「黒字倒産」のリスクにも繋がる重要な点です。PLの利益と実際の現金の増減には、次のようなズレが生じる要因があります。
- 売掛金の増加:
売上を計上した時点で利益は認識されますが、実際の現金回収はその後になります。売上が拡大している時期は、売掛金も増え続けるため、利益に比べて現金収入が少なくなります。 - 在庫の増加:
仕入れた商品は販売するまでPL上で費用にならず、BSの在庫として計上されます。しかし、仕入代金の支払いは発生するため、現金は減少します。 - 設備投資:
設備を購入すると、一度に大きな資金が出ていきますが、PL上では減価償却費として複数年に分けて費用計上されます。 - 借入金の返済:
元本の返済はPL上の費用にはなりませんが、現金は確実に減少します。
これらの要因で、黒字でも資金不足に陥ることがあります。だからこそ、PLだけでなくBS・CFも含めた財務三表を総合的に見ることが重要なのです。
Q: 中小企業でもキャッシュフロー計算書は作った方がいいですか?
A: 法的な作成義務がない場合でも、経営管理上、作成することを強くお勧めします。
キャッシュフロー計算書は、会社のリアルな資金繰り状況を把握し、将来の資金ショートリスクを予見するために非常に有効です。特に、次のような企業には必須と言えます。
- 成長期の企業(売上増加に伴い運転資金需要が高まる)
- 季節変動が大きい業種(資金の波が大きい)
- 在庫を多く抱える業種(小売、卸売、製造業など)
- 設備投資を計画している企業
- 借入金が多い企業
作成方法としては、顧問税理士に相談するか、freeeやマネーフォワードといった対応している会計ソフトを使えば比較的簡単に作成できます。難しければ、簡易的な資金繰り表(入出金管理表)から始めるのも一つの方法です。
Q: 財務分析の指標がたくさんありますが、初心者はまず何を見ればいいですか?
A: 初心者の方は、まず3つの基本指標に注目することをお勧めします。
- PLの「営業利益」:
本業での稼ぐ力を示す指標です。これが継続的にプラスかどうか、そして前年と比べて増加しているかどうかをチェックしましょう。営業利益率(営業利益÷売上高)で見ると、業種間の比較も可能です。 - BSの「自己資本比率」:
会社の安全性を示す指標です。純資産÷総資産で計算し、一般的には20%以上あれば一応安心できるレベルとされています。 - 可能ならCFの「営業キャッシュフロー」:
本業での現金創出力を示します。これがプラスかマイナスか、そしてプラスならその金額が十分かどうかを確認しましょう。
これらの指標を毎月または四半期ごとにチェックし、推移を見ることで、会社の状況を大まかに掴むことができます。慣れてきたら、売掛金回転期間や在庫回転期間、固定比率などの指標も見ていくと良いでしょう。
指標はあくまでも道具です。「なぜこの数字になっているのか?」「どうすれば改善できるのか?」を考えることが重要です。
まとめ
今回は、財務三表(PL・BS・CF)の基本的な読み方から、それらを経営に活かすためのポイントまでを解説しました。
PLで儲けを確認し、BSで会社の体力(財産と借金のバランス)を把握し、CFでお金の流れをチェックする。
この3つをセットで見ることで、初めて会社の本当の姿が見えてきます。
「数字は苦手」と感じていた方も、まずは自社の決算書を手に取り、この記事で紹介したポイントを一つずつ確認してみてください。
私は銀行員時代に、財務諸表を読めずに失敗した企業をたくさん見てきました。
一方で、数字をしっかり把握し経営判断に活かせている企業は、不況下でも着実に成長を続けていました。
その違いは「財務諸表を読む力」にあったのです。
財務諸表は、決して難しいだけの書類ではありません。
読み解く力を身につければ、それはあなたの会社をより強く、より成長させるための強力な武器となります。
今日からできる小さな一歩を踏み出し、自信に満ちた経営判断を目指しましょう。
もし具体的な分析方法や改善策で迷ったら、税理士や中小企業診断士への相談も検討してみてください。
また、この記事が少しでもお役に立ったなら、ぜひ周りの経営者の方にもシェアしていただければ幸いです。
皆さんの会社が財務面でも強固になり、持続的な成長を実現できることを心より願っています。


🔄 明日の資金繰りを今日解決する最短ルート
┗ 最短3時間での資金調達を実現
┗ キャッシュフロー改善に特化した専門提案
┗ 経営危機を未然に防ぐ資金戦略サポート
【売掛金を即現金化】ファクタリングで資金繰りの不安を解消