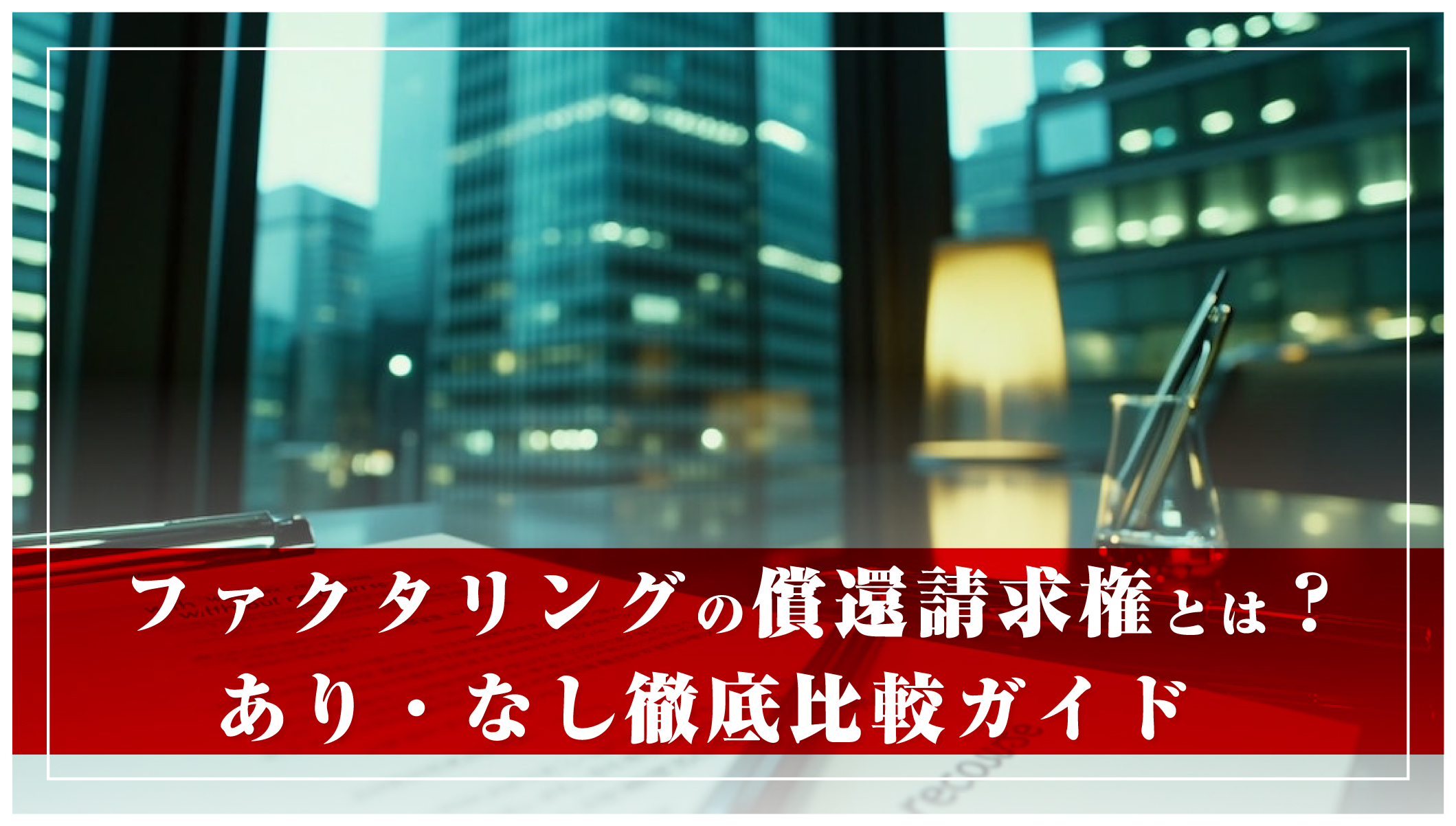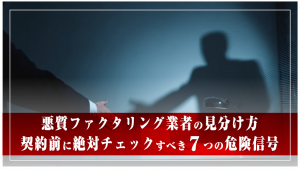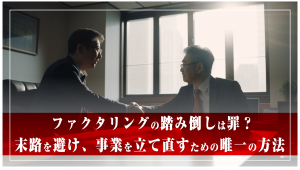「ようやく確保したキャッシュが、一夜にして“返済義務”へと姿を変える――。」
そんな悪夢を避ける最短ルートは、ファクタリング契約書のわずか三文字『償還請求権』を正しく読み解くことにあります。
本記事を読めば、
- 償還請求権あり/なしが自社のリスクと手数料をどう左右するか
- 2024年改正法・最新判例がファクタリング実務に与えた影響
- 実例に学ぶ“助かった企業”と“破綻した企業”の分かれ道
――これらを5分で把握し、次の資金調達を“安心して選べる状態”になれます。
結論から言うと、倒産リスクが読めない時代には「ノンリコース(償還請求権なし)」を基本線に、スピード・コスト・信用影響を総合比較することが最も安全かつ効率的です。
20年以上にわたり中小企業500社超の資金繰りを支援してきた筆者が、契約条文のチェックポイントから優良業者の見極め方まで、現場目線で徹底解説します。
さあ、“返済義務”という地雷を踏まずに、確実にキャッシュを守る方法を一緒に確認しましょう。

📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化

🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
償還請求権とは?ファクタリングの基本を押さえよう
債権譲渡の仕組みと法律上の位置づけ
まず押さえておきたいのが、ファクタリングの基本的な構造です。
ファクタリングとは、売掛債権(=未回収の請求書)を第三者に売却して、早期に現金化する仕組みです。
金融機関からの融資とは異なり、借入ではなく「売却」である点が大きな特徴です。
この仕組みは、民法466条以降に定められる「債権譲渡」規定に基づいています。
さらに2020年の民法改正により、「譲渡禁止特約」がある請求書であっても、債権譲渡そのものは法的に有効となりました(ただし、対抗要件の整備が必要です)。
また、ファクタリングは貸金業法の「融資」とは異なるため、通常は貸金業登録の対象外となります。
 山田 麻里
山田 麻里ただし、実質的に“返済義務あり”の契約(償還請求権あり)であれば、東京地裁では“実質融資”と判断され、貸金業法違反とされた判例もあります。(2024年3月判決)
🔍 図解:ファクタリングの構造
[あなた(売掛債権保有者)]
↓ 債権売却
[ファクタリング会社]
↓ 回収
[売掛先(顧客)]要約:ファクタリングは“請求書の売却”という合法的な資金調達手段。ただし契約形態によっては“実質融資”扱いになるリスクもある。
ウィズリコースとノンリコースの定義
ファクタリング契約を理解する上で最も重要なのが、「償還請求権の有無」です。
これは、売掛先が支払不能になった場合に、あなた(債権売却者)がその分を補填する義務があるかどうかを示しています。
- ウィズリコース(償還請求権あり)
→ 売掛先が支払わなければ、あなたが返済義務を負う - ノンリコース(償還請求権なし)
→ 支払不能でも返済義務なし(=リスクは業者側)
この違いは“買戻し特約”の有無で明確にされることが多く、契約書の中に「債務不履行時には原契約者が買戻す」旨の条項があれば、それはウィズリコースとみなされます。
✅ チェックポイント
- 「買戻し特約あり」→償還請求権付き
- 「ノンリコース型」と明記あり→返済義務なし
- 不明な場合→必ず問い合わせを!
要約:「償還請求権あり」は返済義務がある契約。「なし」はリスクを業者に移転できる安心設計。
手形割引・銀行融資との違い
ファクタリングと似た仕組みとして、「手形割引」や「銀行融資」が挙げられます。
ここでは、それぞれの違いを簡潔に整理します。
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 | 銀行融資 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 売掛金 | 約束手形 | 信用と担保 |
| 返済義務 | なし(ノンリコースの場合) | 基本的にあり | あり |
| スピード | 最短即日 | 数営業日〜 | 1〜2週間以上 |
| 登記 | 必要な場合あり | 原則不要 | 原則不要 |
| 審査 | 売掛先の信用中心 | 手形発行者の信用 | 自社の信用力 |
要約:銀行融資は自社の信用に依存。手形割引は支払い不能時の返済義務が重く、ファクタリング(ノンリコース型)はスピードとリスク回避を両立できる手段。
2社間・3社間ファクタリングと償還請求権の関係
3社間:基本はノンリコース、低コストだが通知必須
ファクタリングには大きく分けて「2社間取引」と「3社間取引」の2種類があります。
その違いを理解することが、償還請求権のリスクを回避する第一歩です。
まず3社間ファクタリングとは、以下のような構造です。
【登場人物】
・あなた(債権保有者)
・売掛先(顧客)
・ファクタリング会社(債権買取業者)
【取引の流れ】
1. 売掛金をファクタリング会社に売却
2. 売掛先にも債権譲渡を通知・承諾してもらう
3. 売掛先がファクタリング会社に直接支払うこの方式では、売掛先がファクタリング会社に直接支払うため、代金回収リスクを業者側が負担しやすく、原則としてノンリコース契約が適用されます。
その分、手数料も低め(2〜9%程度)に抑えられるのがメリットです。
ただし、デメリットもあります。
売掛先への通知・承諾が必須となるため、「資金繰りが厳しいのか?」と誤解される可能性があるのです。
そのため、取引先との関係性が良好で、信頼に自信がある事業者向けのスキームと言えるでしょう。
要約:3社間は原則ノンリコースで低コストだが、売掛先通知が必須。信用に影響を与える可能性も。
2社間:スピード重視だが条件が厳しくコスト高
一方、2社間ファクタリングは、ファクタリング会社とあなた(債権売却者)の間でのみ完結する取引です。
売掛先には債権譲渡の通知を行わず、あくまで元の取引通り、あなたの口座に入金されます。
【取引の流れ】
1. 売掛金をファクタリング会社に売却
2. 売掛先には通知しない
3. 売掛先があなたに支払 → あなたが業者に送金この構造では、ファクタリング会社は回収をあなたに依存することになるため、リスクが高くなります。
その結果、以下のようなデメリットが生じます。
- 手数料が高額(8〜18%以上も)
- 償還請求権あり(ウィズリコース)契約になりやすい
- 債権譲渡登記(資金調達バレ)の必要性
- 二重譲渡(他社にも売る)リスクへの対応費用が発生
とはいえ、審査が緩く、最短即日で資金化できる点は大きな魅力です。
取引先との関係に配慮したい事業者や、時間的余裕がない資金繰りには向いています。
要約:2社間はスピード優先・通知不要だが、リスクが大きく手数料も高額になりやすい。償還請求権付き契約が多いため注意が必要。


医療・介護報酬ファクタリング等の特殊スキーム
一般企業のファクタリングと別枠で考えるべきが、医療・介護報酬ファクタリングです。
これは、診療報酬や介護報酬などの公的債権(国保連や社保支払基金から支払われる確実な債権)を対象としたスキームです。
この分野では以下のような特徴があります。
- 売掛先が公的機関のため支払遅延リスクがほぼゼロ
- 原則3社間・ノンリコース契約
- 手数料も0.8〜2%と極めて低い
また、医療機関・介護事業者の資金繰りには月末入金のギャップがあり、このスキームは継続的なキャッシュフロー確保に役立っています。
要約:医療報酬ファクタリングは超低リスク・低コスト。特定業種向けの優れた資金調達手段。
償還請求権あり vs なし:メリット・デメリット徹底比較
コスト(手数料)とリスクのトレードオフ
ファクタリングを選ぶ際、多くの方が真っ先に注目するのが「手数料の違い」です。
しかし、表面上の数字だけで判断すると、リスクの所在という最も重要なポイントを見落とす危険があります。
以下の表をご覧ください。
| 比較項目 | 償還請求権あり(ウィズリコース) | 償還請求権なし(ノンリコース) |
|---|---|---|
| 返済義務 | 売掛先が支払不能 → あなたが返済 | 原則、あなたの返済義務なし |
| 手数料相場 | 8〜18%(2社間) | 1〜9%(3社間) |
| リスク負担者 | あなた(債権売却者) | ファクタリング会社 |
| 審査基準 | 売掛先+あなたの信用 | 売掛先の信用が中心 |
| 融資判定リスク | 実質融資と見なされる可能性あり | 原則なし(合法的債権売却) |
このように、「償還請求権あり」は手数料が抑えられる反面、倒産や未回収のリスクを“あなた自身が背負う”契約です。
一方、ノンリコース型は手数料がやや高くなることもありますが、万が一の時も返済義務がないため、精神的・財務的リスクが抑えられます。
要約:手数料の安さは魅力だが、「万が一」の返済義務こそが償還請求権の本質。表面的なコスト比較ではなく、“誰が最後に責任を取るのか”を確認すべき。


財務への影響とオフバランス効果
ファクタリングの大きなメリットの一つが、「バランスシートを圧迫しない」という点です。
特にノンリコース契約であれば、債権が完全に売却されたとみなされ、負債計上が不要=オフバランス処理が可能です。
🔍 オフバランスの効果とは?
- 自己資本比率の維持:借入を増やさずに資金調達ができるため、銀行格付けにも好影響
- 信用情報への影響が少ない:借入履歴が残らず、将来の融資申請にもプラス
- 資金調達余力を確保できる:借入枠を使わずに運転資金を確保可能
ただし、ウィズリコース契約では「将来的な返済義務が残る可能性」があるため、監査法人や金融機関によっては“オフバランスとして認められない”ケースもあるため要注意です。
要約:ノンリコース契約は本来のファクタリングメリットである「財務健全性向上」を最大限に活かせる。一方、ウィズリコースではこの効果が薄れる可能性がある。
こんな場合は「あり」でもOK/「なし」が必須
すべてのケースでノンリコースが正解とは限りません。事業フェーズや信用状況、売掛先との関係性によっては「償還請求権あり」でも現実的な選択肢となります。
✅ 「あり」でもOKなケース
- 資金調達スピードを最優先したい(明日までに払いたい請求がある)
- 売掛先の与信に自信があり、支払遅延のリスクが極めて低い
- ノンリコース審査で落ちたが、やむを得ず2社間で進めたい
- 短期的な資金不足で、一時的な利用に限る
✅ 「なし」が必須なケース
- 複数取引先からの入金にバラツキがあり、支払い遅延の可能性がある
- 自社のキャッシュフローに余裕がない(返済が困難)
- オフバランス化で銀行格付けやM&A準備を進めたい
- 過去にファクタリングでトラブルを経験している
要約:自社や売掛先の信用状況、調達の目的に応じて判断を分けるべき。安さ重視なら“あり”も検討余地ありだが、リスク回避を最優先するなら“なし”が原則。
契約前に必ず確認!チェックリストと注意点
契約書のキラーワード10選
ファクタリング契約において、トラブルの多くは「契約書の読み飛ばし」から始まります。
とくに注意すべきは、償還請求権の有無を間接的に示す“キラーワード”の存在です。
以下は、契約書でよく見かける注意ワード10選です。
| 用語 | 意味・リスク | 判断目安 |
|---|---|---|
| 買戻し特約 | 売掛先が支払不能時、債権を元の売主が買戻す | 償還請求権あり(確定) |
| 違約金 | 契約内容に違反した場合の高額ペナルティ | 計算方法と上限の明記要確認 |
| 遅延損害金 | 送金遅れ等で追加利息が課される | 年率計算で高額請求の恐れ |
| 表明保証条項 | 売掛金の存在や適格性を“保証”させる | 売掛先の瑕疵で損害賠償の対象に |
| 回収不能時の責任 | 回収不能=売主が全額返金の義務 | 償還請求権ありに該当する恐れ |
| 債権譲渡通知の猶予 | 「通知は後日」と曖昧な表現 | 二重譲渡トラブルの温床 |
| 債権の真実性担保 | 売掛債権が架空・重複ではないことを保証 | 故意過失問わず賠償義務が発生 |
| 期限の利益喪失 | 一部違反で契約全体が即時解除される | 一括返金のトリガーとなる可能性 |
| 抵当条項/連帯保証 | 自社資産や代表者個人に保証責任を課す | 実質融資・貸金業法違反の疑いも |
| 反社条項 | 反社会的勢力と関係があると一方的解除 | 調査方法・定義が不明確な場合も |



これらの文言が1つでも含まれていたら、「ウィズリコースの可能性あり」として専門家チェックを受けましょう。
要約:契約書にはリスクを“あなた側に押し付ける条項”が潜んでいることが多い。「償還請求権なし」の明記があるかどうかが最重要ポイント。
手数料以外の隠れコストを見抜く方法
「うちは10%って言われたから大丈夫」と安心している方、その“10%”に何が含まれているか、ちゃんと確認しましたか?
ファクタリングには、表面上の手数料とは別に、次のような“隠れコスト”がかかることがあります。
| コスト名 | 内容 | 発生の有無・目安 |
|---|---|---|
| 登記費用 | 債権譲渡登記にかかる実費・手数料 | 数万円〜10万円前後(2社間で多い) |
| 事務手数料 | 書類審査・契約対応等の固定費 | 1万〜3万円/件程度 |
| 振込手数料 | 入金時の振込コスト(片道・往復) | 数百〜数千円 |
| 着金スピード手数料 | 即日対応オプション費用 | 追加2〜5%の場合も |
| 解約違約金 | 途中キャンセル時の補償費用 | 5万円〜数十万円のケースあり |
| 二重譲渡リスク保証料 | 他社への譲渡を防ぐための保険的コスト | 手数料に上乗せ |
📝 確認すべき質問リスト
- 「手数料◯%に登記費用は含まれていますか?」
- 「送金手数料はどちらが負担しますか?」
- 「事前見積書に全ての費用が網羅されていますか?」
要約:手数料“以外”のコストが最終的な負担を左右する。「総コストで比較する」姿勢がリスク回避の第一歩。
優良ファクタリング会社を選ぶ7つの指標
最後に、「契約する前に見極めたい」優良業者の見抜き方を7つの視点から紹介します。
- 登録・認可の有無:貸金業登録や財務局登録などの開示があるか
- 取引実績と業歴:法人登記情報・HPでの開示内容を確認
- 契約書の説明責任:契約条項を細かく説明してくれるか
- 料金体系の透明性:手数料以外のコストが明示されているか
- 利用者の口コミや評判:GoogleレビューやSNSの実体験が参考に
- 法人名義・電話番号が正確か:携帯番号・個人名義の業者は避ける
- 相談時の対応姿勢:リスクを説明せず契約を急がせる業者はNG
📌 診断ポイント
- 営業資料やHPで「ノンリコース明記」があるか?
- 質問に答えず「今すぐ契約」と迫ってこないか?
要約:ファクタリング業者選びは“価格”だけでなく“態度”も見るべき。あなたの不安に誠実に応える会社こそ、長期的に付き合えるパートナー。
ケーススタディ:成功例と失敗例から学ぶ
ファクタリング契約は、「契約書にサインするだけ」のように見えて、その中身によって天と地ほどの差が生まれます。
ここでは、実際に起きた成功・失敗の2事例をもとに、「償還請求権の有無」が経営に与えるインパクトを解説します。
成功例:取引先A社倒産でも連鎖倒産を回避
業種:建設業(下請け中小企業)
売掛先:中堅ゼネコンA社(年商50億円)
売掛金額:約900万円
ファクタリング方式:3社間・ノンリコース契約
手数料:3.5%
シナリオ
建設業B社は、支払いサイトが長いゼネコンA社からの売掛金約900万円をノンリコース契約でファクタリング会社に譲渡。譲渡通知も完了し、数日後に資金調達が実行されました。
ところが翌月、A社が急な資金ショートで倒産。A社は弁済不能となり、本来ならその分の売掛金は未回収となるところでした。しかしB社は、ノンリコース契約だったため返済義務はゼロ。そのおかげで資金繰りが維持され、従業員の給与や仕入れ費用も確保。連鎖倒産を回避できました。
学び:売掛先の信用力が高くても「絶対」はない。ノンリコース契約は“万が一”への最善の備えになる。
失敗例:ウィズリコース契約で追加返済を迫られたB社
業種:EC事業(中小スタートアップ)
売掛先:大手ネットモール運営会社
売掛金額:500万円
ファクタリング方式:2社間・ウィズリコース契約
手数料:9.8%+事務手数料3万円
シナリオ:
資金繰りが急迫していたEC事業者のC社は、月末の仕入れ資金を確保するため、即日対応のファクタリング会社と契約。担当者から「この方式なら早くお振込できます」と勧められ、細かい条項を確認しないまま契約書にサインしました。
結果、3営業日後に500万円が入金されましたが、翌月、売掛先のモール側で「与信トラブル」により支払いが遅延。ファクタリング会社はC社に対し、「買戻し特約に基づき、速やかに返済を」と請求。
C社は資金に余力がなく、すぐに返済ができずに遅延損害金が加算。最終的に、年利換算で200%超の実質金利となり、返済が困難に。最終的に内容証明と訴訟に発展し、経営は事実上破綻しました。



「償還請求権あり」の契約では、入金=終わりではない。“返済義務がない”ことを確認せずに契約すると、後々取り返しがつかないリスクになります。
学びのポイント|トラブルを防ぐ3つの鉄則
両事例から明確になった教訓は、以下の3点です。
- 契約内容を“速度優先”で決めない → 即日入金の魅力に惑わされず、契約条項を理解して判断を。
- 償還請求権の有無を必ず確認 → ノンリコースと書かれていない=基本的に返済義務ありの可能性大。
- 専門家や複数社への見積もりを必ず取る → 「最初に相談した1社」だけで決めないこと。違約金条項も含めて比較。
📌 今すぐできるチェックリスト
- 「ノンリコース」と契約書に明記されているか?
- 「買戻し特約」や「違約金」の条項があるか?
- 他社の見積書と比べて割高・不明点がないか?
要約:実例を通して分かるのは、契約前の“たった5分の確認”が、数百万円規模の損得を分けるということです。
よくある質問(FAQ)
ファクタリングを検討される経営者や個人事業主の方から、筆者がこれまでに最も多く受けた質問を、実務経験に基づいてわかりやすく解説します。
Q1:償還請求権なしでも、売掛先が支払わなかった場合、本当に返済義務はゼロですか?
A:原則として返済義務は発生しません。ただし“完全ノンリコース契約”であることが条件です。
ノンリコース契約の場合、売掛先が倒産・未払いに陥っても、あなたに返済義務は生じません。これは、売掛債権の回収リスクをファクタリング会社が引き受ける契約だからです。
しかし注意すべきは、契約条項の中に“表明保証違反”や“送金遅延に伴う損害賠償”といった例外規定があること。たとえば、以下のようなケースでは追加請求されることがあります。
- 売掛債権が実在しない/二重譲渡されていた
- 契約時に重要な情報を隠していた(虚偽申告)
- 売掛先への入金を自己都合で遅延・留保した
✅ チェックすべき文言例:「債権の真実性担保」「虚偽申告時の損害賠償」「債務者支払拒絶時の補填義務」
補足:ノンリコースはあくまで「支払不能時に備える保険」。契約内容と事実関係によっては義務が発生する場合があるため、契約書の文言は最後まで確認を。
Q2:手数料◯%は高すぎ?適正相場を見極める基準は?
A:契約形態や業種・信用力によって異なりますが、以下がひとつの目安です。
| ファクタリング形式 | 手数料相場(2025年時点) |
|---|---|
| 3社間(ノンリコース) | 2〜9% |
| 2社間(ウィズリコース) | 8〜18% |
| 医療・介護報酬型(3社間) | 0.8〜2% |
これらの数値はあくまで平均的な目安であり、以下の要素によって上下します。
- 売掛先の信用力(上場企業・公的機関=手数料が低い)
- 債権の回収時期(回収までの期間が短いほど安くなる)
- 自社の財務状況(赤字・債務超過なら割高になる)
また、「手数料◯%」と一口に言っても、登記費用・事務手数料・オプション費などが含まれていないケースも多いため、総コストで比較することが重要です。
補足:「安さ」を最優先した契約は、後から追加費用が発生することも。費用構成をすべて確認しましょう。
Q3:債権譲渡登記をすると、取引先に知られてしまいますか?
A:公示情報になるため、調べれば分かる可能性があります。ただし即通知されるわけではありません。
債権譲渡登記とは、「この債権は譲渡されました」と法務局に登録する手続きであり、登記簿謄本を取得すれば誰でも閲覧できます。そのため、売掛先が調査すれば気付く可能性があることは事実です。
登記の目的は主に2つあります。
- 二重譲渡を防止するための対抗要件
- ファクタリング会社の保全手段
特に2社間ファクタリングでは、売掛先に通知ができない分、登記で保全するのが通例です。
✅ 登記を避けたい場合の選択肢
- 3社間ファクタリングに切り替える
- 「通知型」ファクタリングを選ぶ(登記より通知で対抗)
- ノンリコースで売掛先承諾を得る
補足:「登記=即バレる」ではないが、可能性はゼロではない。信頼関係に影響を与える場合は慎重に。
まとめ|“手数料”よりも“リスク”に目を向けよう
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
この記事では、ファクタリング契約における「償還請求権のあり・なし」の違いを軸に、その仕組み・リスク・判断基準を整理してきました。
最後にもう一度、押さえておくべき要点を振り返っておきましょう。
🔑 要点チェックリスト
- 償還請求権あり(ウィズリコース)は手数料が安くても、支払い不能時は自社が返済義務を負う
- 償還請求権なし(ノンリコース)なら、万が一の際も返済不要でリスク回避に最適
- 契約書では「買戻し特約」「遅延損害金」「違約金」などの文言に要注意
- 手数料以外の隠れコスト(登記費用・送金手数料など)も比較の対象にすべき
- 業者選びでは、「説明責任」「契約条項の明示」「評判・実績の確認」が重要
- 成功事例では、ノンリコースで連鎖倒産を回避。失敗事例では、返済不能から訴訟・経営破綻へと発展
🎯 今すぐ実践したい3つのアクション
- 契約前に「償還請求権」の有無を必ず確認し、ノンリコースの明記を探す
- 2社以上の見積もりを取り、手数料・総コスト・契約条件を比較
- 資金調達目的と売掛先の信用力に応じて、最適な方式を選択する


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化