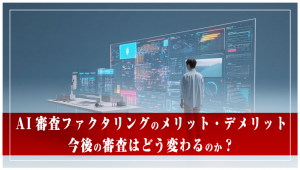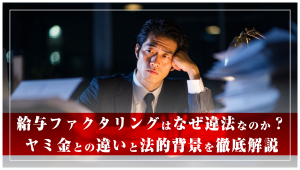「明日の支払いが足りない……」
これは、私がコンサルタント時代に何度も耳にした中小企業経営者の悲痛な声です。
売掛金はある。仕事も順調。でも、「回収は1カ月後」。
資金繰りに余裕がない企業にとって、そのタイムラグこそが最大の敵でした。
そんな現場で活用されていたのが「ファクタリング」という資金調達の手段。
特に利用されていたのが、現金化を目的とする「買取型」と、貸倒リスクの回避を目的とする「保証型」の2つです。
 山田 麻里
山田 麻里この2つ、目的も仕組みもまったく異なります。
にもかかわらず、混同されやすく、間違った使い方によって「こんなはずじゃなかった」という事態に陥るケースも少なくありません。
【この記事の結論】買取型と保証型の違いが一目でわかる比較表
| 項目 | 買取型ファクタリング | 保証型ファクタリング |
|---|---|---|
| 目的 | 「今すぐの資金調達」 (売掛金を前倒しで現金化) | 「将来のリスク対策」 (売掛先の倒産に備える保険) |
| 資金化のタイミング | 最短即日〜数日 | 資金化はなし (倒産時に保証金が支払われる) |
| 手数料の目安 | 2社間:10〜20% 3社間:3〜8% | 1〜8%(掛け捨て) |
| 審査の対象 | 主に「売掛先」の信用力 | 主に「自社」の信用力 |
| こんな時に | 「急な支払いがある」「融資を断られた」 | 「大口取引先が不安」「新規取引に備えたい」 |
本文では、それぞれの仕組みや会計処理の違い、ケース別の使い分け方をさらに詳しく解説します。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
ファクタリングの基本と「買取型」「保証型」2つの形態
ファクタリングとは何か|「売掛金を資金化または保証する」手段
ファクタリングとは、売掛債権(納品済み・請求済みだが未入金の取引)を、金融機関や専門業者を通じて「早期に現金化する」あるいは「未回収リスクを保証する」手段のことです。
📘 図解|ファクタリングの全体像
【通常の売掛取引】
受注 → 納品 → 請求 → 入金(30〜60日後)
【ファクタリング導入時】
受注 → 納品 → ファクタリング会社に請求書提出
→ 数日以内に資金化(買取型) or 債権保証(保証型)特に中小企業では、売掛金の回収待ちが資金繰りの足かせになることが多く、ファクタリングは「資金繰りを支える安全弁」として重宝されています。
✔️ 要約: ファクタリングは、売掛金を「今使えるお金」に変えるか、「貸し倒れから守る」仕組みです。
買取型と保証型の違い|「前払い」か「保険」か
ファクタリングには大きく分けて次の2種類があります。
| 項目 | 買取型ファクタリング | 保証型ファクタリング |
|---|---|---|
| 概要 | 売掛債権を売却し現金化 | 売掛債権の支払保証を得る |
| 資金調達効果 | あり(即日〜数日で入金) | なし(入金は通常通り) |
| リスク対応 | 倒産リスクを回避(ノンリコース) | 貸倒時に保証会社が補填 |
| 会計処理 | 売掛債権の売却処理 | 保証料の費用処理/保証収入 |
| 活用目的 | 資金繰り対策 | 与信リスク対策・債権管理 |
買取型は、「お金が今すぐ必要」という時に非常に有効です。
一方で保証型は、取引先が万一支払い不能になった際に損失を最小限に抑える「保険的な使い方」がされます。
つまり、
「資金繰りが目的」なら買取型、
「信用リスクの回避」が目的なら保証型
という使い分けが基本となります。
買取型ファクタリングの特徴と注意点
仕組みと流れ|売掛債権を売って即資金化
買取型ファクタリングは、未回収の売掛金(請求済みだが未入金)を、ファクタリング会社に「売却する」ことで、即時の資金化を実現する仕組みです。
売却後、ファクタリング会社が取引先(売掛先)から直接回収するか、間接的に回収を行うことで、債権を消化します。
契約形態には大きく分けて以下の2つがあります。
| 契約形態 | 特徴 | 通知の有無 |
|---|---|---|
| 2社間ファクタリング | 利用企業とファクタリング会社の間で契約 | 通知なし(ただし登記ありの場合あり) |
| 3社間ファクタリング | 利用企業・取引先・ファクタリング会社の3者で契約 | 通知あり(取引先承諾が必要) |
🔁 買取型ファクタリングの流れ(2社間の場合)
- 請求書など売掛債権の提出
- 審査(数時間〜1日程度)
- ファクタリング会社から売掛金の80〜95%が即入金
- 売掛先からの入金が後日ファクタリング会社に届く
- 残額(手数料を差し引いた分)が精算される
✔️ 要約: 買取型ファクタリングは、売掛債権を即日〜数日で資金化できる仕組み。通知の有無によって契約形態が異なる。


メリットと活用場面|「今すぐ現金が必要」を救う最短手段
買取型ファクタリングの最大の魅力は「スピード」です。
最短で申込当日に入金されるケースも珍しくなく、赤字企業や創業間もない企業でも利用可能です。
✅ 主なメリット
- 即日〜3営業日で入金可能
- 担保や保証人が不要(信用力に依存しにくい)
- 赤字や債務超過でも利用できる(銀行融資に代わる手段)
- 取引先に通知不要(2社間の場合)
🧩 活用事例|飲食業A社(赤字・2社間利用)
都内の飲食店チェーンA社は、コロナ禍の影響で赤字が続き、融資審査が通らない状態に。
売掛先に対する200万円の請求書を使い、クラウドファクタリングで即日170万円を調達。
従業員給与と仕入資金に充て、経営を持ち直すきっかけとなった。
✔️ 要約: 銀行融資が難しい局面でも、即時の資金調達が可能な手段として買取型は非常に有効。
デメリットとリスク|手数料と信頼性に注意
一方で、買取型には以下のような注意点もあります。
⚠️ 主なデメリット・リスク
- 手数料が高い(2社間で平均10〜20%)
- 悪質業者による法外な手数料や違法契約のリスク
- ノンリコース(償還請求権なし)でも登記や通知により取引先に知られる可能性
- 会計処理が煩雑になる(売掛債権の売却仕訳)


❗️要注意:債権譲渡登記の影響
ファクタリング会社が債権の優先権を確保するため、債権譲渡登記を行うことがあります。
この登記情報は取引先にも知られる可能性があり、信用不安を招く恐れも。
📌 業者選びのポイント
- 金融庁や業界団体の登録事業者を選ぶ
- サービス料・手数料・契約条項の内訳を明示しているか
- レビュー・事例の豊富な会社(例:OLTA、QuQuMo、ビートレーディング)
✔️ 要約: 即時性の高さと引き換えに、手数料負担や契約リスクがある。業者選びが命。
次章では、「保証型ファクタリング」について、仕組みや活用メリット、注意点を詳しく見ていきます。
保証型ファクタリングの特徴と注意点
仕組みと流れ|「保険」のように債権を守る
保証型ファクタリングは、取引先の倒産や支払い遅延に備え、売掛債権に対して保証をかける仕組みです。
このサービスは、与信管理や貸倒リスクのアウトソーシングとして利用され、資金調達効果はありません。
🔄 保証型ファクタリングの流れ
- 利用企業が売掛先との取引条件を保証会社に提示
- 保証会社が取引先の与信審査を実施
- 承認後、保証契約が締結され、保証料(1〜8%)を支払う
- 万が一、取引先が期日に支払えない場合、保証会社が立替払い
この立替金は「保険金」のような扱いで、企業にとっては損失回避策になります。
✔️ 要約: 保証型は、取引先が倒れたときの“最後の砦”。お金は先に入らないが、リスクを大幅に軽減できる。
メリットと活用場面|倒産リスクを外部に移せる
保証型の最大の魅力は、信用不安のある取引先と安心して商談ができることです。
✅ 主なメリット
- 売掛債権の貸倒リスクをゼロに近づけられる
- 与信管理をアウトソースできる(自社のリスク管理体制強化)
- 取引先への通知が不要(※条件による)
🧩 活用事例|部品製造業B社(年間売上20億円)
自動車部品メーカーB社は、売上の7割を占める大手1社との取引に依存していた。
その大手の業績が悪化し、不安を感じたB社は保証型ファクタリングを導入。
結果として、約5,000万円分の売掛債権に保証がつき、安心して取引を継続できた。
大企業でも中堅企業でも、「万が一」の事態は起こり得ます。保証型は、その“予期せぬ倒産”による大損害を防ぐ”バリア”となります。
✔️ 要約: 保証型は、経営上の信用リスクをカバーし、安心して取引を続けるための武器。
デメリットとリスク|資金化されない点に要注意
即時資金化が可能な買取型と異なり、保証型ファクタリングにはいくつかの制限と注意点があります。
⚠️ 主なデメリット
- 資金調達効果はゼロ(売掛金は通常通り回収)
- 保証料が発生(1〜8%は掛け捨て)
- 審査基準が厳しく、新興企業や赤字企業は通らない場合も
- 回収不能が保証対象外になるケースもある(取引形態や期日遅延等)
❗️ 利用時の要注意ポイント
- 保証対象外の取引条件(前払い/特殊業態など)がないか確認
- 保証上限額と免責額の有無をチェック
- 契約書に記載されている免責事項・通知義務を見落とさない
✔️ 要約: 資金化はできないが、信用不安には効果絶大。保証内容の条件確認が重要。
比較の視点が変わる|資金繰りとリスクヘッジは分けて考える
ここまでの説明でお分かりの通り、「お金を今使いたい」か、「万が一に備えたい」かで、選ぶべきファクタリングの形は180度異なります。
✔︎ 緊急の資金繰り:買取型
✔︎ 取引先の信用不安:保証型
この前提を踏まえ、次章では両者を徹底的に比較していきます。
両者の違いを徹底比較
手数料・コスト構造の違い|見えにくい“実質コスト”に注意
ファクタリングを比較する上で、まず注目すべきは手数料や費用構造の違いです。
| 項目 | 買取型ファクタリング | 保証型ファクタリング |
|---|---|---|
| 費用発生のタイミング | 債権売却時 | 契約時(保証料) |
| 手数料 | 2社間:10〜20% 3社間:3〜8% | 1〜8%程度(掛け捨て) |
| 実質的なコスト | 入金額が目減り | 現金支出だが、安心料 |
🔍 解説ポイント
- 買取型は、入金額から手数料が差し引かれるため「額面100万円 → 実入金85万円」などのイメージ。
- 保証型は掛け捨て費用であり、資金化はないが、「倒産時の保険料」と考えると納得感あり。
✔️ 要約: 買取型は「即キャッシュ確保」で高コスト、保証型は「将来リスクヘッジ」で低〜中コスト。
会計処理の違い|「売却」と「保証」でまったく異なる
会計処理の面でも、両者は明確に異なります。正確な仕訳処理を行わないと、税務署や金融機関から指摘を受けるリスクもあります。
| 項目 | 買取型ファクタリング | 保証型ファクタリング |
|---|---|---|
| 仕訳方法 | 売掛債権の売却処理 → 売掛金減少+売却損計上 | 保証料を費用計上 → 債権に変動なし |
| 例①(入金時) | 普通預金 950,000円 売掛債権売却損 50,000円 / 売掛金 1,000,000円 | 支払手数料 50,000円 / 普通預金 50,000円 |
| 例②(保証支払発生時) | 該当なし(既に債権売却済) | 雑収入 1,000,000円 / 売掛金 1,000,000円 |
✔️ 要約: 買取型は「債権を消す」処理、保証型は「保証料支出+損失補填時の収益」で処理。
リスクと債権管理の違い|ノンリコースと保証補填
ファクタリングは単なる資金調達だけでなく、信用リスクの管理ツールとしても重要です。
この観点で両者を見比べてみましょう。
| 項目 | 買取型ファクタリング | 保証型ファクタリング |
|---|---|---|
| リスクの所在 | ノンリコースなら倒産時も請求なし | 倒産時に保証金が支払われる |
| 管理の主導権 | ファクタリング会社が回収 | 利用者が引き続き回収管理(保証あり) |
| 債権管理の手間 | 減る(譲渡により) | 残る(債権は手元) |
❗ ノンリコース型の注意点
買取型でも「ノンリコース契約」であれば、取引先倒産時に利用企業が責任を負うことはありません。
ただし、通知や登記によって関係性が明らかになり、信用低下につながる懸念もあります。
✔️ 要約: リスクをどこまで外部化できるかがカギ。買取型は債権管理を丸ごと手放せる点が利点。
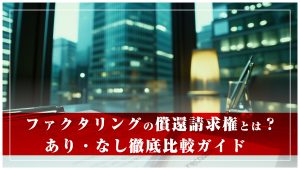
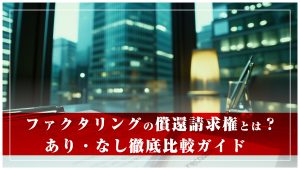
利用目的と適性の違い|“どんな企業に向いているか?”
最後に、目的別・企業別に向いているファクタリングの種類をまとめます。
| 利用目的 | 向いているファクタリング |
|---|---|
| 急な資金ショート | 買取型 |
| 融資が受けられない | 買取型(信用不問) |
| 取引先の信用に不安 | 保証型 |
| 新規取引開始時のリスク管理 | 保証型 |
| 債権管理の効率化 | 買取型(3社間) |
🧭 判断のポイント
- 今すぐ現金が必要 → 買取型一択
- 中長期的に信用リスクを抑えたい → 保証型で“安心”を買う
✔️ 要約: 利用目的が「資金確保」か「リスクヘッジ」かで選択肢が分かれる。
次章では、実際にどう使えばいいのか?
ケーススタディで「明日支払いたい」「大口取引先が不安」「併用できるの?」など、リアルな活用例を提示します。
ケース別の使い分けガイド
ケース1:明日中に支払いが必要 → 買取型ファクタリング
📌 シナリオ
「口座残高が50万円。明日中に100万円の外注費を支払わないと、仕事が止まる——」



こうした突発的な資金ショートに対しては、迷わず買取型ファクタリングが適しています。
💡 活用戦略
- 未回収の売掛債権(例:300万円)をファクタリング会社に提出
- 即日審査&入金(80%前後=240万円)
- 資金繰りの“詰み”を回避
✅ 成功事例:広告制作業・C社
月末に予定外の支出が重なり、資金がショート寸前に。
OLTAを利用し、請求書ベースで即日250万円入金。
取引先への通知もなく、翌日には支払いを完了。
✔️ ポイントまとめ:
- 即入金可能(最短2時間)
- 審査は売掛先の信用に依存
- 手数料は割高でも、緊急回避には有効


ケース2:大口取引先に不安がある → 保証型ファクタリング
📌 シナリオ
「年商1億のうち7,000万が、ある1社との取引。倒れられたら……終わりだ。」



こうした取引先集中型のリスクに対しては、保証型ファクタリングがベストです。
💡 活用戦略
- 大口取引先との契約内容を保証会社に提示
- 与信審査を経て、貸倒時に補償が得られる保証契約を締結
- 倒産時でも、売掛債権が保証される安心感
✅ 成功事例:精密機械部品メーカー・D社
メイン取引先である大企業の業績悪化が報じられ、不安に。
1,000万円超の売掛債権に保証型ファクタリングを導入。
その後、実際に支払い遅延が発生したが、90%が保証金で補填され、大きな損失を免れた。
✔️ ポイントまとめ:
- 貸倒リスク回避に最適
- 資金繰りには影響しない
- 事前審査の通過が前提
ケース3:資金繰りも守備も固めたい → ハイブリッド運用(併用型)
📌 シナリオ
「受注は好調。でも、資金の流れと信用不安、どちらも気になる。」



このような攻守バランス型の経営方針には、買取+保証のハイブリッド運用が適しています。
💡 活用戦略
- 中小の売掛債権(入金遅れがちな取引先)を買取型で即資金化
- 大口の主要取引先には保証型をかけて信用リスクを回避
- 資金繰りと信用管理を“分散化”して、経営の安定性を向上
✅ 成功事例:建設資材商社・E社
多数の現場を抱える中、毎月1,000万円単位の資金繰りが発生。
一部をQuQuMoで即時資金化しつつ、主要取引先には保証型を導入。
キャッシュの流動性と信用安定性を同時に実現した。
✔️ ポイントまとめ:
- 資金化対象と保証対象を分ける
- コストは増すが、全体のリスクヘッジは強化
- 仕訳・会計処理が複雑化するため、税理士の助言推奨
📋 チェックリスト|どっちが向いている?
| 質問 | YESなら… |
|---|---|
| いますぐお金が必要? | 買取型 |
| 取引先が不安? | 保証型 |
| 会計処理が複雑でも対応できる? | 買取型/併用型 |
| 銀行融資が難しい? | 買取型 |
| 今の取引にリスクヘッジをかけたい? | 保証型 |
よくある質問(FAQ)
Q1. ファクタリングを使うと、取引先にバレますか?
A:2社間ファクタリングであれば通知なしで利用可能です。
ただし、債権譲渡登記を行う場合は、登記簿から取引先に知られる可能性があります。
🔍 補足解説:
- 2社間:利用企業とファクタリング会社のみで契約 → 通知不要
- 3社間:取引先を含む契約 → 通知・同意が必要
取引先との関係性を重視する場合は、「登記不要型」や「非通知型」を選べる業者を検討しましょう。
Q2. 保証型ファクタリングは、どんな場面に向いていますか?
A:信用不安がある取引先や、新規取引の開始時に有効です。
特に以下のようなケースで効果的です。
- 売上の大半を1社に依存している
- 取引先の経営状況が不安定
- 新規契約だがリスクヘッジしておきたい
- 金額が大きく、貸倒が致命傷になる取引
倒産リスクの“地雷回避”として、保証型は有効な安全装置となります。
Q3. ファクタリングの手数料は経費になりますか?
A:はい、会計上は「支払手数料」や「売掛債権売却損」として経費計上が可能です。
📘 会計処理の概要
| 種別 | 勘定科目 | 備考 |
|---|---|---|
| 買取型 | 売掛債権売却損・支払手数料 | 債権の帳簿処理を伴う |
| 保証型 | 支払手数料・保証料 | 掛け捨ての費用処理のみ |
税理士によって科目の選定は異なる場合もありますが、いずれも損金処理(税務上の経費)が可能です。
Q4. 契約するファクタリング業者はどう選べばよいですか?
A:以下3点が必須条件です。
- 金融庁や業界団体の登録状況を確認(例:日本ファクタリング業協会)
- 手数料や契約条件を明示しているか(例:初期費用ゼロ、明示されたパーセンテージ)
- 利用者の口コミ・事例が豊富であるか(公式サイト・Googleレビュー・SNSなど)
また、「ノンリコースかどうか」「登記が必要か」なども重要な判断基準です。
Q5. ファクタリングって常用しても大丈夫?
A:一時的な資金繰りには有効ですが、常用は慎重に。
❗ 長期利用のリスク
- 高コスト体質が定着しやすい(手数料10〜20%が継続的に発生)
- 本質的なキャッシュフロー改善に結びつかない可能性
- 銀行や金融機関の融資判断に影響する場合もある
→あくまで“緊急用・補助的手段”としての活用が基本
中長期的には、売掛サイトの見直しやリース・融資との組み合わせを検討すべきです。
まとめ
ファクタリングには、買取型と保証型という2つの異なる手法があります。
それぞれの違いを整理すると、次のようになります。
🔑 ファクタリング比較一覧
| 項目 | 買取型ファクタリング | 保証型ファクタリング |
|---|---|---|
| 主な目的 | 資金繰りの即時改善 | 倒産リスクのヘッジ |
| 資金化 | ◎(即日~数日) | ×(入金なし) |
| 手数料 | 高め(10~20%) | 低~中(1~8%) |
| 会計処理 | 債権売却処理 | 保証料・雑収入処理 |
| 通知の有無 | 2社間は原則なし | 通知不要(審査次第) |
| 向いている企業 | 資金が急ぎの中小企業 | 与信リスクを抱える中堅~大手 |
🧩 自社に合った選び方
- 急な支払いに追われている → 買取型で即日入金を確保
- 主要取引先の信用が揺らいでいる → 保証型で安全網を張る
- 攻守のバランスを取りたい → 両方を目的別に使い分ける
✅ 今すぐやるべきことチェックリスト
🔲 売掛金の回収予定と支払予定を整理した
🔲 緊急資金 or リスク対策、どちらが優先か明確にした
🔲 信頼できるファクタリング業者を比較検討した
🔲 業者の「手数料」「契約条件」「登記の有無」を確認した
🔲 税理士または専門家と会計処理方針を相談した
本記事が、あなたの経営判断に少しでも貢献できたなら幸いです。
ファクタリングは決して“最後の手段”ではなく、“柔軟で戦略的な選択肢”です。
必要なときに、必要な形で使いこなし、キャッシュフローと信用リスクの両面から、より強い経営体制を構築していきましょう。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化