コロナ禍を何とか乗り越えたものの、いよいよゼロゼロ融資の返済が始まり、原材料高や人件費アップなど新たなコスト増にも直面し、再び資金繰りに頭を抱えていませんか?
私は中小企業向け金融コンサルティング会社に勤務後、独立したファイナンシャルライターの山田麻里です。
コンサル時代、数多くの中小企業の方々から「銀行からの追加融資が厳しい」「赤字決算が続いて融資が断られた」といった相談を受けてきました。
そんな状況で今、中小企業経営者の間で急速に注目を集めているのが「ファクタリング」です。
売掛金を早期に現金化できるこの手法は、コロナ後の資金調達環境の変化に対応する重要な選択肢となっています。
本記事では、ファクタリング需要が急拡大している理由や仕組み、そして融資以外の多様な資金調達の選択肢について、わかりやすく解説します。
読み終える頃には、きっと貴社に最適な次の一手が見えてくるはずです。

📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
ポストコロナで激変!中小企業を取り巻く資金調達の現状
ゼロゼロ融資返済開始と新たな資金繰り圧力
「そろそろゼロゼロ融資の返済が始まるけど、大丈夫かな…」
こんな不安を抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
コロナ禍で多くの企業が利用した実質無利子・無担保融資(通称:ゼロゼロ融資)の返済据置期間が終了し、いよいよ本格的な返済フェーズに入っています。
 山田 麻里
山田 麻里帝国データバンクの調査によると、コロナ関連融資を受けた企業の約9%が「返済に不安がある」と回答しています。
売上がコロナ前の水準に戻っていない企業も少なくなく、毎月の返済負担がキャッシュフローを圧迫するケースが増えているのです。
私がコンサルタント時代に支援した飲食業のA社は、月商800万円に対して、コロナ融資の返済だけで月50万円の負担。原材料費の高騰も重なり、手元資金が急速に減少していきました。
💡 ワンポイントアドバイス
返済に不安がある場合は、早めに金融機関に相談しましょう。返済条件の変更(リスケジュール)に応じてくれるケースもあります。
融資審査の厳格化?銀行に頼れない現実
「追加融資を申し込もうと思うんですが…」
このご相談、実はかなり厳しい状況になっています。
コロナ禍で一時的に緩和された融資審査ですが、ポストコロナでは再び厳格化の傾向にあります。特に以下のような企業は融資を受けるハードルが高くなっています。
銀行は基本的に「返済能力」を重視します。
赤字でキャッシュフローが厳しい企業に、さらに融資を行うことはリスクが高いと判断されるのです。
特に「コロナ融資で借入金が膨らみすぎている」「追加融資を断られた」という声をよく耳にします。
こうした状況では、融資以外の資金調達手段を検討する必要があるでしょう。
あなたの会社も融資に頼りきりになっていませんか?
実は、負債に頼らない資金調達の選択肢が注目を集めています。
なぜ今?ファクタリング需要が急拡大した3つの理由
理由1:緊急時の「つなぎ資金」としての圧倒的なスピード感
「来週までに仕入代金を払わないと、次の納品がストップしてしまう…」
こんな緊急事態、経営者なら一度は経験したことがあるのではないでしょうか。
銀行融資では通常、申込から実行まで数週間かかります。
でも、明日・明後日にお金が必要なケースもありますよね。
ファクタリングの最大の魅力は審査から入金までのスピードです。
最短即日〜3営業日程度で資金化できるケースも多く、急な資金需要に対応できます。
近年ではオンライン完結型のファクタリングサービスも登場し、より手軽に利用できるようになりました。
スマホやPCからWeb上で必要書類をアップロードし、オンライン審査で済ませるスタイルです。
対面での煩雑な手続きも省け、地方の企業にとっても大きなメリットになっています。
📊 データポイント
2023年のトレンドとして、オンラインファクタリングの普及率が高まっています。オンライン完結で最短即日入金を実現するサービスも増加中です。
理由2:融資以外の選択肢としての「利用しやすさ」
ファクタリングが注目されるもう一つの理由は、審査基準の違いにあります。
銀行融資が自社の財務状況(赤字・黒字、債務超過の有無など)を重視するのに対し、ファクタリングは主に「売掛先(債務者)の信用力」を審査します。
つまり、あなたの会社の財務状況が悪くても、取引先の信用が良ければ利用できる可能性が高いのです。



実際、ファクタリング会社の審査では、申込企業の決算書が赤字や債務超過であったり、税金滞納があったりしても、審査にはほとんど影響しません。
「融資を断られた企業の受け皿」として機能しているわけです。
もちろん、反社会的勢力でないことなどの基本的なチェックは行われますが、融資に比べるとハードルはぐっと下がります。
キャッシュフローが厳しい局面こそ、こうした選択肢を知っておくことが重要です。
あなたが今、資金繰りに悩んでいるなら、融資だけでなくファクタリングも検討してみる価値がありそうですね。
理由3:法改正と業界健全化による追い風
ファクタリングが広がっている背景には、法制度の整備と業界の健全化という追い風もあります。
2020年の民法改正(債権法改正)により、売掛債権の譲渡制限が緩和され、より柔軟に債権を活用できるようになりました。
これにより、ファクタリングの法的な基盤が強化されたのです。
また、かつては悪質な業者の横行などでイメージが悪化した時期もありましたが、2010年代後半から業界の健全化努力が進み、サービスへの信頼も回復してきました。
大手企業の参入や業界団体の設立などにより、透明性のある適正な取引が増えています。
データで見ても、世界的にファクタリング市場は急拡大しています。
2022年の世界ファクタリング市場規模は約3.33兆ドルに達し、2023年には3.61兆ドルと年約10%成長しました。
日本でも2019年に約5億ドル(約8兆円相当)の市場規模となり、コロナ以降さらに拡大しています。
これらの背景があり、「緊急の資金繰り改善策としてファクタリングを利用する経営者が増えている」という状況が生まれているのです。
ファクタリングとは?仕組みとメリット・デメリットを徹底解説
「売掛金の早期現金化」ファクタリングの仕組みを図解
そもそもファクタリングとは何でしょうか?
簡単に言えば、「売掛金の早期現金化サービス」です。
例えば、あなたの会社がA社に商品を販売し、100万円の売掛金が発生したとします。
通常なら支払期日(例:3ヶ月後)まで待つ必要がありますが、今すぐ資金が必要な場合に活用できるのがファクタリングです。
ファクタリングには主に2つの形式があります。
2社間ファクタリング
・ あなたの会社とファクタリング会社だけで契約する形式
・ 売掛先(A社)には通知せず利用できる
・ 手数料は高めだが、取引先に知られたくない場合に便利
3社間ファクタリング
・ あなたの会社、ファクタリング会社、売掛先(A社)の三者間で契約
・ 売掛先の承諾が必要
・ 手数料は2社間より低めになることが多い
専門用語では「償還請求権」という言葉も出てきます。
これは「もし売掛先が倒産などで支払い不能になった場合に、ファクタリング利用企業(あなた)がファクタリング会社に立て替えて支払う義務が発生する契約条項」のことです。
多くのファクタリングは「ノンリコース(償還請求権なし)」ですが、契約前に必ず確認しましょう。


メリット:借入じゃないから負債が増えない!スピーディな資金化
ファクタリングの主なメリットは以下の通りです。
- 資金調達のスピードが速い:
最短即日~数日で資金化可能 - 審査が柔軟:
赤字決算や税金滞納があっても利用できる可能性が高い - 負債計上されない:
借入ではなく資産(売掛金)の売却なので、バランスシート上の負債が増えない - 返済義務がない:
返済するプレッシャーから解放される - 貸し倒れリスクの移転:
ノンリコース契約なら、売掛先の倒産リスクをファクタリング会社に移転できる - 資金繰り計画が立てやすくなる:
入金時期が確定するため、計画が立てやすい



特に「借入ではないから負債が増えない」という点は、すでに借入過多で融資が難しい企業にとって大きなメリットです。
会社の財務状態を悪化させずに資金調達できる点が評価されています。
デメリット:手数料コストと注意すべき点
一方で、以下のようなデメリットや注意点もあります。
- 手数料が融資より高い:
一般的に売掛金額の5%~20%程度(3社間で低め、2社間で高め) - 悪質業者のリスク:
高額な手数料を請求する悪質な業者も存在 - 取引先への影響:
3社間の場合、取引先に知られることで信用不安を懸念される可能性がある - 依存リスク:
繰り返し利用すると手数料負担が大きくなり、資金繰りがさらに悪化する恐れがある - 二重譲渡等のトラブル:
契約書の確認や債権譲渡登記などの手続きが必要
特に手数料コストは、融資の金利(年数%)に比べるとかなり高くなります。
例えば100万円の売掛金を手数料10%でファクタリングすると、手元に入るのは90万円。
10万円が手数料となります。




しかし、「今すぐ資金が必要」「他に選択肢がない」という切羽詰まった状況では、このコストを許容できるケースも多いでしょう。
🔍 専門家の見解
ファクタリングは「緊急時の一時的な資金調達手段」と割り切り、計画的に利用することが重要です。手数料負担を考慮して、恒常的な利用は避けるべきでしょう。
融資だけじゃない!ポストコロナの資金調達【徹底比較】
ファクタリング vs 銀行融資・ビジネスローン
ここでは、主要な資金調達手段を比較してみましょう。
| 項目 | ファクタリング | 銀行融資 | ビジネスローン |
|---|---|---|---|
| 資金化までの速さ | 最短即日~数日 | 数週間~数ヶ月 | 数日~2週間程度 |
| 審査の難易度 | 低~中(売掛先の信用力重視) | 高(財務状況、事業計画重視) | 中(銀行より柔軟だが金利は高め) |
| コスト | 手数料5%~20%程度 | 年利1%~5%程度 | 年利8%~15%程度 |
| 返済義務 | なし(売掛金の売却) | あり(元金+利息) | あり(元金+利息) |
| 向いている状況 | 緊急の資金需要、融資審査が通らない場合 | 長期的な資金需要、設備投資など | 銀行融資とファクタリングの中間的ニーズ |
銀行融資は低金利で大きな金額を借りられるメリットがありますが、審査が厳しく時間もかかります。
ビジネスローンはその中間的な位置づけで、銀行より審査は柔軟ですが金利も高めです。
ファクタリングは審査のハードルが低く、スピードも速いのが最大の強みですが、コスト面では割高になります。
それぞれの特性を理解し、自社の状況に合った選択をすることが大切です。
皆さんはどのような資金調達手段を利用していますか?
状況によって使い分けることも一つの戦略です。
クラウドファンディングという選択肢
最近注目されているもう一つの資金調達手段が「クラウドファンディング」です。
インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募る方法で、主に以下の種類があります。
購入型クラウドファンディング
- 支援者に対して商品やサービスをリターンとして提供
- 新商品開発や新規事業立ち上げに向いている
- 資金調達と同時に市場調査・PRにもなる
融資型クラウドファンディング
- 支援者からの投資に対して金利を支払う形式
- 銀行融資より審査が通りやすい場合も
- 金利は銀行より高めだが、ファクタリングよりは低いケースが多い
株式型クラウドファンディング
- 会社の株式や持分を提供する形式
- 急成長が見込めるベンチャー企業向き
- 経営権の一部を手放すことになる点に注意
クラウドファンディングのメリットは、銀行融資が難しいアイデア段階のプロジェクトでも、共感や将来性によって資金を調達できる点です。
さらに、資金調達と同時に宣伝効果が得られることも大きな魅力です。



一方、デメリットとしては、目標額に達しないとゼロになるケースがあること、準備に時間と労力がかかること、支援者へのリターン実行責任が生じることなどが挙げられます。
ファクタリングと比較すると、緊急性の高い資金ニーズには向きませんが、新規性のある事業やPR効果も期待したい場合は検討する価値があるでしょう。
🎯 実践ステップ
クラウドファンディングに挑戦する場合は、Makuake、CAMPFIRE、Readyforなどの主要プラットフォームを比較検討してみましょう。融資型ならクラウドクレジットやレンデックスなどがあります。
返済不要が魅力!補助金・助成金の活用法
「返済不要」という最大のメリットを持つのが、補助金・助成金です。
代表的なものには以下があります。
事業再構築補助金
- ポストコロナの事業転換支援
- 補助上限:数百万円~数千万円(企業規模等による)
- 審査あり、採択率は30~50%程度
小規模事業者持続化補助金
- 小規模事業者の販路開拓等を支援
- 補助上限:50万円(特別枠で100万円)
- 比較的採択率が高い
IT導入補助金
- デジタル化、IT導入による生産性向上を支援
- 補助上限:最大450万円
- IT導入を検討している企業に最適
補助金・助成金は返済不要という最大のメリットがある反面、以下のような点に注意が必要です。
特に「後払い方式」は重要なポイントです。
補助金が採択されても、まず自社で費用を支出し、完了報告後に補助金が支給されるケースがほとんどです。
その間のつなぎ資金としてファクタリングを活用するという組み合わせも効果的です。
私が支援したある製造業のお客様は、設備投資に事業再構築補助金を活用。採択から入金までの期間のつなぎ資金をファクタリングで調達し、スムーズに事業転換を進めることができました。
失敗しない!ファクタリング利用の注意点と賢い選び方
要注意!よくある失敗事例とその回避策
ファクタリングを利用する際には、以下のような失敗例を知っておくことが重要です。
失敗例1:手数料が高すぎて資金繰り改善にならなかった
あるサービス業C社は、急な資金需要に対応するためファクタリングを利用しましたが、手数料が25%と非常に高額。
結局、短期的な資金繰りは改善したものの、その後の運転資金が不足し、悪循環に陥りました。
回避策:
・ 複数のファクタリング会社から見積もりを取り、比較する
・ 相場(5〜20%程度)から大きく逸脱した手数料を提示する業者は避ける
・ 手数料だけでなく、スピードや対応なども総合的に判断する
失敗例2:二重譲渡等の契約トラブル
製造業D社は、同じ売掛債権を誤って複数のファクタリング会社に譲渡してしまい、大きなトラブルに発展。
取引先との信頼関係も損なわれました。
回避策:
・ 債権譲渡登記や通知を適切に行う
・ 社内で管理を徹底し、譲渡済みの売掛金を一覧化する
・ 契約書の内容を十分に確認する
失敗例3:ファクタリング依存症
小売業E社は、資金繰りが苦しくなるたびにファクタリングを利用し、最終的に売掛金の大部分を早期現金化するようになりました。
手数料負担がかさみ、根本的な収益改善がないまま、資金繰りがさらに悪化する悪循環に陥りました。
回避策:
・ ファクタリングは「緊急時の一時的な手段」と割り切る
・ 並行して本業の収益改善に取り組む
・ 定期的な資金繰り計画を立て、依存しないようにする
特に注意したいのは「ファクタリング依存症」です。
手数料負担が積み重なると、長期的には資金繰りが悪化する可能性があります。
基本的にはスポットで利用し、資金繰りが安定したらファクタリングから卒業することが理想です。
ファクタリングを検討している場合、「この資金は何に使うのか?」「いつまでに回収できるのか?」を明確にしておくことが重要です。単に資金繰りの穴埋めではなく、明確な目的があるかを考えてみましょう。
悪質業者を見抜く!信頼できるファクタリング会社の選び方
残念ながら、ファクタリング業界には悪質な業者も存在します。
安全に利用するためのチェックポイントを紹介します。
1. 会社の信頼性を確認
□ 住所や連絡先が明確に記載されているか
□ 会社の実績や規模は妥当か
□ 口コミや評判はどうか
□ 反社会的勢力との関係がないか
2. 契約内容をしっかり確認
□ 手数料は相場の範囲内か(5%~20%程度)
□ 必要書類は適正か(過剰な個人情報の要求はないか)
□ 契約書の内容に不審な点はないか
□ 償還請求権(リコース)の有無は明記されているか
3. 対応の丁寧さをチェック
□ 質問に対して誠実に回答してくれるか
□ 手数料や条件を事前に明示しているか
□ 強引な勧誘はないか
□ 専門用語を分かりやすく説明してくれるか
特に警戒すべきは、「貸金業登録をせずに実質的な貸付を行うヤミ金融」です。
例えば「給与ファクタリング」と称して個人の給与債権を買い取る行為は貸金業法違反で摘発事例があります。
一方、事業者向けのファクタリング自体は合法で、経済産業省も債権流動化を中小企業金融の有効策として推奨しています。
安全にファクタリングを利用するためには、信頼できる業者を選ぶことが何よりも重要です。
不明点は必ず質問し、納得できない場合は契約を見送りましょう。
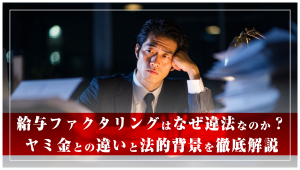
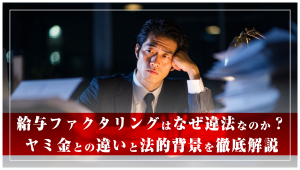


【事例紹介】ファクタリング活用で危機を乗り越えた企業
成功事例:建設業A社 – 急な資金ショートを乗り切り受注拡大へ
建設業を営むA社(従業員15名、年商2億円)は、大型公共工事を受注したものの、資材調達のための前払い資金が不足していました。
銀行に融資を申し込みましたが、直近の決算が赤字だったため審査に時間がかかると言われてしまいます。
しかし、公共工事という確実な売掛先があることから、ファクタリングの利用を決断。
3,000万円の売掛金を手数料10%(300万円)でファクタリングし、即日2,700万円の資金を調達しました。
これにより資材調達がスムーズに進み、工事を予定通り完了。
その後の評価も高く、さらなる受注につながりました。
手数料は決して安くありませんでしたが、機会損失を避け、信用を維持できたことで長期的にはプラスだったと社長は振り返っています。
教訓事例:小売業B社 – ファクタリング依存からの脱却
アパレル小売業のB社(従業員8名、年商1億円)は、コロナ禍での売上減少から資金繰りが悪化。
当初は一時的な対応としてファクタリングを利用していましたが、次第に恒常的に頼るようになってしまいました。
月に2回程度、合計約1,000万円の売掛金をファクタリングに出し、手数料として毎月約150万円を支払う状況に。
本来入ってくるはずの売掛金が目減りし続け、さらなる資金繰り悪化という悪循環に陥ってしまいました。
このままでは立ち行かなくなると危機感を抱いたB社は、以下の改革に着手しました。
- 専門家(中小企業診断士)に相談し、収益構造の見直し
- 不採算店舗の閉鎖と経費削減
- オンライン販売の強化
- 金融機関と交渉し、既存借入のリスケジュール
- ファクタリングへの依存度を段階的に下げる計画の実行
結果的に、半年かけてファクタリングからの「卒業」に成功。
現在は収益も改善し、安定した資金繰りを取り戻しています。
この事例からわかるように、ファクタリングは緊急時の救済策として有効ですが、根本的な経営改善なしに依存し続けると危険です。
「ファクタリングはあくまで一時しのぎ」という認識を持つことが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q: ファクタリングって違法じゃないの?安全ですか?
A: 事業者向けのファクタリング自体は合法的な資金調達手段です。
裁判例でもファクタリング契約の合法性が確認されており、経済産業省も中小企業の資金調達手段として債権流動化を推奨しています。
ただし、貸金業登録をせずに実質的な貸付を行う悪質な業者も存在します。
特に「給与ファクタリング」と称して個人の給与債権を買い取る行為は貸金業法違反で摘発事例があるため注意が必要です。
安全に利用するためには、信頼できるファクタリング会社を選ぶことが重要です。
会社の実績や口コミ、契約内容をしっかり確認しましょう。
Q: ファクタリングの手数料はどれくらいが相場ですか?
A: 手数料は、2社間か3社間か、売掛先の信用力、売掛金の額、資金化までの期間などによって大きく変動します。
一般的に、リスクの低い3社間ファクタリングで5%~15%程度、リスクの高い2社間ファクタリングで10%~20%程度が相場と言われます。
ただし、これはあくまで目安です。
手数料以外にも、契約書作成費用や債権譲渡登記費用などが別途かかるケースもあります。
必ず複数社から見積もりを取り、総コストを比較検討してください。
相場を大きく超える手数料(25%以上など)を提示する業者は避けるべきでしょう。
Q: 赤字決算でもファクタリングは利用できますか?
A: はい、利用できる可能性が高いです。
ファクタリングの審査では、自社の財務状況よりも売掛先(支払い元)の信用力が重視されるため、赤字決算や債務超過であっても、売掛先の信用さえ良ければ審査に通ることが多いです。
実際、ファクタリング会社の多くは、申込企業の決算書が赤字や債務超過、あるいは税金滞納があっても、審査にはほとんど影響しないと明言しています。
ただし、売掛先の信用力が低い場合や、取引実績が乏しい場合は審査が厳しくなる可能性もあります。
また、審査基準はファクタリング会社によって異なるため、複数社に相談してみることをお勧めします。
まとめ
コロナ後の厳しい経営環境において、ファクタリングは中小企業の資金調達の重要な選択肢となっています。
特に融資審査が厳しくなる中、スピーディーで柔軟な資金調達手段として注目を集めています。
しかし、手数料コストが高いというデメリットもあり、「緊急時の一時的な対応策」と位置づけることが重要です。
恒常的に利用し続けると、手数料負担が重くのしかかり、さらなる資金繰り悪化を招く恐れがあります。
本記事で紹介したように、資金調達には融資、ファクタリング、クラウドファンディング、補助金・助成金など多様な選択肢があります。
自社の状況に合わせて、これらを適切に使い分けることが大切です。
まずは今後半年の資金繰り計画を立て、どのタイミングでどの程度の資金が必要かを明確にしましょう。
その上で、必要に応じてファクタリングも含めた複数の選択肢を検討することをお勧めします。
資金繰りの不安は、行動することで必ず小さくできます。
この記事が少しでも皆さんの経営判断のお役に立てば幸いです。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化



