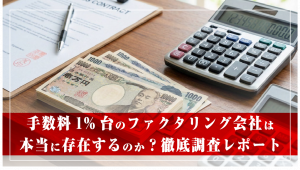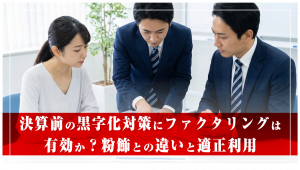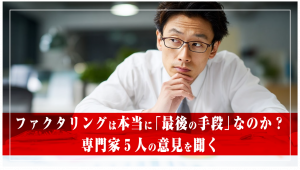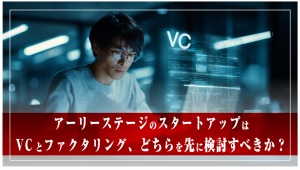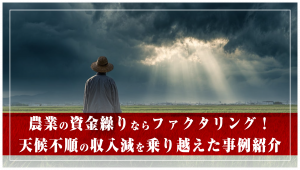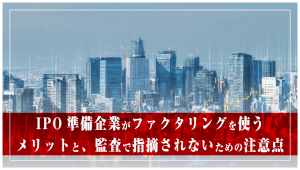売上はあるのに手元資金が足りない…。
新しい事業にチャレンジしたいけど資金がない…。
中小企業経営者の皆さんなら、こうした資金調達の悩みに直面したことがあるのではないでしょうか。
銀行融資は審査が厳しく、親族や知人からの借入にも限界があります。
そんなとき、選択肢として浮上するのが「ファクタリング」と「クラウドファンディング」です。
 山田 麻里
山田 麻里結論から申し上げると、どちらが優れているかは一概には言えません。
資金調達の「目的」「緊急性」「金額」によって最適な選択は変わってきます。
この記事を読めば、ファクタリングとクラウドファンディングの明確な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして自社に合った方法を選ぶための具体的なヒントが理解できるでしょう。
私は金融コンサルタントとして多くの中小企業の資金調達をサポートしてきました。
その経験を活かし、今回は資金調達の選択肢を広げるための比較記事をお届けします。
悩みを解消し、事業成長の一歩を踏み出すためのガイドとしてご活用ください。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
ファクタリングとは?売掛金を早期現金化する仕組みとメリット・デメリット
ファクタリングの仕組み:債権を売って資金を得る?
ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却し、資金を早期に手に入れる方法です。
言い換えると、「未来のお金」である売掛金を、手数料を払って「今すぐのお金」に変える仕組みと言えるでしょう。
具体的には、次のような流れになります。
- 企業Aが取引先B社に商品を納品し、請求書を発行(支払期日は3ヶ月後)
- しかし企業Aは今すぐ資金が必要
- そこでファクタリング会社Cに売掛債権を売却
- ファクタリング会社Cは手数料を差し引いた金額を企業Aに支払う
- 支払期日が来たら、取引先B社はファクタリング会社Cに支払いを行う
ファクタリングには主に2種類あります。
💡 ファクタリングの2つの形態
2社間ファクタリング: 自社とファクタリング会社の間だけで完結。取引先に知られずに利用できますが、手数料は高め(8〜18%程度)。
3社間ファクタリング: 取引先も含めた三者間の契約。取引先への通知・承諾が必要ですが、手数料は比較的安価(5〜10%程度)。
つまり、ファクタリングは「借りる」のではなく「売る」という点が重要です。
債務ではなく資産の売却なので、バランスシート上の負債は増えません。


ファクタリングのメリット:スピードと柔軟性が魅力
ファクタリングの最大のメリットは、資金調達の「スピード」と「審査の柔軟性」です。
具体的には以下のようなメリットがあります。
スピード感
最短即日〜数日で資金化が可能です。
銀行融資が数週間〜数ヶ月かかるのと比べると圧倒的に早いと言えるでしょう。
急な資金ショートや支払いに対応できます。
審査の柔軟性
銀行融資とは異なり、自社の業績や信用力ではなく、売掛先(債務者)の信用力が重視されます。
そのため、赤字決算や税金滞納があっても、大手企業などの信用力の高い取引先への売掛金があれば利用できる可能性が高いです。


担保・保証人不要
原則として不動産などの担保や個人保証は不要です(売掛債権自体が「担保」の役割を果たします)。
負債にならない
会計上は「債権の売買」となるため、銀行借入のように負債が増えるわけではありません。
使途自由
調達した資金の使い道に制限はなく、運転資金や設備投資など自由に活用できます。



こうした特徴から、ファクタリングは特に「入金を待っている間の資金繰りを改善したい」「銀行融資が通らなかった」「緊急で資金が必要」といった状況に適していると言えるでしょう。
ファクタリングのデメリット:手数料と注意点
一方で、ファクタリングには以下のようなデメリットもあります。
手数料が高い
最大のデメリットは手数料の高さです。
2社間ファクタリングの場合、売掛金額の8〜18%程度が手数料として差し引かれることも珍しくありません。
3社間ファクタリングでも5〜10%程度の手数料がかかります。
例えば、500万円の売掛金を2社間ファクタリングで現金化すると、手数料10%として50万円が差し引かれ、手元に入るのは450万円となります。
悪質業者の存在
残念ながら、法律の未整備を利用した悪質なファクタリング業者も存在します。
極端に高い手数料を請求したり、債権の二重譲渡を行うなどのトラブル事例が報告されています。
金融庁も「買取代金が債権額に比して著しく低額なケースは偽装ファクタリングの疑いがある」と注意喚起しています。
取引先への影響
3社間ファクタリングでは取引先への通知が必要となるため、資金繰りに困っていると思われる可能性があります。
また、2社間でも契約内容によっては債権譲渡禁止特約に抵触する恐れもあります。
継続利用のリスク
一時的な利用なら問題ありませんが、高い手数料を払い続けると利益を圧迫します。
アンケート調査では、27%の利用者がファクタリングで何らかの失敗を経験しており、その主な理由は「業者選定ミスによる高額手数料」でした。
コンサルタント時代の経験からお伝えすると、ファクタリングは「非常時の道具」と心得ることが大切です。
計画的な利用と信頼できる業者選びができれば、資金繰りの強力な味方になるでしょう。


クラウドファンディングとは?共感を力に資金を集める仕組みとメリット・デメリット
クラウドファンディングの仕組み:ネットで支援者を募る?
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて不特定多数の人々から小口の資金を集める方法です。
自社の事業やプロジェクトに共感してくれる支援者を募り、その「応援の気持ち」を資金として集めるイメージです。
日本国内の市場規模は年々拡大し、2022年には約2,000億円に達したとの予測もあります。
Makuake(マクアケ)やCAMPFIRE(キャンプファイヤー)などのプラットフォームを通じて、様々なジャンルのプロジェクトが資金を集めています。
クラウドファンディングには主に4つのタイプがあります。
🔍 クラウドファンディングの4つの種類
購入型: 支援者に商品やサービスを提供するタイプ。最も一般的で中小企業が利用しやすい。
寄付型: リターンなしで純粋な寄付として資金を集めるタイプ。社会貢献性の高い活動に向いている。
投資型: 株式や配当などの金銭的リターンを提供するタイプ。金融商品取引法の規制対象。
融資型: 利息付きで返済する前提での資金調達。いわゆるソーシャルレンディング。
中小企業やスタートアップが最も活用しやすいのは購入型で、プロジェクトの内容や目標金額を設定し、支援者には商品やサービスなどのリターンを提供します。
目標金額に達した場合のみ資金を受け取れる「All-or-Nothing型」と、達成できなくても集まった分だけ受け取れる「All-in型」があります。
クラウドファンディングのメリット:資金調達+αの効果
クラウドファンディングの魅力は、単なる資金調達を超えた様々な効果が期待できる点にあります。
返済不要の資金
購入型や寄付型の場合、集めた資金は原則として返済不要です。
融資や借入と異なり、元本や利息の返済義務がありません。リターンとして商品やサービスを提供するだけでよいのです。
マーケティング効果
新商品やサービスの市場反応を事前に確認できる「テストマーケティング」の役割も果たします。
支援の集まり方や反応から、本格展開前に顧客ニーズを把握できるでしょう。
PR効果とファン獲得
プロジェクトを通じて自社の理念や商品の魅力を広く発信できます。
成功すれば、メディアに取り上げられる可能性も。何より、熱心な支援者という「ファン」を獲得できるのは大きな資産です。
実績がなくても挑戦可能
創業間もない企業や個人でも、アイデアや商品の魅力次第で資金を集められます。
銀行融資のような業績や担保は問われません。
追加投資のきっかけに
クラウドファンディングでの成功実績があると、その後のVC(ベンチャーキャピタル)投資や銀行融資の獲得がしやすくなる傾向があります。



クラウドファンディングの事例では、国内最高額は約3億円という記録もあります。
もちろん、これは例外的な成功例ですが、適切なテーマと戦略があれば、数百万円〜数千万円の資金調達も十分可能です。
クラウドファンディングのデメリット:時間と労力、不確実性
一方で、クラウドファンディングには以下のようなデメリットや注意点もあります。
時間がかかる
資金調達までに時間がかかるのが最大のデメリットです。
準備期間(1〜2ヶ月)、募集期間(1〜3ヶ月)、入金処理(約0.5ヶ月)を合わせると、企画開始から実際に資金を使えるようになるまで、最低でも3〜4ヶ月程度が必要です。
準備と運営の労力
プロジェクトページの作成、魅力的な動画や写真の準備、SNS等での告知活動、支援者とのコミュニケーションなど、相当な時間と労力が必要です。
「お金を集めるだけ」ではなく、「プロジェクトを運営する」という意識が重要です。
成功率は決して高くない
平均的な成功率は20〜40%程度で、半数以上のプロジェクトが目標未達に終わるのが現実です。
「良い商品があればお金は自然と集まる」というわけではありません。
プラットフォーム手数料
目標達成時には、調達額の10〜20%程度がプラットフォーム手数料や決済手数料として差し引かれます。
さらにリターン製造・発送コストも考慮すると、実質的な調達コストは調達額の25〜30%に達することも珍しくありません。
アイデア模倣のリスク
公開前の商品やサービスを詳細に発表するため、アイデアを模倣されるリスクがあります。
特許出願や商標登録などの知的財産保護策を検討すべきでしょう。
リターン履行の義務
支援者へのリターン(商品・サービス)は必ず提供する義務があります。
開発の遅延や予想外のコスト増加があっても、約束は守らなければなりません。
論理的に考えると、クラウドファンディングは「緊急の資金ショート対策」には向いていません。
新商品開発や新規事業立ち上げなど、「時間をかけても共感を得られるプロジェクト」に適していると言えるでしょう。
徹底比較!ファクタリング vs クラウドファンディング【早見表付き】
目的の違い:キャッシュフロー改善か?新規プロジェクトか?
ファクタリングとクラウドファンディング、どちらを選ぶべきかは、まず資金調達の「目的」を明確にすることが重要です。両者は基本的に次のような目的の違いがあります。
ファクタリングに適した目的
- 短期的な資金繰りの改善
- 支払いの期日が迫っているなど緊急の資金需要
- 売掛金の入金を待つ間のつなぎ資金
- 銀行融資が難しい状況での代替手段
クラウドファンディングに適した目的
- 新商品・新サービスの開発資金
- 新規事業の立ち上げ
- 社会的意義のあるプロジェクト
- マーケティングや認知度向上を兼ねた資金調達



例えば、「今月末の支払いに間に合わせるため」という目的であれば、明らかにファクタリングが適しています。
一方、「半年後に発売予定の新商品の試作開発費用」であれば、クラウドファンディングの方が向いているでしょう。
端的に言えば、ファクタリングは「既に発生した売上の現金化を早める」ための手段であり、クラウドファンディングは「これから生み出す価値に対して先に資金を集める」手段と言えます。
スピード・コスト・手間を比較
続いて、両者を重要な観点から比較してみましょう。
スピード
- ファクタリング: ◎(最短即日〜数日で資金化可能)
- クラウドファンディング: △(企画から資金受取まで数ヶ月必要)
スピードに関しては、ファクタリングが圧倒的に優位です。
審査書類が揃えば最短即日での資金化も可能で、オンラインファクタリングサービスでは申込から最短1時間で入金されるケースもあります。
一方、クラウドファンディングは準備期間(1〜2ヶ月)、募集期間(1〜3ヶ月)、事務処理期間を合わせると、最低でも3ヶ月程度かかります。
コスト
- ファクタリング: △(手数料10〜30%程度、3社間なら5〜10%程度)
- クラウドファンディング: △(プラットフォーム手数料10〜20%+リターン原価・送料)
コスト面では、一概にどちらが有利とは言えません。
ファクタリングは直接的な手数料が高いものの、クラウドファンディングも手数料に加えてリターン製造・発送コストなどを考えると、実質的なコストは同等か、場合によってはクラウドファンディングの方が高くなることもあります。
ただし、クラウドファンディングは資金調達以外の効果(PR効果など)も得られるため、総合的な費用対効果で判断する必要があるでしょう。
手間
- ファクタリング: 〇(必要書類提出と審査のみ)
- クラウドファンディング: ×(企画立案、ページ制作、PR活動、支援者対応など多大な労力)
手間の面では、ファクタリングの方が明らかに少ない労力で済みます。
必要書類を提出し審査を受けるだけですから、業務への影響は限定的です。
一方、クラウドファンディングは実質的に「一つのプロジェクト」を運営するのと同じくらいの労力が必要です。
プロジェクトページの作成、魅力的な写真や動画の準備、SNSでの拡散、支援者とのコミュニケーションなど、かなりの時間とエネルギーを要します。
審査基準
- ファクタリング: 売掛先の信用力が重視される
- クラウドファンディング: プロジェクトの魅力・共感性が重視される
審査の観点も全く異なります。
ファクタリングでは債務者(売掛先)の信用力が最重要視されるのに対し、クラウドファンディングでは「共感を呼ぶストーリー」「魅力的な商品・サービス」が成功の鍵を握ります。
自社の状況に応じて、どちらの審査基準の方がクリアしやすいかを考慮するとよいでしょう。
【早見表】ファクタリングとクラウドファンディングの違いが一目でわかる!
下記の表で、両者の主な違いを整理してみました。資金調達方法を検討する際の参考にしてください。
| 比較項目 | ファクタリング | クラウドファンディング |
|---|---|---|
| 基本的な性質 | 売掛債権の売却 | 多数の支援者からの資金調達 |
| 適した目的 | 資金繰り改善・つなぎ資金 | 新規プロジェクト・商品開発 |
| 調達スピード | 最短即日〜数日 | 数ヶ月(準備+募集期間) |
| コスト | 手数料10〜30%(2社間) 手数料1〜9%(3社間) | 手数料10〜20%+リターンコスト |
| 必要な労力 | 少ない(書類準備と審査) | 多い(企画・PR・支援者対応) |
| 重視される要素 | 売掛先の信用力 | プロジェクトの魅力・共感性 |
| 返済義務 | なし(債権の売却) | なし(購入型・寄付型の場合) |
| 成功率 | 高い(売掛先が優良なら) | 20〜40%程度 |
| 副次効果 | ほぼなし | PR効果・マーケティング効果あり |
| 向いている企業 | 取引実績ある中小企業 | 商品開発型・ストーリー性ある企業 |
| 利用可能な業種 | 売掛金がある業種全般 | 製品開発、コンテンツ、社会貢献等 |
| 資金使途制限 | なし | プロジェクト実行に関わる用途 |
あなたの会社にはどっち?最適な資金調達方法を選ぶための3つのステップ
Step1: 資金調達の「目的」「金額」「緊急度」を明確にする
資金調達方法を選ぶ際、まず自社の状況を客観的に整理することが重要です。
具体的には次の3つのポイントを明確にしましょう。
資金調達の目的は何か?
- 仕入れや人件費などの運転資金ですか?
- 設備投資や事業拡大のための成長資金ですか?
- 新商品開発やマーケティングのための投資資金ですか?
必要な金額はいくらか?
- 具体的な数字で必要金額を算出しましょう
- 最低限必要な金額と理想的な金額の両方を考えておくと良いでしょう
いつまでに資金が必要か?
- 1週間以内の緊急性がありますか?
- 1〜3ヶ月程度の準備期間は確保できますか?
- 半年先など中長期的な資金計画ですか?
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
ケースA: 来週支払い予定の仕入代金100万円が不足している。2ヶ月後には売掛金150万円の入金がある。
→ 緊急性が高く、短期的な資金繰り改善が目的なので、ファクタリングが適しています。
ケースB: 半年後に発売予定の新商品開発資金として300万円が必要。収益化は1年後を想定している。
→ 時間的猶予があり、新規プロジェクトの資金なので、クラウドファンディングが検討できます。
ケースC: 今月末に支払うべき給与総額500万円が不足。売掛金はあるが入金は3ヶ月後。
→ 緊急性が高く、かつ金額が大きいため、ファクタリング(可能なら3社間)が適しています。
このように、目的・金額・緊急度の3要素を明確にすることで、どちらの資金調達方法が適しているかの判断材料が得られます。
Step2: 自社の「状況」と「強み」を分析する
次に自社の現状と強みを分析し、どちらの資金調達方法に適しているかを検討しましょう。
ファクタリングに有利な条件
- 安定した売掛金がある
- 取引先に大企業や官公庁など信用力の高い先がある
- すでに商品・サービスを提供し、売上実績がある
- 資金繰りの改善が急務である
クラウドファンディングに有利な条件
- 新しい商品やサービスのアイデアがある
- ストーリー性や社会的意義のある事業内容である
- SNSなどで一定のフォロワーやファンがいる
- 魅力的なリターン(商品・サービス)を提供できる
- マーケティングや広報の人材・スキルがある
例えば、「大手企業との取引がある製造業」であれば、その取引先への売掛金を活用したファクタリングが有効でしょう。
一方、「ユニークな商品を開発中のデザイン会社」であれば、その商品の魅力を活かしたクラウドファンディングの方が成功確率が高いかもしれません。



金融コンサルタントとしての経験から言えば、自社の「強み」を活かせる方を選ぶことが成功の近道です。
売掛債権という「強み」があればファクタリング、商品の魅力やストーリーという「強み」があればクラウドファンディングが向いているでしょう。
Step3: メリット・デメリットを再確認し、リスクを評価する
最後に、両方法のメリット・デメリットを改めて確認し、自社にとってのリスクを評価しましょう。
ファクタリングのリスク評価
- 手数料負担が利益を圧迫する可能性はないか?
- 3社間の場合、取引先への影響はどうか?
- 継続的に利用する場合の財務への影響は?
- 悪質業者に当たるリスクを回避できるか?
クラウドファンディングのリスク評価
- 目標金額を達成できない可能性はどの程度か?
- プロジェクト運営に十分な人的リソースを割けるか?
- リターン提供コストは適切に見積もれているか?
- 知的財産保護は十分か?
不安な点がある場合は、専門家(金融機関、クラウドファンディングプラットフォームの担当者、税理士等)に相談することも検討してください。
特にファクタリングは業者選びが重要ですし、クラウドファンディングはプラットフォーム選びやプロジェクト設計で専門的なアドバイスが役立ちます。
📚 さらに詳しく
初めて利用する場合は、小規模なテストから始めるのも一つの方法です。例えば、売掛金の一部だけをファクタリングしてみる、または小さな目標金額でクラウドファンディングに挑戦してみるといった段階的なアプローチも検討してみてください。
ここに注意!ファクタリング・クラウドファンディング利用時の落とし穴
ファクタリング:悪質業者を見抜き、契約内容をしっかり確認
ファクタリングを利用する際、最も重要なのは信頼できる業者を選ぶことです。
アンケート調査では、ファクタリングで失敗した企業の多くが「業者選定ミス」を原因に挙げています。
以下のポイントに注意しましょう。
複数社から見積もりを取る
手数料率は業者によって大きく異なります。
必ず複数社から見積もりを取得し、比較検討しましょう。特に初めての利用時は重要です。
手数料以外の諸経費も確認
手数料の他に、事務手数料、印紙税、振込手数料などが発生する場合があります。
最終的に手元に残る金額を必ず確認してください。
契約書を隅々まで読む
特に重要なのは「償還請求権の有無」です。
これは売掛先が支払わなかった場合に、ファクタリング会社から資金の返還を求められるかどうかという条項です。
可能なら顧問弁護士等に確認してもらうことをお勧めします。
違法な高金利に注意
ファクタリングは貸金ではないため貸金業法の上限金利規制は適用されませんが、極端に高い手数料(例:50%以上)は「偽装ファクタリング」の可能性があります。
金融庁も「買取代金が債権額に比して著しく低額なケースは偽装ファクタリングの疑いがある」と注意喚起しています。
「給与ファクタリング」との違い
個人向けの「給与ファクタリング」は最高裁で実質的な貸金業と判断され、違法とされています。
企業の売掛債権を対象とする正規のビジネスファクタリングとは全く別物です。
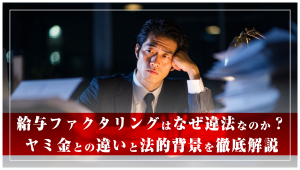
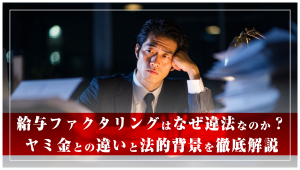
⚠️ 注意事項
悪質業者を見分けるポイント:
- 極端に高い手数料を提示する業者
- 所在地や会社概要が不明確な業者
- 契約内容の説明が不十分な業者
- 法人登記や金融関連の登録が確認できない業者
困ったときの相談先:
- 金融庁相談窓口
- 弁護士会
- 地元の商工会議所や商工会
金融コンサルタントとして多くの企業を見てきた経験から言えることは、「安すぎる手数料」や「審査なしでOK」といった甘い言葉には要注意ということです。
適正な審査と透明な手数料体系を持つ業者を選びましょう。
クラウドファンディング:成功のための準備と誠実な対応が鍵
クラウドファンディングの成功率は平均20〜40%と決して高くありません。
成功に近づくためには、以下のポイントに注意することが重要です。
現実的な目標設定
初めてのプロジェクトでは、できるだけ達成可能な現実的な目標金額を設定しましょう。
目標が高すぎると達成が難しくなります。特にAll-or-Nothing方式では、わずかに届かなくても資金を得られません。
魅力的なリターン設計
支援者にとって魅力的なリターン(商品・サービス)を設計することが重要です。
ただし、リターンの原価や発送コストも含めて計算し、採算が取れるかを事前に確認してください。
リターンコストが調達金額の大部分を占めてしまうケースもあります。
事前の告知・PR活動
プロジェクト公開前から告知を始め、公開初日に20%程度の達成率を目指すことが推奨されています。
初動の勢いがその後の展開を大きく左右します。SNSや既存顧客への事前案内は必須です。
支援者への丁寧な対応
支援者からの質問や意見には誠実かつ迅速に対応しましょう。
また、プロジェクト進行中も定期的に状況を報告することで信頼を築けます。
税務処理の確認
調達した資金は、多くの場合「売上」または「雑収入」として課税対象になります。
税務処理について事前に税理士等に相談することをお勧めします。
リターン提供の遅延リスク管理
想定より支援が多く集まった場合や、製造・開発に遅れが生じた場合の対応策も考えておきましょう。
納期遅延が発生した場合は速やかに支援者に状況を説明することが重要です。
あるデザイン雑貨メーカーは、新商品開発のためのクラウドファンディングで、目標200万円に対して320万円の調達に成功しました。成功の要因として「事前のSNS告知」「ストーリー性のある動画制作」「魅力的な限定リターン設計」が挙げられています。また、支援者とのコミュニケーションを大切にし、開発状況を定期的に報告したことで、その後のリピート購入にもつながりました。
私がコンサルティングした企業の事例からも、「共感を呼ぶストーリー」と「継続的なコミュニケーション」が成功の鍵だと実感しています。
単なる商品販売ではなく、「なぜそれを作りたいのか」「どんな想いがあるのか」を伝えることで支援の輪が広がりやすくなります。
最新動向と成功のヒント:資金調達の選択肢を広げるために
ファクタリング・クラウドファンディング市場の今とこれから
両市場とも近年急速に拡大しており、今後もさらなる成長が見込まれています。
最新の動向を把握しておくことで、より効果的な資金調達戦略を立てられるでしょう。
ファクタリング市場の最新動向
- 市場規模の拡大:
日本のファクタリング市場は2023年度で約5.7兆円(売掛債権買取額ベース)に達したとの推計があります。年々拡大傾向にあります。 - 法制度の整備:
2020年の民法改正により、「譲渡禁止特約付き債権の譲渡」が一定条件下で可能となりました。これにより、中小企業でも契約上は譲渡不可だった売掛金をファクタリングしやすくなっています。 - 支払いサイト短縮化の動き:
2024年11月から下請代金の支払サイト短縮要請(60日超の手形払いは是正対象)など、国の施策が資金繰り改善を後押ししています。 - オンライン化の進展:
オンラインで完結するファクタリングサービスが増加し、申込から入金までのスピードが向上しています。 - 業界の健全化:
金融庁による注意喚起や東京都の悪質業者排除の動きなど、業界の健全化が進んでいます。適正な手数料や透明性の高いサービスが評価される傾向にあります。
クラウドファンディング市場の最新動向
- 市場規模の拡大:
日本国内の市場規模は年々拡大し、2022年には約2,000億円に達したとの予測があります。世界的にも年率11%以上で成長すると見られています。 - プラットフォームの多様化:
Makuake、CAMPFIRE、READYFORなど大手プラットフォームの他、特定分野に特化したプラットフォームも登場しています。業種や目的に応じて選択肢が広がっています。 - 企業の戦略的活用:
大企業もマーケティング目的でクラウドファンディングを活用するケースが増えています。新商品の市場反応を測るテストマーケティングやファン獲得の場として活用されています。 - 不動産クラウドファンディングの台頭:
不動産投資に特化したクラウドファンディングも拡大しており、少額から不動産投資ができる新たな選択肢として注目されています。 - 法規制の整備:
投資型クラウドファンディングは金融商品取引法の規制対象となり、投資家保護の枠組みが整備されています。
【事例紹介】こんな企業がこう使った!成功の秘訣
実際の成功事例から学ぶことは多いものです。
以下、両方法を効果的に活用した企業の事例をご紹介します。
ファクタリング成功事例
A社(製造業・従業員30名)は、大手メーカーからの大型受注を獲得しましたが、材料仕入れと人件費の支払いが先行するため、一時的な資金不足に陥りました。
銀行融資は審査に時間がかかるため、既存の売掛金(約800万円)を3社間ファクタリングで現金化。
手数料率5%(40万円)を支払いましたが、大型案件を無事に完遂でき、結果的に200万円の利益を確保できました。
成功のポイントは「一時的な資金ニーズに対して計画的に利用した点」と「複数のファクタリング会社から見積もりを取得し、最適な条件を選んだ点」です。
経営者は「手数料は決して安くないが、機会損失を避けられたことを考えれば妥当な投資だった」と振り返っています。
クラウドファンディング成功事例
B社(地方の老舗醤油蔵・従業員8名)は、老朽化した製造設備の更新資金を調達するため、クラウドファンディングに挑戦しました。
目標金額200万円に対して、最終的には300万円を集めることに成功。
支援者からの応援メッセージが地元紙にも取り上げられ、知名度向上にもつながりました。
成功のポイントは「単なる設備更新ではなく、地域の伝統を守る物語としてストーリーを構築した点」と「支援者特典として通常は販売していない限定商品を用意した点」です。
特に、古来の製法で作る限定醤油セットは高額支援者に人気で、プロジェクト終了後も定期的な問い合わせがあるそうです。
大型成功事例
国内では、あるスタートアップ企業がクラウドファンディングで1億円超の資金を集めた例もあります。
革新的なガジェット製品の開発プロジェクトで、1,000人以上の支援者から資金を集め、その後大手企業からの出資も獲得して事業を拡大しました。
こうした大型の成功事例は必ずしも一般的ではありませんが、商品の革新性やマーケティング戦略次第で、中小企業でも大きな成功を収める可能性があることを示しています。
組み合わせも有効?資金調達戦略の多様化
資金調達は「どちらか一方」と考えるのではなく、状況に応じて組み合わせたり、他の手段と併用したりする柔軟な発想も重要です。
両方法の組み合わせ例
- クラウドファンディングで新商品の開発資金を調達し、生産資金の一部をファクタリングでまかなう
- ファクタリングで急場の資金繰りを乗り切りながら、中長期的な資金調達のためにクラウドファンディングを準備する
他の資金調達方法との連携
- 銀行融資とファクタリングの併用(長期資金は融資、短期資金はファクタリング)
- クラウドファンディング成功後、その実績を基に公的補助金や助成金を申請
- 投資型クラウドファンディングと従来のエンジェル投資を組み合わせる
例えば、ある製造業のC社は、次のような資金調達戦略を展開しました。
- 新製品の試作開発費用→クラウドファンディング(300万円)
- 量産体制構築→日本政策金融公庫の融資(1,000万円)
- 納品までのつなぎ資金→ファクタリング(一時的に利用)
このように、資金の用途や時期に応じて最適な調達手段を使い分ける「多様化戦略」が、中小企業の安定した資金繰りには効果的です。
資金調達の方法は一つではなく、状況に応じて柔軟に選択・組み合わせることで、より効率的かつ安定した経営が可能になるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q: ファクタリングを使うと取引先に知られて信用を失いませんか?
A: 2社間ファクタリングであれば、通常、取引先への通知は不要です。
したがって、基本的には知られることはありません。一方、3社間ファクタリングでは取引先への通知と承諾が必要になります。
ただし、契約上「債権譲渡禁止」の約束があった場合でも、2020年の民法改正により、債務者(取引先)に通知や承諾を得れば譲渡可能となりました。
通知する場合は、「資金繰り改善のための正当な金融取引」であることを丁寧に説明すると良いでしょう。
最近では、多くの企業がファクタリングを利用しており、以前に比べて「怪しい取引」というイメージは薄れてきています。
特に大手企業との取引では、下請代金支払遅延等防止法の改正もあり、支払サイト短縮の流れの中で、ファクタリングを前向きに捉える傾向も出てきています。
Q: ファクタリングは違法ではないですか?闇金とは違う?
A: 正規のファクタリングは民法上認められた「債権の売買契約」であり、違法ではありません。闇金(高金利貸付)とは全く異なる合法的な金融取引です。
闇金融(高利貸し)は利息を取って貸し付ける行為で、貸金業法による上限金利規制(年15〜20%)に違反すると違法となります。
一方、ファクタリングは「貸付」ではなく「債権買取」なので、貸金業法の規制対象外です。
ただし、実質的には貸付なのにファクタリングと称する「偽装ファクタリング」と呼ばれる詐欺的行為は違法となる可能性があります。
金融庁も「額面に比べ極端に安い買取代金しか受け取れない契約は偽装貸付の疑いがある」と警告しています。
信頼できる業者を選ぶことが重要で、金融機関系のファクタリング会社や上場企業が運営するサービスであれば、法令遵守の面で安心できるでしょう。
Q: クラウドファンディングで目標金額に達しなかったらどうなりますか?
A: プラットフォームの方式によって異なります。多くの購入型クラウドファンディングでは、次の2つの方式があります。
All-or-Nothing方式: 目標金額に達しなかった場合、プロジェクト不成立となり、支援金は全て支援者に返金されます。あなたは手数料も支払わず、資金も得られません。
All-in方式(実績型): 目標達成できなくても、集まった分だけ受け取れます。ただし、手数料は発生します。
未達成だった場合でも、あなたに借金が残るわけではありません。
ただし、プロジェクト準備のための時間と労力は無駄になってしまいます。
そのため、初回は現実的な目標設定をすることをお勧めします。
例えば「最低限必要な金額」を目標に設定し、「ストレッチゴール」(追加目標)を設けるなどの工夫も有効です。
未達に終わった場合でも、得られたフィードバックや経験は次回に活かせます。
実際、再挑戦して成功するケースも多いので、一度の失敗で諦める必要はありません。
Q: クラウドファンディングで集めたお金に税金はかかりますか?
A: はい、クラウドファンディングで調達した資金は、基本的に課税対象となります。
ただし、課税の扱いは種類によって異なります。
購入型クラウドファンディング: 商品やサービスの対価として資金を受け取るため、通常は「売上」として計上され、法人税(法人の場合)や所得税(個人事業主の場合)の課税対象となります。また、消費税の対象にもなります。
寄付型クラウドファンディング: 法人が受け取る場合は「寄付金収入」として課税所得になることが一般的です。ただし、認定NPO法人など一部の法人では非課税となる場合もあります。
投資型クラウドファンディング: これは出資にあたるため、返済義務はありませんが、株式発行等の会計処理が必要です。
融資型クラウドファンディング: 借入金として処理され、返済義務があります。金利は経費として認められます。
税務処理は複雑なので、クラウドファンディングを実施する前に、税理士など専門家への相談をお勧めします。
特に、「リターン」の位置づけや、調達資金の使途に関する経費計上については、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
ファクタリングとクラウドファンディング、どちらが優れているということではなく、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
適切な選択は、あなたの会社の状況や資金調達の目的によって変わってきます。
ファクタリングは、売掛金を早期に現金化する方法として、資金繰りの改善や緊急の資金需要に対応するのに適しています。
スピードが最大の魅力ですが、手数料コストと業者選定には注意が必要です。
クラウドファンディングは、新規プロジェクトや商品開発のための資金調達に向いており、資金だけでなくPR効果やマーケティング効果も期待できます。
時間と労力がかかりますが、成功すれば大きなリターンが得られる可能性があります。
資金調達の決断をする際は、まず自社の状況を整理し、「目的」「金額」「緊急度」を明確にしましょう。
そして自社の「強み」を活かせる方法を選ぶことが成功への近道です。
必要に応じて、専門家への相談や少額からの試行も検討してみてください。
最後に、資金調達は経営戦略の一部であり、一時的な対応ではなく中長期的な視点で計画することが大切です。
適切な選択と活用によって、資金繰りの不安を解消し、事業成長への確かな一歩を踏み出しましょう。
皆さんの事業の発展を心より応援しています。


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化