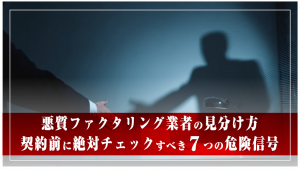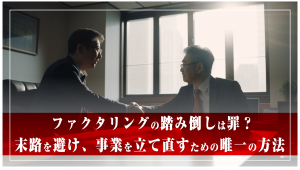「今月末の支払いが足りない…でも、来月には売掛金が入るはずなんだ。」
そんなギリギリの資金繰りに、身に覚えはありませんか?
これは私がかつて支援した、都内の建設会社経営者の言葉です。彼のように、売上はあるのに“資金が回らない”という中小企業・個人事業主は少なくありません。
多くの経営者がまず頭に浮かべるのは「銀行融資」ですが、実際に間に合うケースはごくわずか。審査・契約・入金までに数週間かかり、スピードが命の資金調達には向きません。
その代替手段としてよく候補に挙がるのが「ファクタリング」と「手形割引」です。
一見似たようなこれらの手法ですが、仕組み・コスト・リスクの構造はまったく異なります。
- 手数料が高くても倒産リスクを回避したいなら?
- 決算書に借入金を載せたくないなら?
- 金利コストを抑えつつ、得意先との関係も維持したいなら?
こうしたニーズに対し、誤った選択をすると損失だけでなく信用の低下を招くこともあります。
本記事では、ファクタリング・手形割引それぞれの特徴・メリット・デメリットを、実務経験に基づいてわかりやすく整理。
さらに、2026年に予定されている「約束手形の廃止」に向けた最新動向も踏まえ、今選ぶべき資金調達の最適解をケース別に提案します。

📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化
🛡️この記事の監修者(運営会社・税理士による共同監修)
-1024x1024.jpg)
ファクタリング関連情報の総合的な監修を行い、正確で信頼性の高い情報提供を実現しています。
ファクタリングと手形割引をざっくり比較
主要な違いを一目で把握
まずは、「そもそも何がどう違うのか?」を感覚的に掴んでいただくために、以下の比較表をご覧ください。
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 対象債権 | 売掛金 | 約束手形 |
| 資金化スピード | 最短即日(オンライン可) | 通常1~3営業日 |
| 手数料・金利 | 2者間:5~25%、3者間:1~7% | 年利換算1.5~5.5%程度 |
| リスク負担 | ノンリコース可(貸倒リスク回避) | 不渡り時は遡及義務あり |
| 信用情報への影響 | 簿外化可能(借入扱いでない) | 決算注記が必要 |
| 審査基準 | 売掛先の信用力重視 | 自社の信用力重視 |
| 取引先への通知 | 2者間:原則不要/3者間:必要 | 裏書譲渡が前提=通知必須 |
📌1行要約:
ファクタリングは「スピード&リスク回避」、手形割引は「低コスト&伝統的信用取引」型。
どちらが選ばれやすい?利用シーン早見表
| 業種・企業規模 | 向いている手法 | 解説ポイント |
|---|---|---|
| 建設業・介護業・運送業など | ファクタリング(2者間) | 売掛サイト長く、資金繰り逼迫が常態化。非通知で取引先に知られずに資金調達できるメリットが大きい。 |
| 製造業(中堅以上) | 手形割引(+でんさい) | 業界的に手形文化が根強く、信用情報への影響を許容できればコスト面で有利。 |
| フリーランス・個人事業主 | ファクタリング(オンライン) | 手形発行の取引がなく、売掛債権の資金化が主流。オンライン完結型が使いやすい。 |
| 信用格付けが高い企業 | 手形割引(銀行) | 割引料が低く済むうえ、銀行との取引実績を積むことが可能。 |
ファクタリングとは?仕組みと特徴
2者間と3者間の違い
ファクタリングとは、未回収の売掛金を第三者に買い取ってもらい、早期に現金化する資金調達手法です。
大きく分けて以下の2種類が存在します。
| 種類 | 売掛先への通知 | 手数料相場 | 与信判断の主軸 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 2者間ファクタリング | 通知不要(非公開) | 5〜25%程度 | 売掛先の信用力 | 売掛先に知られずに資金化できる。スピード重視・個人事業主にも対応。 |
| 3者間ファクタリング | 通知・同意あり | 1〜7%程度 | 売掛先の承諾 | 信用性が高く、手数料が低め。大手取引や官公需などに多い。 |
【図解】2者間 vs. 3者間ファクタリングのフロー
[自社]──(売掛債権あり)──▶ [ファクタリング会社]──▶ [資金提供]
│
▼
[売掛先] ← 通知:必要(3者間)/不要(2者間)📌1行要約:
取引先に知られたくないなら2者間、コストを抑えるなら3者間が基本。
ノンリコース契約のメリット
ファクタリングの最大の特徴は、「ノンリコース(償還請求権なし)」で契約できる点です。
これは、売掛先が万が一倒産しても、自社が買戻しを求められない契約形態。
つまり、貸倒リスクをファクタリング会社に“完全移転”できることを意味します。
このリスク転嫁により、次のようなメリットが生まれます。
- 🔹 バランスシートに債務計上されず、借入金扱いにならない
- 🔹 信用情報への影響を抑えられる
- 🔹 倒産リスクヘッジとして機能する
 山田 麻里
山田 麻里ただし、ノンリコースといっても、「偽装債権や契約違反があれば請求される」リスクはゼロではありません。契約条項をしっかり確認しましょう。
最新トレンド:オンライン完結&でんさいファクタリング
最近では、オンライン完結型ファクタリングが急速に広がっています。
- ✅ 見積〜審査〜契約〜入金までを最短即日で完了
- ✅ 必要書類はスマホやPCからアップロード
- ✅ 売掛債権を「でんさい(電子記録債権)」として登録すればさらに手数料減
といった利便性が強みです。
特に「でんさいファクタリング」は、印紙税ゼロ/紛失リスクゼロ/譲渡が簡単という特長があり、銀行・政府も推進している次世代型債権資金化スキームです。
📌1行要約:
時短・低コスト化が進む今、オンライン&でんさいの併用が主流になりつつあります。


手形割引とは?仕組みと特徴
裏書譲渡と償還請求権
手形割引とは、将来の支払いが確約された約束手形を、金融機関などに持ち込み、期日前に現金化する方法です。
このとき、企業は手形を「裏書譲渡」する形で割引業者に手形を引き渡し、利息相当の割引料を差し引かれた金額を受け取ります。
しかしここで注意すべきが、償還請求権(リコース)の存在です。
これは、万が一手形の支払人が不渡りを出した場合、割引を受けた企業(あなた)がその支払いを肩代わりしなければならないという仕組みです。
つまり、手形割引は表面的には資金化できても、貸倒リスクは自社に残る点がファクタリングとは大きく異なります。
【図解】手形割引の流れとリスク
[あなた(割引人)]───▶ [銀行・ノンバンク]──▶ 現金受取
│ ▲
▼ │
[手形受取人(取引先)]─── 不渡り発生 ─▶ 請求返還(償還請求権行使)📌1行要約:
手形割引は資金化できても、不渡りリスクは“自分の肩に残る”。
銀行割引とノンバンク割引の比較
手形割引を利用する際は、「どこで割引するか」も大きなポイントです。
主な割引先には「銀行」と「ノンバンク」の2種類があります。
| 項目 | 銀行 | ノンバンク |
|---|---|---|
| 割引料率 | 年1.5〜3.5%程度(信用力で変動) | 年3〜6%前後(やや高め) |
| 審査基準 | 厳格(決算書・信用格付け) | 柔軟(手形実績・事業性重視) |
| 必要書類 | 決算書・納税証明書・取引履歴など | 手形原本・簡易申込書など |
| 実行スピード | 1〜3営業日程度 | 最短当日も可(要事前確認) |
一般的に、信用格付けが高い企業は銀行を、スピード重視・信用力が弱い企業はノンバンクを選ぶ傾向があります。
でんさい割引の台頭
今、金融業界では手形文化からの脱却が進んでおり、その中心にあるのが「でんさい(電子記録債権)」です。
でんさいは、紙の手形の代替となる電子債権で、以下のような利点があります。
- 🔸 紛失・盗難リスクゼロ(完全デジタル)
- 🔸 印紙税不要(税コスト削減)
- 🔸 分割譲渡・早期割引がしやすい
- 🔸 登録型なので履歴管理が正確
多くの金融機関では、でんさい割引専用の金利プランを設けており、割引料率も1.5〜2.5%台と手形よりも安くなる傾向があります。
さらに、2024年11月からは「でんさいライト」という中小企業向け新制度もスタート予定で、手数料無料・利用簡素化が進められています。
📌1行要約:
「でんさい割引」は、手形割引の進化形——低コスト・安全・電子化対応が魅力。
6つの視点で違いを徹底比較
ファクタリングと手形割引は、資金化という目的は同じでも、その「方法論」と「結果」に大きな違いがあります。
ここでは、多くの経営者が意思決定時に重視する6つの軸で比較し、それぞれの適性を明らかにします。
1. 資金化スピード
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 最短実行日 | 即日(オンライン型) | 翌営業日〜3営業日 |
| 平均所要日数 | 1〜2営業日 | 2〜4営業日 |
| 時間短縮要因 | 書類電子化、非対面審査 | 銀行取引実績の有無 |
📌要点:
緊急の資金繰りにはファクタリングが優位。特にオンライン完結型なら、午前中の申し込みで当日入金も可能です。
2. 手数料・金利コスト
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 手数料相場 | 2者間:5〜25%/3者間:1〜7% | 年利換算1.5〜5.5%(日割計算) |
| コスト構造 | 手数料制(固定率) | 割引料(利率制) |
| 変動要素 | 売掛先の信用力 | 自社の財務・信用情報 |
📌要点:
「とにかく低コストで済ませたい」なら手形割引が有利。ただし、年利換算の落とし穴に注意。
ファクタリングのほうが費用は高くなるが、スピードとノンリコースの価値をどう評価するかがポイント。
3. リスク負担(貸倒・遡及)
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 債務者倒産時の影響 | ノンリコースなら返済義務なし | 不渡り時は遡及請求対象 |
| 契約類型 | ノンリコース/ウィズリコース | リコース(原則) |
| 貸倒会計処理 | バランスシート外処理 | 償却・回収不能処理 |
📌要点:
安全性を最重視するならファクタリング。特に、信用不安のある得意先が多い場合は、ノンリコース契約一択と言っても過言ではありません。
4. 信用情報・決算書への影響
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 簿外処理可能性 | ノンリコースなら可 | 注記必須(割引手形) |
| 借入扱い | 原則なし | 実質借入とみなされるケースあり |
| 信用格付けへの影響 | 低 | 中〜高(銀行借入枠にカウント) |
📌要点:
銀行評価や取引先への印象を気にするならファクタリングが有利。見せかけの健全性を維持したい局面で役立ちます。
5. 審査ハードルと与信枠
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 審査基準 | 売掛先の信用重視 | 自社の与信力重視 |
| 利用条件 | 請求書/契約書の整合性 | 決算書・事業実績の提出 |
| 与信制限 | 売掛先ごとの上限あり | 自社与信枠による上限あり |
📌要点:
財務内容に不安がある企業や創業間もない事業者には、ファクタリングの方が利用しやすい傾向にあります。
6. 取引先への開示要否
| 項目 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| 売掛先への通知 | 2者間:不要/3者間:必要 | 必須(裏書により通知) |
| 関係への影響 | 原則非開示(2者間) | 信用低下リスクあり |
| 情報管理 | 契約上の守秘義務 | 開示前提の慣行 |
📌要点:
得意先との関係維持を重視するなら「通知なしの2者間ファクタリング」が安心。逆に手形割引は、商習慣として通知が避けられません。
ケース別・選び方のポイント
「理屈はわかったけど、結局うちにはどっちが合うの?」
そんな疑問に答えるべく、ここでは典型的な資金繰り課題ごとに“最適な手法”を明示していきます。
ケース①|倒産リスクを避けたい場合
シナリオ:
建設業を営むA社。主力取引先の業績悪化が続いており、「売掛金が回収できない可能性がある」との不安が現実味を帯びてきた。手形割引だと不渡りのリスクが残るため、より安全な方法を探している。
最適解:
✅ ノンリコース型の2者間ファクタリング
- 売掛先の信用不安がある場合、貸倒リスクを完全に転嫁できるノンリコース契約が有効。
- 自社与信に不安があっても審査に通りやすく、倒産防止の保険的役割として機能。
📌ワンポイント:
手数料は割高でも、会社を守る「リスク回避コスト」として割り切るべき局面。
ケース②|コスト最優先で資金化したい場合
シナリオ:
老舗製造業のB社。自己資本比率も高く、信用格付けも良好。資金に困っているわけではないが、一時的に仕入資金が不足。少しでも手数料を抑えたい。
最適解:
✅ 銀行での手形割引(+でんさい併用)
- 信用力が高ければ、年利1.5~2.0%前後の低金利で割引可能。
- 取引先との関係も安定しており、通知や裏書による悪影響が出にくい。
📌ワンポイント:
今後のためにも、でんさいへの切り替えで印紙税と手形管理コストを削減していくのがおすすめ。
ケース③|信用情報を守りたい場合
シナリオ:
創業3年目のデザイン事務所C社。大手クライアントとの取引が増えてきたが、まだ銀行融資の信用実績は浅い。今後の資金調達も見据えて、決算書に傷をつけたくない。
最適解:
✅ ノンリコースファクタリング(オンライン対応)
- 資金調達を借入金として計上せず、簿外処理が可能なため、財務上の“見栄え”を守れる。
- 電話や面談不要のオンラインファクタリングなら、事務負担も軽く、即日対応も可能。
📌ワンポイント:
クラウド会計と連携可能な業者を選べば、スムーズに帳簿処理も可能に。
ケース④|手形文化が根強い業界の場合
シナリオ:
地方の内装工事業D社。多くの取引先が未だに約束手形での支払いを行っており、ファクタリングに切り替えると「信用不安を疑われるのでは」と懸念している。
最適解:
✅ 銀行での手形割引(段階的にでんさいへ移行)
- 業界慣習が根強い場合、無理にファクタリングへ移行せず、段階的に電子債権へのシフトが現実的。
- でんさいなら、見た目の“手形”は維持しつつ、電子化メリットも得られる。
📌ワンポイント:
業界団体がでんさい導入を進めている場合、共同利用制度を活用するのも◎。
利用手順と必要書類のチェックリスト
ファクタリングも手形割引も、正しくステップを踏まなければ審査落ちや遅延の原因になります。
ここでは、スムーズに資金化を実現するための手順と必要書類を、手法別に整理しておきます。
ファクタリング|資金化までの4ステップ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 見積依頼 | 専用フォーム・電話で問い合わせ | 2〜3社に同時依頼がベスト |
| ② 書類提出 | 請求書、取引先との契約書、通帳など | 最新月の取引実績が重視される |
| ③ 審査・契約 | 売掛先の与信調査後、契約締結 | ノンリコースの有無を要確認 |
| ④ 資金振込 | 契約完了後、最短即日入金 | オンライン型ならスピード対応も |
📎 必要書類一覧(一般的な2者間ファクタリングの場合)
- 請求書・発注書(対象売掛金の証憑)
- 取引先との契約書または継続取引実績
- 代表者身分証・法人登記簿謄本
- 直近3〜6ヶ月の入出金口座履歴(通帳写し)
- 売掛先とのメールや納品書など、商流を証明できる資料
🔍 よくある見落とし:



契約時に「償還請求特約」や「買戻し条項」がこっそり入っているケースがあります。必ず「完全ノンリコースかどうか」を事前に明示してもらいましょう。
手形割引|資金化までの4ステップ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 割引申込 | 銀行orノンバンクへ相談 | 金利交渉の余地あり |
| ② 手形持参・裏書 | 手形原本に裏書し提出 | 印紙の有無もチェック |
| ③ 割引料計算 | 満期日までの日数をもとに算出 | 日割・年利換算の仕組みを理解 |
| ④ 資金振込 | 原則翌営業日〜数日で実行 | 銀行との取引履歴が影響大 |
📎 必要書類一覧(銀行割引の場合)
- 割引希望の手形原本
- 決算書(直近2〜3期分)
- 登記簿謄本・印鑑証明
- 納税証明書(場合によって)
- 法人口座の通帳写し
🔍 よくある見落とし:
手形裏書時に印鑑間違いや空欄処理の不備があると、再発行対応や審査保留になることがあります。
特に初めての方は、銀行職員または割引業者に確認しながら進めるのがおすすめです。
見積比較で失敗を防ぐ3つのコツ
- 最低2〜3社へ同時見積依頼:
手数料や審査スピード、対応の丁寧さを比較しやすくなります。 - 「償還請求条項」の有無を必ずチェック:
ノンリコースを名乗っていても、免責事項に注意。 - 見積書に隠れコストが含まれていないか確認:
例:振込手数料、登記費用、書類作成費など。
📌1行要約:
「いかに早く資金化できるか」だけでなく、「いくら手元に残るか」で比較すべきです。
約束手形廃止後の資金調達はどう変わる?
2026年廃止の背景
経済産業省は2022年、2026年度末をめどに約束手形の利用を廃止する方針を発表しました。
背景には、以下のような構造的な問題があります。
📌【約束手形の課題点】
- 支払いサイトが長く、中小企業の資金繰りを圧迫
- 手形不渡りによる連鎖倒産リスク
- 管理・保管・印紙など、紙ベース特有の事務負担
- 国際的にはすでに時代遅れの制度(欧米ではほぼ廃止済み)
これを受けて、政府は「電子記録債権(でんさい)」の普及と「請求書早期資金化(ファクタリング)」の導入を推進。 2024年からはでんさいの簡易版「でんさいライト」もスタート予定で、中小事業者にも使いやすい環境が整いつつあります。
代替手段の本命はでんさい&ファクタリング
では、手形に代わる資金調達手段として、何を選ぶべきか?
結論から言えば、「でんさい」+「ファクタリング」の組み合わせが、最も現実的かつ強力な選択肢です。
| 手段 | 主なメリット | 向いている場面 |
|---|---|---|
| でんさい(電子債権) | ・印紙税不要 ・紛失リスクゼロ ・支払確定性が高い | BtoB長期取引・信用取引が多い業種 |
| ファクタリング | ・即日現金化可 ・倒産リスク移転(ノンリコース) ・簿外処理可能 | 売掛先が複数/資金繰りが頻繁に変動する業種 |



でんさい債権そのものをファクタリングに回すという活用法も登場しており、「支払はでんさい→資金化はファクタリング」で、安全性・スピード・コストのバランスを最適化できます。
【図解】2026年以降の主な資金調達イメージ
取引先 →(でんさい)→ あなたの会社 →(ファクタリング)→ 資金調達📌1行要約:
約束手形の時代は終わり。これからの資金繰りは「電子化×即時化」で備えるべきです。
今からできる3つの準備
- でんさいの導入準備を始める:
金融機関に口座連携や利用登録の可否を確認。 - ファクタリング業者を比較検討しておく:
特に「でんさい対応済み業者」や「ノンリコース契約」を扱う会社が◎。 - 社内の帳簿・取引書式を電子債権仕様に対応させる:
取引先との連携も含めて、事務フローの見直しが必要。
よくある質問(FAQ)
Q:ファクタリング手数料の相場はどのくらい?
A:ファクタリングには「2者間」と「3者間」の2方式があり、手数料の相場は大きく異なります。
- 3者間ファクタリング(売掛先通知あり):1〜5%前後
- 2者間ファクタリング(通知なし):5〜20%程度
→売掛先の信用力や取引金額によって変動します。
📌 ポイント:
取引先に通知しても問題がないなら、3者間を選んだ方が圧倒的に手数料は安くなります。
Q:手形割引は個人事業主でも利用できますか?
A:原則として可能ですが、銀行との取引実績や決算書提出が求められる場合が多く、ハードルはやや高めです。
- 銀行割引では「過去の手形取引実績」が審査に影響
- ノンバンク系であれば比較的柔軟な審査が期待できます
📌 ポイント:
初めて手形割引を検討する個人事業主は、ノンバンク系割引業者の方が使いやすいでしょう。
Q:ノンリコース契約でも追加請求されることは?
A:ノンリコースとは「売掛先が倒産しても請求されない」契約形態ですが、以下の場合は例外的に請求される可能性があります。
- 売掛債権が架空・虚偽だったと判明した場合
- 支払遅延が発生し、かつ契約条項違反があった場合
- 回収不能リスクの重大な隠蔽があった場合
📌 ポイント:
ノンリコース契約=無条件で責任ゼロではありません。
「契約書の読み込み」と「情報開示の正確性」がリスク回避のカギです。
まとめ
ファクタリングと手形割引は、どちらも売掛債権を使って早期に資金化できる強力な手段です。
しかしその中身を詳しく見ていくと、コスト構造・リスク分担・与信の考え方が根本的に異なります。
| 比較軸 | ファクタリング | 手形割引 |
|---|---|---|
| スピード | 即日〜1営業日 | 翌営業日〜数日 |
| リスク | ノンリコースで回避可 | 不渡り時は返済義務あり |
| 信用情報 | 簿外処理可能 | 割引手形として注記必要 |
| コスト | 手数料制(高め) | 金利制(低め) |
特に2026年の約束手形廃止を見据えると、電子記録債権(でんさい)とノンリコース型ファクタリングの併用が新たな資金繰りの主流になると予想されます。
✅ この記事のポイントまとめ
- 資金繰りの即効性を求めるならファクタリング(特にオンライン対応型)
- コストを最小限に抑えるなら手形割引(でんさいが有利)
- 信用情報を守る必要があるならノンリコース型が安心
- 2026年の手形廃止に備え、電子化体制の準備は今から必須


📊 売掛金を最速で現金化する方法
┗ 最短3時間での資金化を実現
┗ 審査通過率98%超の高い成約実績
┗ 優良ファクタリング会社のみ厳選
【今すぐ診断】「ファクタリングベスト」で売掛金の価値を最大化